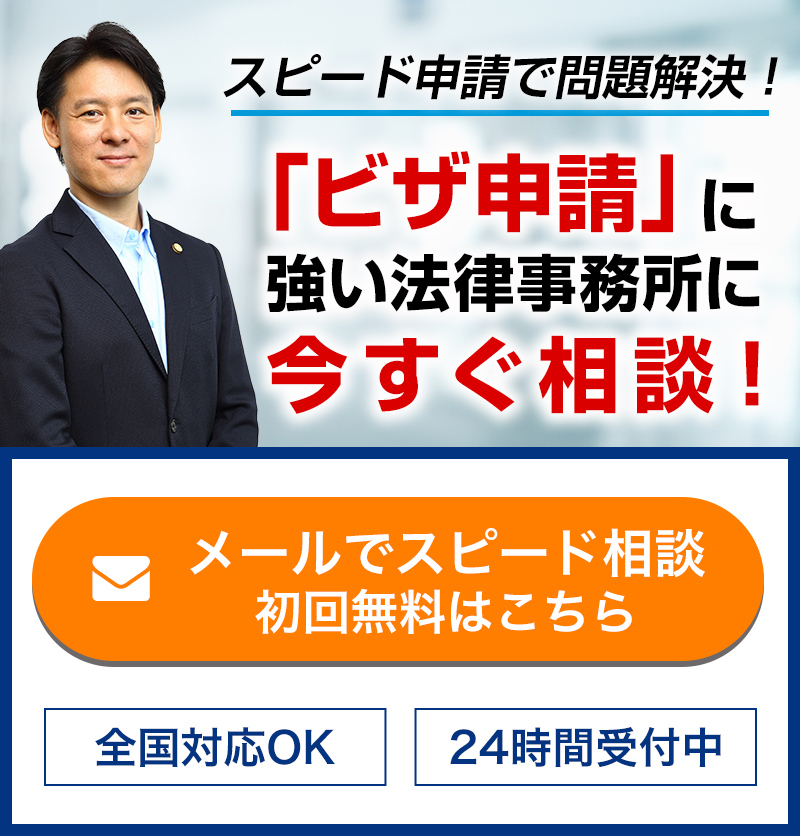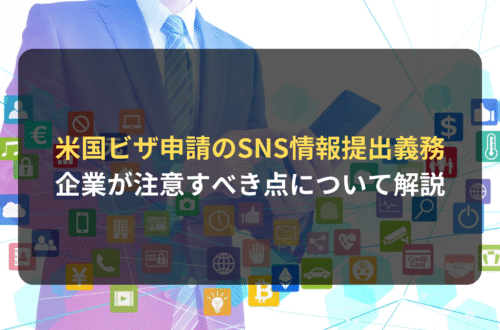はじめに:H-1B制度見直しの潮流と企業にとっての意味
米国における高度外国人労働者の主要な受け入れ制度であるH-1Bビザは、長年にわたりテクノロジー、研究、製造など幅広い産業の国際競争力を支えてきました。しかし2025年、トランプ政権は新たな大統領令「Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers」を発表し、H-1Bビザを含む非移民労働者の受け入れを厳格化する方針を打ち出しました。この動きは、不法就労の抑止や米国人雇用の保護を目的とする一方で、海外人材に依存するグローバル企業にとっては実務上の大きな負担となり得ます。さらに、H-1B申請に対する新たな課金制度の導入や、抽選(ロッタリー)方式の見直しなど、企業側のコストや手続きの透明性に関わる改革も進行中です。
日本企業にとってもこの影響は無視できません。研究開発拠点の設置、米国法人への技術者派遣、現地での人材採用など、国際事業展開のあらゆる段階で調整を迫られる可能性があります。ビザ取得・更新の負担増やスケジュールの不確実性は、プロジェクトの遅延や人材戦略の見直しにつながりかねません。
この記事では、H-1Bビザを取り巻く最新の規制動向を整理し、新たな厳格化措置の具体的内容、日本企業が直面する実務的リスク、そして代替となる人材確保の手段について詳しく解説します。
新たな厳格化措置の概要
トランプ政権によるH-1Bビザ制度の見直しは、従来の運用を根本から揺るがす内容となっています。新たに発表された大統領令では、外国人労働者の入国・雇用を制限するための包括的な措置が導入され、雇用主には追加的な金銭的・手続的負担が課されることになりました。さらに、抽選制度の見直しや高賃金人材の優遇策など、ビザ発給の仕組みそのものが再構築されつつあります。ここでは、今回の大統領令および関連制度改正の要点を整理し、企業が留意すべき主要な変更点を具体的に解説します。
大統領令「Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers」のポイント
2025年9月19日、トランプ政権は「Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers(特定非移民労働者の入国制限)」という大統領令を発し、9月21日午前0時1分(東部時間)から発効させました。
この大統領令は、国外にいるH-1B 非移民労働者が米国に入国・再入国する際に適用され、一定の条件を満たさない場合はビザ取得や入国が認められない旨を規定します。
特に、雇用主が追加支払いを行っていない場合には、H-1B申請を審査しない・承認しない方向とされており、入国許可の制限が新設されています。
また、この措置は 12か月間(2025年9月21日〜2026年9月20日)を期限としており、延長や変更は将来的な政府判断および議会の動向にかかっています。
新規 H-1B 申請への $100,000 追加課金制度とその適用範囲
この大統領令の中核となる措置として、H-1B 非移民労働者を国外から米国に入国させるためには、雇用主が 1人あたり $100,000 の追加支払い(補足料金) を行うことが義務づけられています。申請時にこの支払いの証明がなければ、USCIS や国務省はビザ申請や入国承認を認めないとされます。
この補足料金は、2025年9月21日以降に提出される新たな H-1B 申請 に対して適用され、既存の H-1B 保有者や既に承認済みの申請には遡及適用されないとされています。
ただし、この支払義務が一律適用されるわけではなく、国家利益例外(National Interest Exemption:NIE)などの免除措置が認められる可能性も明示されています。
抽選制度(ロッタリー方式)見直し・重み付け方式導入の動き
H-1Bビザ制度はこれまで多数の申請がある年度には抽選(ロッタリー方式)で選定される慣行がありましたが、トランプ政権下ではこの方式を見直す動きが浮上しています。複数の報道によれば、ロッタリー方式そのものを廃止または縮小し、申請者の賃金水準や技能レベル等を重み付けの基準として優先付けする方式への移行案が検討中です。これにより、より高賃金・高度人材を優遇し、低賃金案件や応募者の乱発を抑制する狙いがあります。
現時点では制度案段階であり、最終的な実施形態や適用時期には不確定性が残りますが、企業は抽選制度の将来的な変化を見据えて準備を進める必要があります。
適用除外・国家利益例外(National Interest Exemption: NIE)制度
追加支払い義務や入国制限には、すべてのケースが対象とされるわけではありません。大統領令および関連ガイダンスには、国家利益例外(NIE: National Interest Exemption)~具体的には、医療機関、研究機関、公共保健、国家安全保障やインフラ分野など、合衆国の国家利益に資すると判断される雇用主・職種については、追加料金支払い義務や入国制限が免除される可能性があります。
ただし、NIEは随時・事例ごとの裁量判断となるため、申請書類や根拠説明が複雑になりやすく、必ず認められるわけではありません。例外制度の適用要件・手続詳細はまだ法令または運用指針として固まっておらず、将来変更され得る点に注意が必要です。
日本企業・グローバル企業に及ぶ影響
海外人材採用戦略への制約と不確実性
H-1Bビザの厳格化は、米国での現地採用や海外からの人材登用を行う日本企業にとって、採用計画そのものを再考せざるを得ない状況を生み出しています。申請要件が強化され、抽選制度も高賃金人材を優遇する方向に再構築されることで、これまで比較的柔軟に採用できていた新卒・中堅層の人材が対象外となるリスクが高まります。さらに、大統領令による追加費用義務や入国制限は、採用時点でのコストや時間を不確実にし、企業側が長期的な雇用を見据えた計画を立てづらくします。結果として、採用枠を米国外に移す、または現地法人を通じた人材確保へシフトする企業が増える可能性があります。柔軟な採用戦略を維持するためには、各国ビザ制度の比較検討と早期の申請準備が不可欠です。
社員の再入国・出張・転勤リスク
今回の大統領令では、国外に滞在中のH-1B保持者にも入国制限が及ぶため、出張や一時帰国を行った社員が再入国できなくなるリスクが生じます。特に、雇用主が新たな追加費用を支払っていない場合、既存のビザ保有者であっても米国への再入国が認められない可能性があります。これは、米国現地法人や研究拠点で働く技術者・駐在員の業務継続に直接的な影響を与えるものです。短期出張や国際会議への参加も制限を受けやすくなり、プロジェクトの進行や顧客対応に支障をきたす恐れがあります。企業としては、対象社員の渡航計画を慎重に管理し、必要に応じて代替の勤務形態(リモート勤務や他国での一時勤務)を用意するなど、リスクヘッジ体制の整備が求められます。
コスト上昇(賃金水準見直し・手数料負担増)
H-1B申請1件あたりに課される追加費用10万ドルは、企業の採用コストを劇的に押し上げる要因となります。特に中小企業やスタートアップにとっては、この負担が新規採用の抑制や人材計画の見直しにつながりかねません。また、抽選制度見直しによって高賃金労働者が優遇される方向性が示されたことで、雇用主は提示賃金を引き上げざるを得ず、結果的に賃金水準全体の上昇圧力がかかります。加えて、ビザ更新や延長の際にかかる弁護士費用・事務手数料・時間的コストも増大し、総合的な人件費負担が高まる見込みです。これらのコスト増は、米国拠点の採算性や投資判断に影響を及ぼす可能性があり、企業は採用計画を財務面から再検討する必要があります。
代替手段と戦略的選択肢
他種非移民ビザ(Lビザ、Oビザ、Eビザなど)の活用可能性
H-1Bビザの厳格化に伴い、企業は他種の非移民ビザを柔軟に活用する戦略が求められます。たとえば、Lビザ(企業内転勤者ビザ)は海外子会社・関連会社からの転勤者に適用され、H-1Bより審査基準が明確で上限枠の制限もありません。また、特定分野で卓越した能力を持つ個人に発給されるOビザ、日米間の条約に基づき投資・貿易を行う企業関係者が利用できるEビザも代替手段として有効です。これらのビザは職務内容や企業形態により適用要件が異なるため、法務・人事部門は各制度を比較し、自社の事業モデルに最も適した申請ルートを選択することが重要です。
グリーンカード(永住権)を見据えた中長期人材戦略
H-1B取得が難しくなる中で、米国で長期的に働くための手段としてグリーンカード(永住権)の活用を視野に入れる企業が増えています。特に、研究開発職や管理職など、長期雇用を前提とするポジションでは、永住権申請を前提にした採用・育成プランを設けることで、安定的な人材確保が可能となります。企業としては、PERM労働認定プロセスやEBカテゴリ(EB-1/EB-2/EB-3)などの永住権申請手続きを理解し、弁護士と連携しながら段階的に進める体制を整えることが重要です。これにより、優秀な外国人社員に対してキャリアの長期的見通しを提示でき、企業への定着率向上にもつながります。
他国拠点・グローバル分散配置によるリスクヘッジ
米国ビザ政策の不確実性が高まるなか、他国での拠点展開や人材分散配置は現実的なリスク回避策として注目されています。たとえば、カナダ、メキシコ、欧州主要国、シンガポールなどは、高度人材受け入れ政策を強化しており、H-1B制限下での代替拠点として有力です。特にカナダでは「Global Skills Strategy」など迅速な就労許可制度が整備されており、米国での業務を補完する研究・開発拠点として活用する企業が増えています。また、米国法人を中心に据えながらも、業務プロセスを国際的に分散させることで、法規制リスクとビザ関連コストを同時に抑制することが可能になります。
リモート勤務・クロスボーダー業務設計の検討
近年のテクノロジー進展により、リモートワークやクロスボーダー業務の設計が、現実的な代替策として企業戦略の一部に組み込まれつつあります。ビザ制限によって現地勤務が難しい場合でも、クラウド環境や安全な通信基盤を活用すれば、海外拠点から米国チームにリモートで参加することが可能です。特に開発職やバックオフィス業務では、居住地に縛られない勤務形態を導入することで、ビザ取得の制約を受けずにグローバル人材を活用できます。また、企業はリモート勤務に関する税務・雇用契約・データ保護の法的リスクを把握し、各国法規に準拠した就労体制を設計する必要があります。柔軟な働き方を制度として整えることが、今後の国際人材戦略における競争力を左右する要素となるでしょう。
海外進出・海外展開への影響
H-1Bビザ制度の厳格化は、単に米国内での雇用・派遣に影響するだけでなく、日本企業の海外展開全体に大きな戦略的見直しを迫る要因となっています。これまで、米国は高度人材の活用や現地法人の設立において最も重要な市場の一つでしたが、ビザ取得や更新のハードルが上がることで、計画段階から法的・実務的な準備をより慎重に行う必要が生じています。特に研究開発拠点、製造ラインの技術指導、マネジメント人材の派遣といった分野では、入国制限や追加課金の影響が業務継続に直結するため、早期のリスク評価と代替案の構築が欠かせません。
このような環境下で、企業が安定した海外事業運営を行うためには、移民法専門家や弁護士との連携が不可欠です。ビザ制度は政権交代や政策転換によって頻繁に更新されるため、社内での判断だけでは対応が難しいケースが多く見られます。専門家と協力し、各ビザカテゴリー(H-1B、L、O、Eなど)の適用可能性やリスクを精査し、複数の申請ルートを確保しておくことが有効です。また、米国内の雇用契約や税務・社会保険の取り扱いにも影響が及ぶ場合があり、移民法のみならず労働法や商法などの民法的観点からも包括的に検討することが求められます。
さらに、今後の制度動向と注意点として、今回の大統領令は2026年9月までの時限措置である一方、政権がこの方針を延長・恒久化する可能性も指摘されています。加えて、米国議会ではH-1B制度の恒久的改正案(高賃金優遇や定員制限の縮小)が議論されており、企業は法改正の行方を注視する必要があります。制度が流動的であることを踏まえ、現行ルールのもとで確実に申請を行うと同時に、将来変更された場合のシナリオを事前に想定しておくことが重要です。特に新規派遣・採用を予定している企業は、申請時期や就労開始日を柔軟に設定し、政策変更による影響を最小限に抑える体制を整えるべきでしょう。
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、国際人事・海外進出に関する豊富な実務経験を有する弁護士・行政書士が連携し、米国ビザ制度に関する最新情報の提供から、具体的な申請戦略の立案、現地法務リスクの評価まで総合的にサポートしています。H-1Bをはじめとする非移民ビザの申請・更新手続き、代替ビザの検討、グローバル人材戦略の法的アドバイスなど、企業の国際展開を法務面から力強く支援します。米国での人材派遣や採用計画に不安を感じる際は、いつでもご相談ください。
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00