
目次
外国人ビザ申請手続きの全体像
出入国在留管理局(入管)の審査姿勢・・・立証責任は申請人自身!
ビザ申請では、日本に在留できる条件を満たしていることを、申請人自身が証明する責任があります。
つまり、複雑な入管法や関連規定を理解し、適切な書類内容で立証しなければなりません。
条件を満たしていても、証明方法が不適切で審査官に伝わらなければ不許可になってしまいます。
提出された書類だけでは情報が足りないと入管が判断した場合、審査中に追加資料の提出を求めてくれることもありますが、これは親切心によるもので、何も求められずに不許可になることもあります。
「必要書類は全て揃えて、受理されたから大丈夫だろう」という考えはとても危険と言えます。
・入国・在留手続の流れについて<
入管業務は行政裁量が広範である
ビザ申請手続きにはいくつか種類があります。
▶参考情報:出入国在留管理庁ホームページ – 法務省
・手続の種類から探す・・・ 1 在留申請
- (1)在留資格認定証明書交付申請
- (2)在留資格変更許可申請
- (3)在留期間更新許可申請
- (4)在留資格取得許可申請
- (5)永住許可申請
- (6)資格外活動許可申請
- (7)就労資格証明書交付申請
- (8)在留資格の取消しについて(解説)
ビザ申請手続きの中でも、特に(1) (2) (3)が代表的です。
(1)在留資格認定証明書交付申請(略称:認定 (外国から日本に呼び寄せる) )
例:母国の会社ではなく日本の会社で働きたい
・就労ビザとは?申請要件を含めた取り方について、ビザ申請に詳しい法律事務所が解説
・技術・人文知識・国際業務ビザとは?申請の要件やポイントを法律事務所が解説
・「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就労するには|業務内容と申請方法について法律事務所が解説
(2)在留資格変更許可申請(略称:変更 (今のビザを別のビザに変更する) )
例:留学ビザで日本の学校等を卒業し、そのまま日本に在留し起業したい
・「経営管理ビザ」の基礎知識と留意ポイントをまとめて解説
・外国人留学生が日本で起業するためには?特定活動44号の制度概要と活用できる在留資格のポイント
・経営管理ビザの審査期間は?申請から取得までの流れを徹底解説
(3)在留期間更新許可申請(略称:更新 (今のビザを更新する) )
例:日本で暮らす外国人夫婦で、外国人夫の扶養を受けている外国人妻が、現在保有の家族滞在ビザを更新したい
・家族滞在ビザの申請|必要書類や就労制限など、在留資格のポイントを法律事務所が解説
ここで大事なのは、特に(2)変更と(3)更新において、行政裁量が広範である⇒許可されにくい場合もあると言うことです。
日本の入管法において、在留資格の変更(第20条第3項)や在留期間の更新(第21条第3項)は、共通して「相当の理由があるときに限り、許可することができる」と定められています。
この「相当の理由」は具体的に定義されておらず、また「許可しなければならない」ではなく「許可することができる」という表現が用いられています。
これは、申請内容が形式的な条件を満たしていても、審査側が個別の事情を総合的に判断し、許可しない選択も可能であることを意味します。
そのため、入管には広範な行政裁量が認められており、その結果として、必ずしも申請が容易に許可されるとは限らない場合があると言えます。
外国人ビザ申請手続きの注意点
申請が「受理」されても申請が「許可」されるとは限らない
ビザ申請において、必要書類を提出し、入管の窓口で受け取ってもらうことを「受理」と言います。
書類に不備があると受理してもらえないため、受理されると「これで一安心」と感じるかも知れません。
受理後の審査プロセスでは、提出書類の内容が詳細にチェックされ、申請人の背景や経歴、申請理由の妥当性などが広い裁量で総合的に判断されます。
前の文章でも触れましたが、形式的な条件を満たしていても、説明が不十分だったり、疑義が生じる点があったりすると、追加資料の提出を求められたり、不許可となったりする可能性があります。
受理されたからといって安心せず、審査期間中も適切な対応を心がけるよう注意しましょう。
適切な対応の具体例として、実は申請が受理された後でも、任意で追加書類を提出することが可能です。
一度受理されたからといって、その後の書類提出ができなくなるわけではありません。
審査に有利に働くと思われる資料があれば、審査中にどんどん提出して構いません。
ただし、どのような書類が審査にプラスの影響を与えるかは、専門的な知識がなければ判断が困難です。
専門家でない者の判断では、かえって審査官に疑念を抱かせるような不適切な書類を提出してしまうリスクもあります。
経験豊富な専門家であれば、個別のケースに応じて「こういった書類はお持ちですか?もし無ければ、代わりにこのような書類で代用できます。」といった具体的で的確なアドバイスを提供できます。
このような柔軟で戦略的な対応こそが、許可率向上の鍵と言えます。
いったん不許可になると再申請の難易度が上がる
ビザ申請で不許可になった場合、その記録は入管に残り、次の再申請時に必ず参照されます。
不許可歴があることで、審査官も慎重にならざるを得ず、「なぜ以前不許可になったのか」「その問題は本当に解決されたのか」という新たな審査要素が加わります。
その結果、申請人はより厳格な審査を受けることになり、通常よりも多くの証明書類や詳細な説明が求められ、再申請の難易度が大幅に上がってしまいます。
一度「不許可」の履歴が残ってしまうと、再申請から許可を勝ち取るには時間も労力も大幅に増大する可能性が高いため、最初の申請から慎重に準備することが極めて重要であることには注意が必要です。
本人申請の特徴と専門家による取次申請の特徴
自分で申請する本人申請
申請人自身が入管法や関連規定を理解し、必要書類の一覧に沿って、資料を収集し、書類を作成する必要があります。
複雑な法的要件を調べ、どのような書類が必要か、どのように証明すべきかを判断しなければなりません。
また、混雑している窓口に出向いて申請したり、複雑な操作でオンライン申請を行ったりと、相応の時間と労力が必要になります。
本人申請の大きなメリットは費用を抑えられることですが、法的知識や実務経験が限られているため、適切な立証方法の選択が難しく、結果として不許可となるリスクも考慮する必要があります。
専門家による取次申請
申請人に代わって入管への提出書類の作成、申請手続き、照会対応、書類の受領などを行います。
申請人は窓口に足を運んだり、複雑なオンライン申請の操作を習得したりする負担から解放されます。
専門家は実務経験と法的知識を活かして、個別のケースに応じた書類構成や説明方法、申請タイミングなどを提案し、審査官に対してより説得力のある立証を行うことが可能です。また、将来的な永住や帰化申請などを見据えたアドバイスも可能です。
専門家への報酬は発生しますが、その分、許可の可能性を高められるという利点があります。
どちらの方法を選択するかは、申請人の状況、時間的余裕、予算、そして案件の複雑さなどを総合的に考慮して判断することが大切です。
まとめ
専門家への依頼が推奨される理由
本人申請では「条件を満たしているから大丈夫だろう」という認識で進めてしまう傾向がありますが、実際には条件を満たしていることを適切に証明できなければ不許可となり得ます。
専門家による取次申請では、行政裁量が大きく働く審査において、申請人にとって最も有利な角度から事案を整理し、戦略的に申請を進めることができるため、許可の可能性を大幅に向上させます。
ビザ申請において行政裁量が広範に認められているということは、単に審査が厳しくなるという意味だけではありません。
むしろ、この裁量の存在は、申請の進め方次第で審査官の判断を申請人に有利な方向へ導く余地があることを意味しています。
経験豊富な専門家であれば、過去の事例や審査傾向を踏まえて、どのような書類をどのタイミングで提出し、どのような説明を加えれば審査官の理解を得やすいかを的確に判断できます。
また、審査中に追加資料の提出を求められた場合や、想定外の照会があった場合にも、専門家なら迅速かつ適切に対応し、逆に許可へのチャンスに変えることも可能です。
こうした戦略的なアプローチは、法的知識と実務経験が豊富な専門家だからこそ実現できます。
確実性を重視し、貴重な時間を有効活用したい場合には、専門家への依頼を検討されることをお勧めします。
・在留資格・ビザ申請サービス
ビザ申請サービスのご案内
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、外国人のビザに関する無料相談を受け付けています。申請書類の適切な準備から法的アドバイス、そして最適な申請戦略の立案まで、幅広くサポートいたします。
当法律事務所では、スタッフ全員が行政書士の資格を持ち、弁護士の指導のもと、ビザ申請・外国人雇用・労務・契約書など、法務の専門知識を持ったプロフェッショナルがそろっています。ご安心してご相談ください。
「弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所」に問い合わせる方法
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の内容は、2025年6月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00


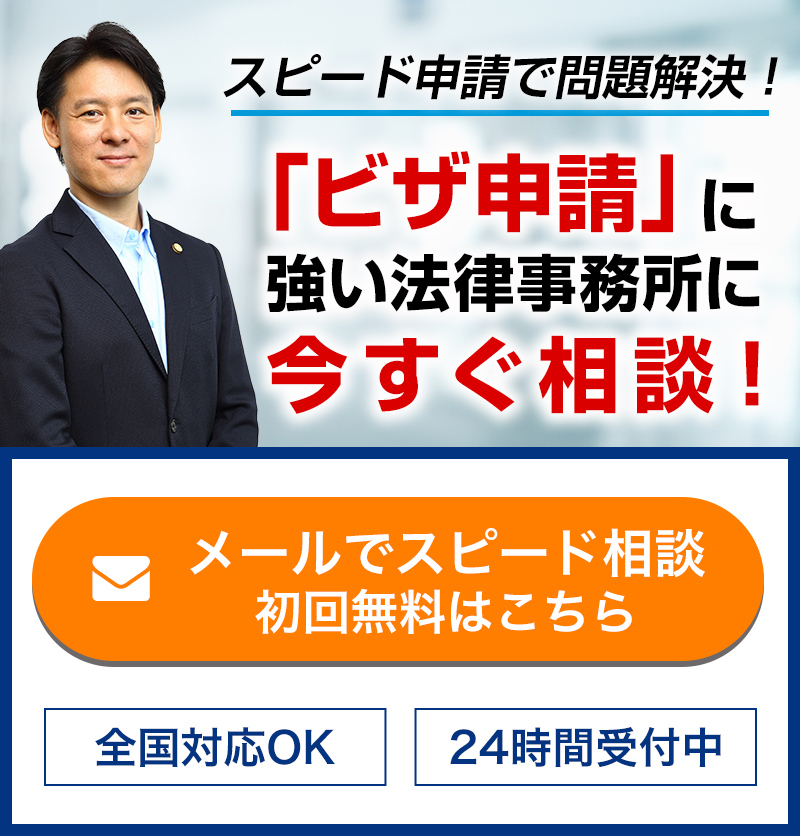
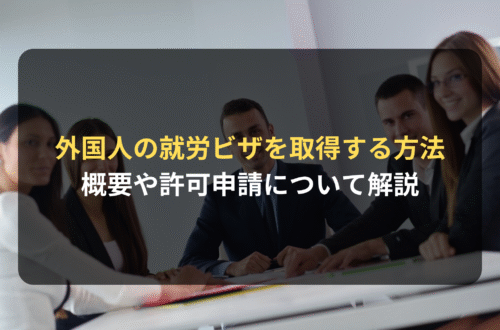
とは-申請方法・注意点を徹底解説-500x330.png)
