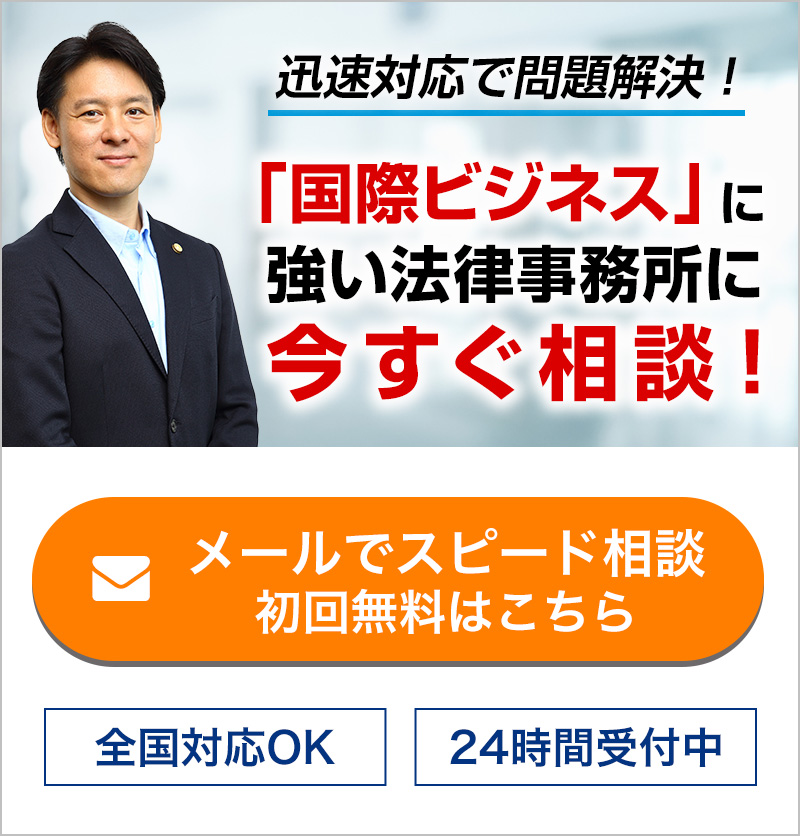目次
はじめに
グローバル市場へのアクセス手段として、越境EC(国境を越えた電子商取引)の重要性は年々高まっています。特に近年では、円安傾向やデジタルインフラの発展を背景に、多くの日本企業が海外展開を視野に入れたEC事業を本格化させています。しかし、国際取引において避けて通れないのが「関税」の問題です。輸出入にかかる関税は、販売価格や収益構造に直接影響を及ぼし、消費者の購買行動や企業の価格戦略、さらにはサプライチェーン全体にまで広範な影響を及ぼします。
特に米国市場では、関税政策が政権交代ごとに大きく変動する可能性があり、企業にとっては不確実性の高いリスク要因となっています。そのため、越境ecを行う上では、各国の関税制度や政策動向を正しく理解し、柔軟かつ戦略的に対応することが不可欠です。
この記事では、関税が越境ECに与える影響や、2025年以降の米国市場の動向、そして日本企業が取りうる具体的な対応策について、最新情報を交えながらわかりやすく解説します。
関税が越境ECビジネスに与える影響とは
関税コストの上昇がもたらす消費者行動の変化
越境ECにおいて、関税は企業だけでなく消費者にとっても大きな影響を及ぼすコスト要因です。とくに米国市場では、近年の関税政策の変動により、中国をはじめとする海外製品に高い関税が課せられるようになりました。これにより、輸入製品の小売価格が上昇し、消費者が「価格に敏感」になる傾向が強まっています。
多くの消費者は、関税によって価格が上昇した商品に対して購入をためらうようになり、結果としてカート離脱率の上昇や購入単価の低下といった行動変化が発生しています。また、関税の存在が明示されていない場合、購入後に追加請求される「予期せぬ関税」に対して不満を抱き、リピーターの減少やブランドロイヤルティの低下にもつながりかねません。
このような背景から、企業は消費者目線での「価格の透明性」や「関税込みの価格表示」など、信頼を損なわない販売戦略が求められています。関税コストを正しく把握し、それをどう消費者に伝えるかが、越境ecの成否を左右する重要なポイントとなるでしょう。
サプライチェーンと価格戦略への影響
関税の変動は、越境ECを展開する企業のサプライチェーンにも大きな影響を及ぼします。関税率の上昇は、仕入コストや物流コストの増加を招き、利益率の低下を引き起こす可能性があります。その結果、多くの企業が仕入先の見直しや生産拠点の移転、ルートの再構築を余儀なくされています。
たとえば、米国での関税強化により、中国からの製品輸入に対するコストが急増したことを受けて、東南アジア諸国へのシフトが進んでいます。このような対応には、法規制や品質基準の違い、物流インフラの整備状況などを総合的に考慮する必要があり、柔軟かつ戦略的なサプライチェーンマネジメントが求められます。
また、関税は販売価格の設定にも直結します。過度な価格転嫁は競争力を失う原因となり、かといって企業側の負担増も長期的には持続困難です。したがって、関税負担を最小限に抑える原産地証明の活用やFTA(自由貿易協定)の活用、現地法人による現地調達の検討など、複数の価格戦略を組み合わせて最適化を図る必要があります。
関税の影響を受けにくいサプライチェーンをいかに構築するかは、海外展開における競争優位性を確保するカギとなります。
米国市場を例に見る関税政策の変化と今後の展望
トランプ政権以降の関税政策の流れ
2018年発足の第一次トランプ政権では「アメリカ・ファースト」の方針のもと、中国をはじめとする貿易相手国に対して大規模な関税措置を導入しました。特に注目されたのが、中国からの輸入品に最大25%の追加関税を課す「セクション301関税」であり、これは電子機器、衣料品、日用品など幅広い製品に影響を与えました。
この政策は米中貿易戦争と呼ばれる大規模な貿易摩擦、対立を招き、サプライチェーンの見直しや輸出および輸入の減速を引き起こしました。その後、バイデン政権に移行した後も、これらの関税措置は大部分が維持されており、大きな緩和には至りませんでした。これは、国内製造業の保護や対中競争への継続的な対抗姿勢が背景にあります。
その後、2024年11月の米大統領選挙において、トランプ氏が共和党候補として再選を果たし、2025年1月20日から第2次トランプ政権が始動しました。新政権は再び「アメリカ・ファースト」の方針を掲げ、貿易政策においても強硬な姿勢を打ち出しています。
このように、政権交代を経ても米国の関税政策は一貫して保護主義を基調としており、特に第2次トランプ政権ではさらなる強化が想定されます。日本の企業が米国の市場に進出・展開するにあたっては、関税の影響を前提にした柔軟かつ実践的な戦略設計が不可欠です。
小売業者への影響
関税政策の強化は、米国内の小売業者にとって深刻な負担となっています。とりわけ海外から商品を輸入して販売するビジネスモデルを採用している小売業者は、仕入コストの上昇という形で直接的な影響を受けています。この結果、小売業者は価格転嫁、利益率の圧縮、販路の見直しなど、さまざまな対応を迫られています。
さらに、関税による価格上昇は、消費者の購買意欲の減退や競争力の低下を招いており、特に低価格帯の商品を扱う企業では販売不振につながるケースが目立ちます。また、米国内でも「関税による消費者負担の増大」、商品の最終価格に上乗せされる税金への批判が高まっており、一部の業界団体は関税撤廃や見直しを求める動きを強めています。
日本企業にとっては、こうした小売業者側の動向を理解し、特定の地域の市場特性に合った協業先の選定や取引条件の交渉に活かすことが重要です。信頼できる現地パートナーとの連携や、コスト削減を支援できる商品構成・価格設計を提案することで、競争力を維持するチャンスにつながります。また、こうした情報を継続的に得るためには、各業界の公式サイトや貿易機関の資料などを活用し、常に最新の動向にアクセスしておくことが不可欠です。
2025年以降の見通しと企業の対応戦略
2025年の新政権発足以降、米国の関税政策は依然として不透明な要素を多く含んでいます。こうした不確実な状況下で企業が取るべき対応は、「リスク分散」と「柔軟な対応力の確保」です。具体的には、複数の仕入先や製造国の確保、関税のかからない商品構成の検討、現地倉庫の利用などが考えられます。また、越境ECにおいては、事前に最終的な関税額や消費税等の課税項目をシミュレーションし、価格表示やプロモーションに反映させることが、顧客満足度の維持に直結します。
関税の影響を受けやすい商品や一般的な輸出入にかかるコスト構造を正確に把握しておくことは、事業計画の策定において非常に重要です。そのため、制度や税率の一覧を把握し、各国の貿易条件を比較・分析する姿勢が求められます。
日本企業が米国市場で継続的に成長を図るためには、政治・経済の変化に敏感に反応し、柔軟かつ中長期的な視野で対応策を講じる姿勢が求められます。現地市場の動向と自社の体制を照らし合わせたリスク対策をまとめ、実行可能な計画に落とし込むことで、不確実性の高い環境下でも安定した海外展開が可能となります。
関税コストへの対応策:日本企業が取るべきアプローチ
関税を考慮した価格・配送戦略の構築
関税が越境ECのコスト構造に与える影響は大きく、これを踏まえた価格戦略と配送戦略の見直しは、収益性と競争力を維持するうえで欠かせません。関税によって発生する追加コストをどのように価格に転嫁するかは、ターゲット市場の価格感度や競合状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。たとえば、商品価格に関税を含めた「関税込み価格」での表示を行うことで、消費者に安心感を与え、購入率の向上を図る手法も有効です。
また、配送面でも工夫が求められます。関税の計算方法は配送方法やインコタームズ(国際商取引条件)によって異なる場合があるため、DDP(関税・送料込み)やDAP(関税別)のどちらを採用するかによって、最終的なコストや顧客満足度が大きく変わります。物流業者や通関業者との連携を通じて、最もコスト効率の良い配送ルートや通関方式を確保することも重要な戦略の一部です。
現地拠点やパートナー企業の活用
関税による負担を軽減するためには、現地拠点の設置や信頼できるパートナー企業の活用が有効な手段となります。例えば、米国市場をターゲットとする場合、米国内に物流センターや倉庫を設けることで、発送にかかるリードタイムや関税の課税タイミングを調整し、コストの最適化を図ることができます。また、一定の取引規模が見込まれる場合には、現地法人を設立して「現地調達・現地販売」を行うことで、国際取引として関税が課される流通プロセス自体を縮小することが可能です。この点は、多くの越境EC企業にとって有効な関税戦略のひとつです。
一方で、現地パートナーとの連携によって、販売、物流、カスタマーサポートといった各業務を現地で一貫して対応する体制を整えることも、非常に有効です。各国の制度や文化は日本と異なり、法規制への適応や顧客対応にも柔軟さが求められます。そのため、現地事情に精通したパートナー企業との協業は、通関に関する関連トラブルの回避や、スムーズな事業運営につながります。
また、関税制度は頻繁に変更される傾向があるため、最新の通関ルールや税制動向に基づいた対応が必要です。現地に根差した情報網を持つパートナーの存在は、そうした変化への迅速な対応において特別な価値を発揮します。こうした体制構築により、企業は継続的かつ安定的に海外市場へ商品を供給する体制を確立することができるでしょう。
税関手続き・HSコードの適切な管理
越境ECにおいて関税負担を抑えるためには、輸出入時の税関手続きとHSコード(Harmonized System Code)の管理を正確に行うことが不可欠です。HSコードとは、国際的に標準化された品目分類コードで、税率の決定に直接関係する重要な情報です。不適切なコードの使用は、過剰な関税の支払いにつながるだけでなく、税関による調査や罰則の対象となるリスクもあります。
そのため、日本企業は自社製品に適したHSコードを正確に把握し、各国の関税率や通関要件を事前に確認しておく必要があります。また、原産地証明やインボイス(商業送り状)、パッキングリストといった書類の正確な作成・提出も求められます。これらの手続きをミスなく行うことで、税関での滞留を防ぎ、物流の遅延リスクも最小化できます。
さらに、特恵関税制度(FTA/EPA)の活用により、関税を軽減または免除できる可能性もあるため、該当条件を満たす取引では積極的に制度を活用することが推奨されます。税関対応の正確性は、コスト削減だけでなく、事業の信頼性を左右する要素となるのです。
海外展開における関税対策を弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に相談したい方はこちら
越境ECの税務を専門家に依頼するメリット
越境ECにおける関税対応は、各国ごとに異なる制度や規制、分類コード(HSコード)などの複雑な知識を要するため、企業の自力対応には限界があります。特に、取引する物品の種類によって関税率や必要な書類が大きく異なるため、誤った対応は税関でのトラブルや余分なコストの発生につながるおそれがあります。そのため、通関時の申告内容や書類作成には細心の注意が必要です。
こうしたリスクを未然に防ぐためには、法務・税務の専門家によるサポートが不可欠です。弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に相談いただくことで、企業の越境EC事業における税務・関税の現状を正確に分析し、最適な対応策を法的観点からご提案いたします。専門家によるアドバイスにより、不要な手間やコストを削減できるだけでなく、長期的に見て持続可能な事業運営に資する戦略の構築が可能となります。貿易実務に精通した弁護士の支援は、複雑な国際取引に取り組む日本企業にとって大きな安心材料となるでしょう。
越境EC法務・税務支援サービスのご案内
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、越境ECや海外展開を行う企業様向けに、関税対応を含む国際取引に関する法務・税務の支援を行っております。関税分類(HSコード)の適正な判断やFTA/EPAの活用、税関とのトラブル対応、米国をはじめとする主要国の関税制度・税制に基づくリスク分析など、実務に即した支援が可能です。また、契約書や取引条件の整備を通じて、関税負担の軽減やトラブルの未然防止にも貢献いたします。
当事務所の越境EC支援サービスの詳細については、以下のページで詳しく紹介しております。事前の対策が将来的なトラブルやコスト削減に直結しますので、まずはお気軽にご相談ください。
当法律事務所では、グローバル事業の法務・税務の両面から専門性の高いサポートを提供しております。関税への対応をはじめ、海外進出に関する幅広い法的課題についても対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
「弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所」に問い合わせる方法
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の内容は、2025年4月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|