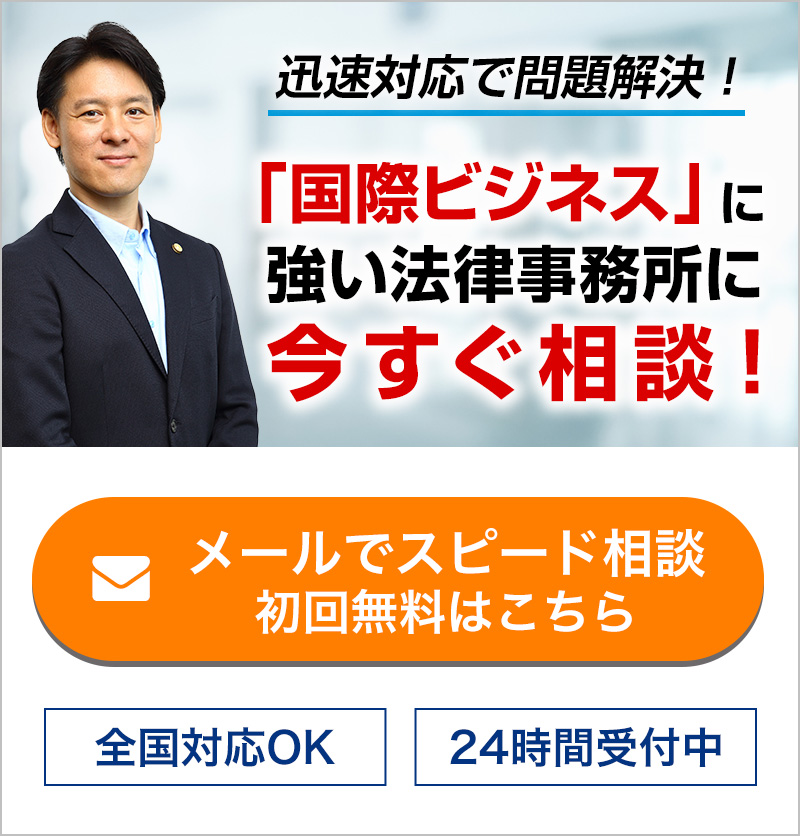目次
はじめに
AI(人工知能)の急速な発展に伴い、その利活用に対する法的規制も各国で整備が進んでいます。中でも米国は、AIを活用した採用・評価システムや消費者分析ツールなどが広く普及している一方で、連邦レベルでの統一的な法整備が進んでおらず、州ごとに異なる規制が次々と導入されている状況です。とりわけ、プライバシーや差別防止に関する意識が高いカリフォルニア州は、AI規制の先端を行く地域として、他州や連邦政府にも影響を与える重要な法域と位置づけられています。
米国市場に進出し、AI技術を活用する日本企業にとって、こうした法制度の動向を正しく理解し、適切に対応することは、事業の継続性と法的安全性を確保するうえで不可欠です。
この記事では、カリフォルニア州を中心に、AI(人工知能)についての義務などの法規制の最新動向と、企業が取るべき対応策について解説します。
カリフォルニア州におけるAI規制の概要
AI(人工知能)技術は、採用、人事評価、マーケティング、顧客対応など、多くの企業活動に活用されつつありますが、その一方で、AIによるAIによるデータやコンテンツの生成や意思決定が差別やプライバシー侵害といった新たな法的問題を引き起こすリスクが顕在化しています。特に米国カリフォルニア州では、こうしたリスクに対応するたAI規制の整備が急速に進んでおり、同州に拠点を持つ、または同州と取引を行う日本企業にとって無視できない法務課題となっています。
具体的にはカリフォルニア州では、2025年1月1日より、18本の新たなAI関連法案が成立・施行されており、これらの法律は、ディープフェイク対策、AIの透明性確保、データプライバシー、医療分野におけるAIの利用制限などが含まれます。以下では、カリフォルニア州のAI関連規制のうち、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
雇用におけるAI活用と差別リスクへの対応
AIを活用した人材採用ツールやパフォーマンス評価ツールは、業務の効率化や公平性向上を目的として広く導入されています。しかし、こうしたツールがアルゴリズムの設計やデータの偏りにより、特定の人種、性別、年齢、障害の有無などに基づく差別を生じさせるリスクがあることが問題視されています。
カリフォルニア州司法長官が2024年3月に発出したリーガルアドバイザリー(法的助言)では、雇用関連の意思決定にAIを利用する場合、カリフォルニア民法(Unruh Civil Rights Act)、雇用機会均等法(Fair Employment and Housing Act)等の差別禁止法が適用されることを明確にしています。企業がAIツールを利用する際、そのツールの動作原理や出力結果が意図せず差別的効果をもたらす場合、ツール提供元ではなく使用企業自身が法的責任を問われる可能性があります。
したがって、日本企業が米国市場においてAIを活用した採用・人事施策を実施する場合、ツールの導入前に第三者によるバイアス評価を行うこと、または影響評価を実施することがリスク低減のうえで重要となります。
アルゴリズムの透明性と説明責任の強化
AIの意思決定はその複雑性ゆえに「ブラックボックス化」しやすく、どのような根拠で判断が下されたのかを明確に説明できないという問題があります。特に差別的な結果が生じた場合に、企業がその根拠やプロセスを説明できないと、法的リスクが一気に高まります。
こうした問題に対応するため、カリフォルニア州ではAIの使用に関する透明性と説明責任(accountability)を求める動きが強まっています。例えば、AIによって自動的に評価・選別された場合、その事実を求職者や従業員に通知する義務や、判断のプロセスに関する情報開示が求められる可能性があります。
企業は、使用するAIツールについて、誰がどのように設計したか、どのようなデータが使われているか、どのようなフィードバックループがあるかを社内で明文化し、必要に応じて説明できる体制を整える必要があります。また、意思決定の正当性を担保するために、定期的な監査やロジックの検証も推奨されます。
プライバシー保護と個人情報の管理義務
カリフォルニア州では、個人情報保護の観点からもAIの活用に対する規制が強化されています。特に、2023年に施行されたカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)と、その改正法であるカリフォルニア州プライバシー権利法(CPRA)は、AIを利用したデータ処理に新たな義務を課しています。
たとえば、企業がAIによって「プロファイリング(個人の性格、行動、嗜好などの分析)」を行う場合、消費者に対してその目的やロジックを説明し、場合によっては同意を得る必要があります。また、消費者には、AIによる自動処理を拒否する権利(オプトアウト)も認められています。
さらに、AIの判断に用いられるデータがどのように収集・保存され、第三者に共有されているのかについても、正確な開示が求められます。こうした要件を満たさない場合、企業は州司法当局による是正命令や制裁金の対象となる可能性があります。
日本企業が米国、特にカリフォルニア州でデジタルサービスを展開する際は、AIツールが扱う情報が「個人情報」に該当するかどうかを事前に特定し、それに応じたデータ管理体制を整備することが重要です。
以上のように、カリフォルニア州ではAI活用に関して、差別防止、説明責任、プライバシー保護の3点を軸とした法的枠組みが整備されつつあります。これらは州法である一方、全米の規制動向にも影響を与えるとみられ、米国進出を目指す日本企業にとっては、AI利用に関する方針や体制を早期に見直す契機となるでしょう。
日本企業が直面しうる法務リスクとは
AI技術の発展に伴い、米国進出を図る日本企業も、採用活動や業務プロセスにAIを積極的に導入しつつあります。しかし、米国におけるAI規制、とくに雇用分野においては、法制度だけでなく、社会通念や訴訟文化にも起因するリスクを正しく理解することが重要です。とりわけカリフォルニア州のように先進的なAI規制を打ち出している地域では、法令順守だけでなく、透明性や公平性といった倫理的側面も含めた対応が求められます。
ここでは、AI導入時に日本企業が直面しやすい3つの法務リスクを整理します。
米国雇用慣行とAI採用システム導入時の注意点
日本企業が米国で人材を採用する際には、現地の雇用慣行を踏まえた慎重な対応が必要です。米国では、応募者との接触段階から細かい規制が適用されるほか、求職者の権利保護に対する社会的意識が非常に高く、AIによる事前選考プロセスにも厳しい目が向けられています。
たとえば、日本では比較的広く行われている履歴書の自動スクリーニングや学歴・年齢などによるフィルタリングが、米国では「職務関連性が乏しい判断」として差別にあたる可能性があります。特に、AIを導入したことで本来の業務能力と無関係な属性(例:特定の大学名や過去の職歴など)による排除が生じている場合、企業側の説明責任が問われる可能性があります。
また、米国ではバン・ザ・ボックス法(前科情報の使用制限)」や「給与履歴の開示制限法」などが存在しており、AIがこれらの情報を含めて処理してしまうことで、無意識のうちに法令違反となるリスクもあります。AI導入にあたっては、採用プロセスの各段階で収集・使用してよい情報の範囲を明確にし、現地法に準拠したプロファイル設計が必要です。
差別・偏見と見なされる可能性のある判断基準
AIが行う意思決定の中でも、評価基準が間接的に差別を生じさせることは、日本企業にとって見落としやすいリスクです。米国では、「間接差別(disparate impact)」という法理が確立されており、表面上は中立に見える基準であっても、結果的に特定の人種、性別、障害者、LGBTQ+といった保護対象グループに不利な結果をもたらす場合、それ自体が違法とされる可能性があります。
近年では、こうしたAIによる差別リスクが実際の訴訟や規制強化のニュースとして報道される機会も増えており、企業の社会的責任が問われる場面が拡大しています。
たとえば、AIが過去の合格者データを学習して「過去に採用された傾向に近い応募者」を高評価するアルゴリズムを構築した場合、歴史的な偏りがそのまま再現され、無自覚な差別が継続される危険性があります。このような「学習データの偏り」による差別は、AI開発者だけでなく、利用企業にも責任が問われる傾向が強まっており、たとえ企業が差別の意図を持っていなかったとしても、影響に対する説明と是正措置が求められます。
さらに、米国では差別の疑いがあれば、従業員や応募者による訴訟が提起されるリスクが高く、企業イメージの毀損や和解金・罰金といったコストにもつながりかねません。AIの評価基準がどのような指標に基づいて構築されているのかを継続的に見直し、リスク評価を行う体制が不可欠です。
サードパーティ製AIツール利用時の契約・責任範囲
多くの日本企業は、AI機能を自社開発するのではなく、外部のソリューションプロバイダーが提供するAIツールを利用しています。こうしたサードパーティ製AIの導入は、開発コストや導入スピードの観点では有利ですが、法務面では契約内容と責任範囲の明確化が不可欠です。
AIツールに誤りがあったり、差別的な判断を下した結果として損害が生じた場合、責任の所在がどこにあるかが問題となります。特に米国では、利用者側(=企業)が実務上のコントロールを行っていたと判断されれば、契約上の免責条項があっても裁判で責任を問われる可能性があります。
そのため、ベンダーとの契約においては、以下のようなポイントを慎重に検討する必要があります:
- AIの判断ロジックの開示義務や品質保証に関する条項
- バイアス評価や監査対応に関する責任分担
- 誤判定が生じた場合の損害賠償責任の範囲
- 使用許諾範囲や米国外での使用制限に関する条件
また、AIツールの更新や改善が継続的に行われる場合には、初回導入時のレビューだけでは不十分であり、利用継続中のモニタリング体制も必要になります。
以上のように、AI技術の導入は企業の効率化に寄与する一方で、現地の法令や社会的要請に適合していない場合には、重大な法務リスクを招く可能性があります。
企業が取るべき具体的な対応策
AI技術を活用する企業にとって、法令を遵守しながら持続的に事業を展開するためには、単に規制に反応するのではなく、自主的かつ予防的なガバナンス体制を構築することが重要です。ここでは、日本企業が海外展開の一環としてAIを導入・運用する際に検討すべき対応策を、具体的なステップとともに解説します。
AIの使用範囲と目的を社内で明確化する
AIの利用は社内のさまざまな業務領域に広がりつつありますが、どの業務で、どのような目的のもとに、どの種類のAIを導入しているのかが不明確なままでは、法的責任の所在が曖昧となり、リスク管理が機能しません。
具体的な対応ステップは以下のとおりです。
AI使用実態の棚卸し
まずは自社が現在使用しているAIシステム・サービスをすべて洗い出し、「どの部門が」「何の目的で」「どのプロセスに」使用しているかを一覧化します。
使用目的の文書化
次に、それぞれのAI使用事例について、業務目的、期待される効果、対象となるデータの種類などを明文化します。雇用、マーケティング、セキュリティなど目的によって適用される法規制が異なるため、目的の明確化は極めて重要です。
利用方針の社内共有
AIの使用にあたって遵守すべき基本方針(例:人権尊重、公平性、差別禁止など)を定め、社内規程に反映させます。
AIの利用が漫然と広がることを防ぎ、必要に応じて影響評価や事前レビューを行う体制を整備することで、外部からの指摘に対して一貫性のある対応が可能になります。
プライバシーポリシー、同意取得プロセスの整備
米国では、AIが個人データを処理する場合、プライバシー保護の観点から情報提供義務や同意取得義務が生じるケースが増えています。たとえば、プロファイリングやターゲティング広告などにAIが使用される場合、その利用目的と範囲を明示し、ユーザーに選択権(opt-in/opt-out)を与える必要があります。
企業が講じるべき具体的な対応は以下のとおりです。
プライバシーポリシーの見直し・改訂
AIによるデータ処理を含む形で、プライバシーポリシーを更新し、収集するデータの種類、処理目的、第三者提供の有無などを明記します。AIによる自動化された意思決定がある場合は、その存在と概要も加える必要があるでしょう。
明確な同意取得の設計
「事前同意」が必要なプロセス(例:プロファイリング、行動履歴の追跡など)については、フォーム設計を法的要件に準拠させる必要があります。UI/UXも含め、利用者が同意の意味を十分理解できるように設計することが大切です。
データ処理に関する社内研修の実施
AIに関与する部門に対して、プライバシー保護の法的基礎と業務上の留意点について教育を行い、無自覚な違反を防ぎます。
このような対応により、AI活用に対する社会的信頼の確保と、カリフォルニア州をはじめとする厳格な州法への実務対応を両立させることが可能になります。
監査体制と記録保持:説明責任への備え
AIを運用する企業には、「何を基準に、どのような判断がなされ、結果として何が生じたのか」を説明する責任があります。この説明責任を果たすためには、単なる結果の記録だけでなく、その過程の記録と検証可能性が求められます。
企業が構築すべき監査・記録体制は以下のようになります。
AI利用ログの定期的な記録と保存
どのAIが、いつ、どのようなデータを用いて、どのような出力を出したのかというログを保存します。自動削除が設定されているツールもあるため、必要に応じて保存方針の再設定をしておきましょう。
AIのパフォーマンスレビューと誤作動検証
出力結果の正確性、公平性、逸脱の有無について、定期的にレビューを実施し、結果を文書化します。差別的傾向がないかを検証するためのテストケースの運用も有効です。
外部監査・第三者検証の導入
特に人事や金融、医療など判断結果に重大な影響が及ぶ分野では、外部の専門家によるレビューや監査制度を導入することも推奨されます。
記録保持と監査の仕組みが整っていれば、万が一トラブルが発生した場合でも、企業としての対応姿勢を示すことができ、法的責任の軽減や、訴訟リスクの低減につながります。
このように、日本企業が米国市場に進出する際には、AI技術の導入と並行して、法令対応・社内ガバナンスの整備を同時に進めることが不可欠です。技術活用と法務対応を両立させる体制こそが、グローバル展開における持続的成長の鍵となります。
米国進出時に法務専門家へ相談すべき理由
AI技術の利活用が進む中で、米国では各州が独自に規制を強化し始めており、日本企業が米国市場に進出する際には、技術面だけでなく法的な対応力も重要な競争要因となっています。
各州で異なるAI規制への対応
米国では、連邦レベルで統一的なAI法が整備されていない一方で、州ごとに個別のAI規制や関連法が導入されつつあります。たとえば、カリフォルニア州では2025年1月1日より、18本の新たなAI関連法が施行されるなど、動きが活発です。一方でニューヨーク市では、2023年7月より雇用におけるAIツールのバイアス監査を義務づける条例が制定されています。
このように、同じAIツールであっても、使用する州や都市によって求められる法的要件が大きく異なるため、企業には地域ごとの制度への高度な理解と実務対応力が求められます。法務専門家に相談することで、進出予定地の法令に応じたリスクアセスメントを行い、適切なガバナンス体制を事前に構築することが可能となります。
違反時の罰則・訴訟リスクの回避
米国では、AIによる差別やプライバシー侵害が発覚した場合、企業が重大な法的責任を負うことがあります。とくにカリフォルニア州では、司法長官が積極的にAI関連の違反事例に対する警告・執行措置を行っており、罰金の科される可能性もあります。さらに、個人による集団訴訟(クラスアクション)が提起されるケースもあり、対応を誤るとブランド価値や財務に大きな打撃を与えかねません。
AIに関連するリスクは、技術的な瑕疵のみならず、運用方法や契約内容にまで及ぶため、専門家の助言なしに対応するのは非常に困難です。法務専門家は、予防的な観点からリスク分析や契約の見直しを支援するほか、万一トラブルが発生した際にも、迅速かつ適切な対応方針を助言してくれます。
ビジネスモデルに適した法的助言の活用
AIの利用目的や運用体制は企業ごとに異なり、一律の法対応ではかえってリスクを高める場合があります。たとえば、AIを外部向けに提供するプロバイダーと、社内運用のためにAIを導入する利用企業とでは、準拠すべき法規制や開示義務の範囲が大きく異なります。
弁護士に相談することで、自社のビジネスモデルに適した規制対応の方針や、法的リスクを回避しつつ競争優位を確保するための助言を受けることが可能です。とりわけ米国では、「法を守る」だけでなく、「社会的責任を果たしていることを外部に示す」姿勢が重視されるため、専門家の視点は非常に有効です。
このように、米国市場においてAIを活用する日本企業にとって、弁護士は単なるリスク回避の存在ではなく、事業の持続可能性と信頼性を支える重要なパートナーとなります。進出前の段階から継続的なリーガルチェックを受ける体制を構築することで、より安心してグローバル市場に挑むことができるでしょう。
米国でのAI活用の法務を弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に相談したい方はこちら
AIの法務を専門家に依頼するメリット
AIの活用がビジネスのあらゆる領域に広がる中、米国ではそのリスクを抑制するための法制度が急速に整備されつつあります。日本企業がこうした環境下で米国進出を図る際には、技術導入と並行して、現地法に即したコンプライアンス体制の整備が不可欠です。AIの利用目的や範囲の明確化、プライバシー対応、契約書の見直し、監査・記録体制の構築など、多方面からの対応が求められる中で、法務専門家の支援を受けることで、より実践的かつ確実なリスク管理が可能になります。
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所に問い合わせる方法
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の内容は、2025年5月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|