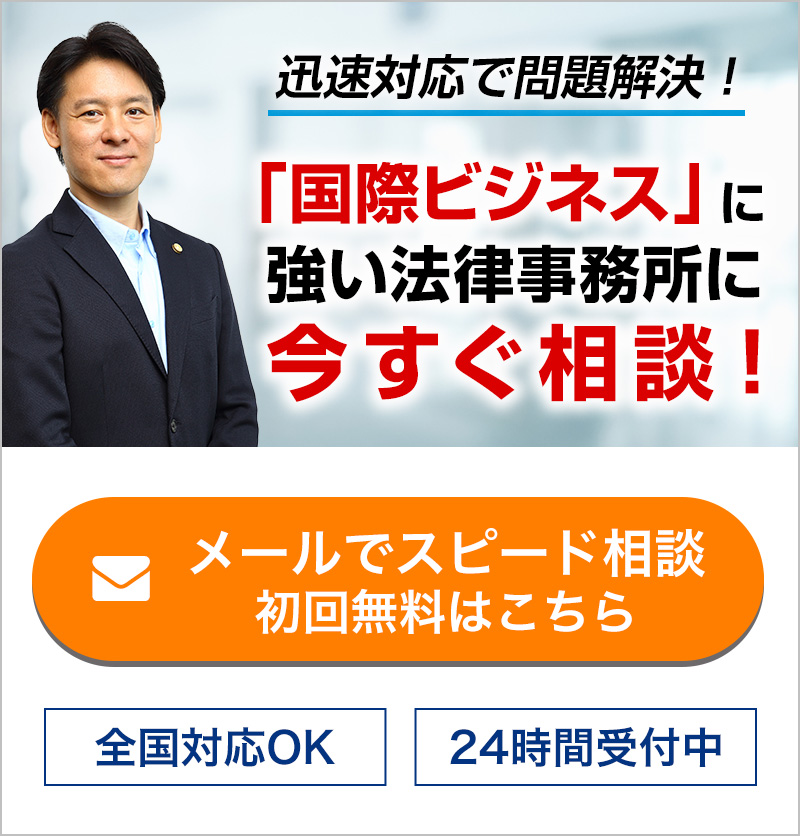目次
【ニュース解説】2025年秋 米国ビザ制度変更、日本企業向け重要情報
米国でのビザ制度は、政権ごとの政策方針によって大きく変化する分野のひとつです。とりわけトランプ政権下では、移民や留学生に対する規制強化が再び進められており、日本企業にとっても無視できない影響を及ぼしています。2025年秋に発表された新ルールでは、非移民ビザ申請について「居住国での申請・面接を原則とする」方針が示され、従来認められていた第三国での柔軟な申請が制限されることになりました。これにより、駐在員派遣や短期出張のスケジュールが大きく左右される可能性があります。
さらに、留学生ビザに関しては、長年続いてきた「在学中滞在許可(Duration of Status)」制度の廃止が提案され、最長4年間の固定滞在と定期的な審査が導入される見通しです。これらの変更は、米国で学ぶ日本人留学生や研究者だけでなく、現地での採用を見込む企業にとっても人材確保戦略を揺るがすものとなります。
グローバル展開を進める企業にとって、人材の確保と適切な派遣は事業成功の要であり、ビザ制度の変化は直接的な経営課題につながります。特に、手続きにかかる時間やコスト、そして滞在資格の不確実性は、計画性と柔軟性を求められる要素です。日本企業が米国市場で安定的に活動を続けるためには、最新の法制度を正確に理解し、戦略的に対応することが欠かせません。
この記事では、非移民ビザ申請に関する新たな方針、留学生ビザにおける滞在制度の変更、そして日本企業が直面しうる実務的リスクとその対策について、最新の動向をもとに解説していきます。
非移民ビザ申請に関する新ルール
居住国でのビザ審査義務化の背景
米国務省は、2025年9月6日付で、「非移民ビザ申請者は国籍または居住国のアメリカ大使館・領事館で面接(ビザインタビュー)を行うこと」を原則とする新たな指導方針を発表しました。
この変更の背景には、不正申請の抑制、ビザプロセスの透明性確保、および米国の安全保障強化の目的があります。具体的には、申請者がどの国に居住しているかを明確にし、それに基づいて責任ある審査を行うことで、無責任な中継申請や第三国での申請によるリスクを軽減する狙いがあります。加えて、その国での居住実態を確認することで、申請内容の信頼性を高め、滞在目的・期間等に関する不整合をあらかじめ排除することも目指しています。企業が海外に拠点を持つ場合や社員を派遣する際には、この「居住国での審査」がどのように扱われるかを事前に把握することが重要です。
これまでの運用との違い
従来、非移民ビザ(Nonimmigrant Visa)を申請する際、多くの場合、申請者は国籍国または便宜上の近隣国・第三国外の米国領事館で申請・面接を行ってきました。例えば、本国での待機時間が長い場合や処理能力の問題がある場合、他国の大使館・領事館を利用することが慣例的に認められることがありました。新ルールでは、原則として「国籍または居住国」での申請を義務づけ、これを外れる申請は居住を証明できることが前提とされるなど制限が設けられます。 また、申請者が居住国以外で申請する場合、手数料が返却されない、不利な審査となる可能性、面接待ち時間が著しく長くなる可能性があることが明記されています。 さらに、外交・公用関係のビザ類、特定の緊急・人道上の理由等、例外が限定的に設定されています。
企業の駐在員派遣や短期出張への影響
日本企業がアメリカへ社員を派遣する際、たとえば駐在員やプロジェクトベースでの短期出張者などは、これまで複数の申請国を検討できた柔軟性が低下する可能性があります。居住国での申請義務により、派遣先国・滞在国以外に本帰国や居住地を明確化する必要が出てきます。たとえば、社員が第三国から出張・派遣されていたケースでは、その「居住」の証明が求められ、書類準備や手続きの追加が必要となるでしょう。また、申請待ち時間が居住国の領事館の稼働状況に依存し、予定していた派遣・出張時期が遅れるリスクもあります。さらに、社員が「国籍国以外の国から申請する」場合に手続き・費用・審査上の不確実性が増すため、企業は派遣計画・人員配置をより慎重に設計することが求められます。
留学生ビザに関する新ルール案
「Duration of Status(在学中滞在許可)」制度の廃止提案
アメリカ国土安全保障省(DHS)は、Fビザ・Jビザなど留学生/交流訪問者(exchange visitor)を対象として、1978年から続く “Duration of Status”(D/S)制度の廃止を提案しています。 D/S 制度の下では、留学生は正規の学位プログラムに在籍し、授業を継続している限り、プログラム修了まで滞在が許可され、在学期間中追加の手続きをあまり必要としない柔軟性が特徴でした。 新ルール案では、この制度を廃し、留学生および交流者には「プログラムの予定期間または最大4年のいずれか短い方」の固定された滞在期間が設定され、その期間を超えて滞在を希望する場合は、正式な延長申請を USCIS(移民局)へ行う必要があります。
この変更の目的には、制度の乱用を防ぎ、学生の状況を定期的に審査可能とすること、及び国家安全保障・移民管理の監視体制を強化することが含まれています。。
最長4年間の滞在制限と定期的な審査の導入
この提案によれば、留学生・交流ビザ保持者の滞在期間は「その教育プログラムが完了するまで」または「4年を上限とする滞在期間」のいずれか短い方に固定されます。
4年を超えて滞在するには、米国市民権・移民局(USCIS)へ延長申請が必要となり、その申請が許可されるかどうかは、その時点での学業状況・プログラム進行度・その他の要件の遵守が審査されます。 また、現在の D/S 下で与えられている「60日間のグレース・ピリオド」(卒業後等の準備期間)などの扱いも見直され、Dビザ(留学生)の場合、グレース・ピリオドが30日になるなどの変更が含まれる可能性があります。
さらに、専攻変更、転校、学位レベルの変更(例えば学部から大学院など)などに関する柔軟性も制限される見込みとされており、これらの変更が許可されるかどうか、またどのような条件で行えるかも新たな規制により定められる予定です。
米国で学ぶ日本人留学生・研究者への影響
日本の学生・研究者にとって、この提案が実施されれば、滞在期間の不確実性が増すことになります。たとえば、大学院での博士課程や研究者ポストでの定期的な教育・研究活動が4年を超える場合、4年の上限に一旦到達すると延長申請が必要となり、その可否によっては予定していた研究期間に支障が出る可能性があります。また、学部から大学院への進学や、専攻変更などを通じて研究テーマの変更を行いたい場合、これまでより制約が強化されることが予想されます。
さらに、グレース・ピリオドの短縮等により、卒業後または学位取得後の準備(次の就職、研究ポスト探しなど)の時間も限られることになります。これにより、留学生や交流研究者が米国で長期の研究–教育を希望する際、プログラム設計を早期に見直す必要性が増すでしょう。日本の企業・大学が共同研究や現地ポストを用意する場合、研究期間・資金計画・帰国タイミング等を慎重に設計することが重要になります。
企業の人材育成・現地採用戦略に及ぶ影響
この留学生ビザ制度の変更案は、日本企業が米国での人材育成や現地採用を行う際にも大きな影響を及ぼします。まず、企業が米国での研究・研修プログラムを設ける際、従来のように留学生を “在学中滞在” させながら長期的なプログラムや段階的なキャリアパスを提供するモデルが困難になる可能性があります。4年という上限に達する前に進捗の評価や延長申請が必要となるため、プランニングの前倒しとリスク管理が不可欠です。さらに、将来的にその留学生を企業社員として現地で雇用したい場合、その移行期間・ステータス変更等の見通しが曖昧になりやすく、候補者が他国や他校への進学を検討するケースも出てくるでしょう。企業にとっては、優秀な海外人材を確保するために、滞在可能期間の制限を見越した契約・研修設計、予算の確保、サポート体制(ビザ申請・延長・移動の手続き)の強化が求められます。また、留学コストや不確実性を嫌う人材が米国以外の国を志望する可能性もあり、留学生採用競争におけるアメリカの魅力が相対的に低下するおそれがあります。
日本企業が直面するリスクと課題
今回のビザルール変更は、日本企業が米国で事業を展開する際に無視できない影響をもたらします。特に 人材派遣・現地採用の不確実性、ビザ取得・更新にかかるコスト増加、そして 留学生を通じた人材確保の難化 という3つの課題は、企業活動に直接的な負担を与えるものです。
まず、人材派遣・現地採用の不確実性についてです。非移民ビザ申請を「居住国」で行うことが義務化された結果、これまで可能であった第三国での柔軟な申請が難しくなります。例えば、駐在員候補者が他国で勤務している場合、その国での「居住証明」がなければ申請が認められず、派遣スケジュールが遅れるリスクが高まります。また、留学生ビザの固定期間化によって、研究活動や学業計画が長期にわたる人材は途中で延長審査を受けざるを得ず、滞在継続が不透明になる可能性があります。こうした不確実性は、企業の人材配置計画や現地プロジェクトの進行に大きな影響を与えるでしょう。
次に、ビザ取得・更新にかかるコスト増加が挙げられます。新ルールでは、申請者が国籍国や居住国でのみ申請できることが原則化されるため、渡航費や追加の事務手続きが発生するケースが増えると考えられます。さらに、留学生ビザで最長4年の制限が設けられることで、在学中の延長申請や審査対応が必要となり、企業がスポンサーとなる場合はそのサポートコストが累積します。弁護士費用や移民関連の手続き費用も増大し、派遣・研修計画の採算性に影響を及ぼすことは避けられません。特に大規模に駐在員を派遣する企業や、現地採用と本社派遣を組み合わせるビジネスモデルを持つ企業にとっては、コストの不確定要素が経営判断を複雑化させる要因となります。
最後に、留学生を通じた人材確保の難化も重要な課題です。従来、日本企業は米国で学ぶ日本人留学生や現地の外国人留学生をインターンシップや新卒採用を通じて人材プールとして活用してきました。しかし、D/S制度の廃止により、留学生が安心して長期的に学業・就職活動を行うことが難しくなります。滞在延長が認められるかどうかが審査に左右されるため、優秀な人材が米国留学を敬遠したり、卒業後に米国での就職を断念するケースが増加するおそれがあります。結果として、現地での優秀なバイリンガル人材や高度専門人材の確保が難しくなり、企業の競争力に直結する人材戦略に影響を与えかねません。
総じて、日本企業はこれまで当然視していた人材派遣・採用のプロセスに大きな不確実性を抱えることになります。派遣計画の遅延、コストの増大、そして人材確保の選択肢減少は、米国市場における事業展開を進める上で避けて通れない課題となるでしょう。そのため、各企業は最新のビザ制度の動向を継続的に把握し、適切なリスクマネジメント体制を整えることが不可欠です。
実務上の対応策
新しいビザルールのもとで米国に人材を派遣・採用するには、これまで以上に戦略的かつ柔軟な対応が求められます。制度変更によって不確実性やコスト負担が増すことは避けられませんが、企業としては計画的に準備を進めることでリスクを軽減することが可能です。ここでは、具体的な実務上の対応策を3つの観点から整理します。
派遣・採用計画の早期化と柔軟なスケジュール管理
まず重要なのは、派遣や採用に関する計画を早期に立案することです。申請先が「居住国」に限定される以上、対象となる社員がどの国に居住しているのか、その国の大使館・領事館の審査状況や面接待ち時間を事前に把握し、余裕を持ったスケジュールを組むことが欠かせません。例えば、これまでは出張の直前にビザ申請を行い、比較的短期間で渡航できたケースもありましたが、今後は申請から発給までに数か月を見込む必要があります。そのため、プロジェクト開始時期を見直したり、代替要員を用意しておくなど、複数のシナリオを想定したスケジュール管理が求められます。さらに、留学生を採用候補として見込む場合にも、卒業後の就労可能期間が短縮される可能性を踏まえ、採用時期を前倒しして内定や雇用契約を早めに提示することが有効です。
ビザ取得プロセスの専門家(弁護士等)活用
次に、ビザ手続きの専門家を積極的に活用することが重要です。新ルールは運用段階でさらに細かいガイドラインや例外規定が示される可能性が高く、各ケースによって必要な書類や審査基準が変わることがあります。企業の担当者が独力で対応するには限界があり、特に延長申請や例外的な申請ルートを利用する場合には、経験豊富な弁護士の助言が大きな差を生みます。例えば、従業員が複数国で勤務経験を持つ場合、どの国を「居住国」として申請するのが適切か、あるいは短期的な派遣であれば別のビザカテゴリーを選ぶべきかなど、判断に専門的知識が欠かせません。また、米国の大学や研究機関と連携して留学生を採用する際にも、ビザ延長の要件や就労資格の変更手続きについて、法的な見解を事前に得ておくことでスムーズな採用につながります。企業内での人事・法務部門と外部の専門家との連携体制を強化し、最新情報を常に共有する仕組みを整えることが実務上の安定性を高める鍵となります。
他国での拠点展開やリモート人材活用の検討
さらに、中長期的な対応策としては、米国以外の拠点展開やリモート人材の活用を検討することも有効です。ビザ制度の厳格化は、米国での活動に依存するリスクを浮き彫りにしました。したがって、例えばカナダやメキシコ、欧州・アジアの主要都市にサテライト拠点を設け、プロジェクトの一部をそちらで実施することで、ビザ発給の遅延や不許可による業務停滞を回避することができます。実際に多国籍企業の中には、米国内の規制強化を見越して他国拠点を強化し、人材を分散配置する動きも見られます。加えて、近年のテクノロジーの進展により、リモート勤務やオンラインでの国際協働が現実的な選択肢となっています。特に研究開発やバックオフィス業務では、現地に必ずしも常駐しなくても成果を上げられる体制を構築することが可能です。こうした仕組みを導入することで、米国ビザの制約を受けにくい柔軟な人材戦略を実現できます。
新ルールは日本企業にとって負担を増すものですが、適切な準備と戦略によって影響を最小限に抑えることができます。派遣・採用計画の早期化、専門家の活用、そして他国展開やリモート人材の活用を組み合わせることで、米国でのビジネス機会を確保しつつ、変化する制度環境に対応することが可能となります。今後も制度改正は継続的に行われると見込まれるため、企業としては短期的な対応にとどまらず、長期的な人材戦略を見直す契機と捉えることが重要です。
海外進出・海外展開への影響
米国におけるビザ制度の見直しは、日本企業にとって法的・実務的に大きなチャレンジとなっています。非移民ビザ申請を居住国で行うことの義務化や、留学生ビザに対する在学中滞在許可制度の廃止提案など、従来の柔軟な運用が制限されつつあります。これにより、駐在員派遣や短期出張の計画、さらには現地で学ぶ留学生を通じた人材確保にまで不確実性が広がっており、今後も追加的な規制が導入される可能性があります。
企業が米国市場に進出し、現地で安定的に事業を行うためには、最新のビザルールを正確に把握し、派遣計画や採用戦略に即した体制整備を行うことが不可欠です。とりわけ、ビザ取得や更新には相応のコストと時間がかかるため、単なる制度理解にとどまらず、戦略的かつ継続的な対応が求められます。これは単なるリスク回避ではなく、企業の信頼性やグローバル展開における競争力を高める上でも重要な取り組みとなります。
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、海外法務に精通した弁護士をはじめ専門家が多数在籍し、米国ビザ制度の最新動向に基づいた総合的なサポートを提供しています。駐在員派遣や現地採用に伴うビザ取得・更新の手続きから、人材戦略の見直し、将来のリスク管理まで、幅広いニーズに対応可能です。米国での事業展開や人材活用に不安を感じられる企業様は、どうぞ安心してご相談ください。
※本稿の内容は、2025年9月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00