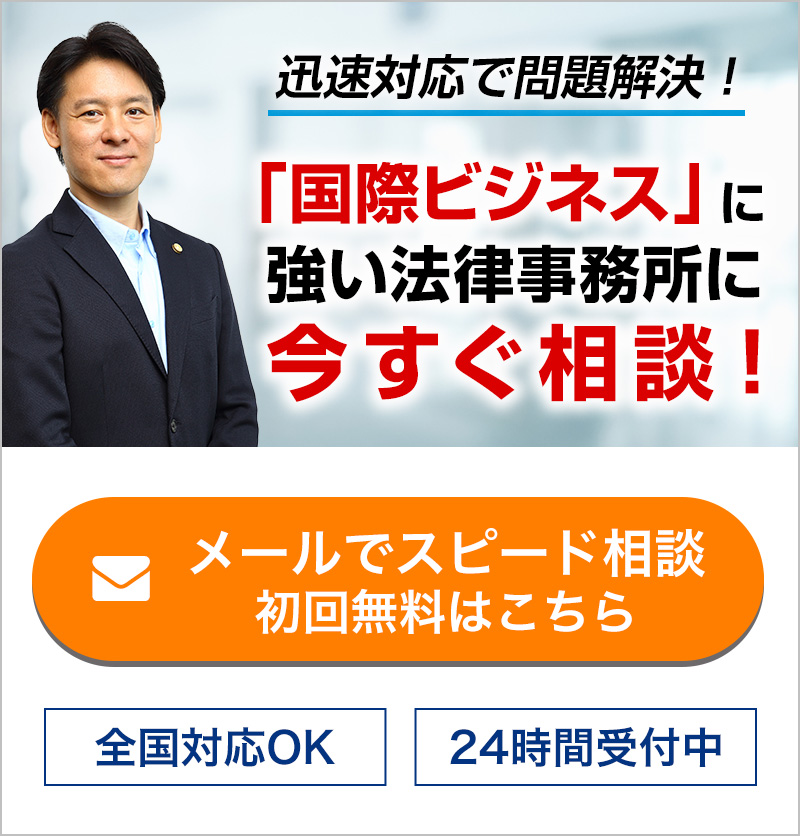外国での行政手続き・事業取引・留学等を行う際、相手国の行政機関・企業・大学等から契約書・委任状・翻訳文・在籍証明書といった私文書を、notarizeのうえ提出するよう求められることがあります。
私文書の認証(ノータリゼーション)について、皆さまは、下記のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「ノータリゼーション(Notarization)・私文書の認証とは何ですか?」
「外国から在籍証明書・卒業証明書・契約書の提出を求められたのですが、そのまま提出しても大丈夫でしょうか?」
「ノータリゼーションとアポスティーユ・公印確認の違いは何ですか?」
「アポスティーユを直接受けられない書類には宣言書を作成すればよいと聞いたのですが本当ですか?」
「私文書にアポスティーユを受けることはできますか?」
この記事では、契約書・委任状・翻訳文・卒業証明書といった私文書を外国の行政機関・企業等に提出する際におさえておきたい、私文書の認証(ノータリゼーション)や宣言書とは何か、どのような場合に宣言書が必要とされるのか、対象となる文書やその申請方法について、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
認証(Notarization)とは
認証(ノータリゼーション)とは、私文書(私署証書)を「この文書の署名又は押印は文書の作成者によって行われたものである。」と公証人が証明する制度と考えると分かりやすいです。文書の内容が真正なものであることを証明するのではなく、文書の署名又は押印の真正を証明することにより、文書が作成者の意思によって作成されたことが“推定”されます。
どのような場合に必要か
契約書・在籍証明書・委任状等の私文書に作成者の署名や記名押印があったとしても、その署名や記名押印が本当に作成者本人のものかどうかは分かりません。押印の真正を担保するために印鑑証明書を活用することも考えられますが、印鑑登録をしていないケースや、印鑑制度のない外国の行政機関や企業との取引を行う場合には、日本の印鑑証明書の制度は使用できません。
上記のような場合には、公証人による私文書(私署証書)の認証を受け、文書を本人が作成したことを証明することが必要となります。
認証の種類
公証人による私文書(私署証書)の認証には、以下の種類があります。
■面前認証(目撃認証):文書を作成した本人が、公証人の面前において当該文書に署名する方法
■面前自認(自認認証):文書を作成した本人が、公証人の面前において文書に署名したことを自ら認める方法
■代理自認:公証人の面前において、文書を作成した本人が、文書の署名が自らのものであることを自認したことを、弁護士等の代理人が陳述する方法
■謄本認証:署名の真正を認証するのではなく、嘱託人が提出した謄本がその原本と一致していることを認証する方法
■宣誓認証:当事者が公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓し、当該文書に署名又は押印を行う方法、証書の署名又は押印が自らのものであると自認したときは、その旨を記載して認証する方法
上記で解説した “文書を作成した本人” のことを “署名者” といいます。
外国向け私文書の認証(日本語で作成された外国で使用される私文書も含む。)の場合には特に、どの認証が必要かを適切に判断することで、スムーズな準備、手続きが可能になります。
アポスティーユとは?外務省の公印証明の流れ・方法・費用等を解説 | 国際ビジネス法務サービス
公証役場・公証人の役割
公証人とは公正・中立な立場から、国の公務である公証事務を行う法律の専門家であり、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者かつ公募に応じた者の中から、法務大臣が任命し就任します。当事者双方にとって公正・中立な立場という点が、一方当事者(依頼者)の代理人として依頼者の利益のために活動する弁護士との違いです。
公証人が提供する法的サービス(公証事務)は、公正証書の作成、私署証書への認証の付与、確定日付の付与の3種類に分けることができ、本記事のテーマである私文書・外国向け文書の認証(ノータリゼーション)は私署証書への認証の付与(公証人法第1条2項)に分類されます。公正証書では任意後見契約書や執行証書等の作成、確定日付の付与は公正証書や内容証明郵便等の書類を対象にしています。
公証人の人数は全国で約500人、公証人が執務する事務所(公証役場)は全国で約300箇所あります。公証事務を依頼する際には任意の公証役場に依頼することが可能です。何度か通う場合には近場を選択したり、後述するワンストップサービスを提供している公証役場を選択することもできます。
宣言書とは何か
翻訳した公文書・外務省の公印確認やアポスティーユを直接受けることができない公文書、署名のない私文書に公証人の認証を受ける際には、これらの文書がどういったものなのかについて、宣言書を作成し、その宣言内容に署名を行います。この宣言書は私文書となる点がポイントです。
このように、宣言書(私文書)を公文書の表紙にするとで、私文書として公証人の認証を受けることができます。また、署名のない私文書についても、そのままでは公証人の認証を受けることができません。こういった場合にも、宣言書に署名を付して文書の表紙にすれば、私署証書として公証人の認証を受けることが可能です。
宣言書の種類
宣言書の種類には下記のようなものがありますが、認証を受ける私文書の内容や、提出先、当事者の関係などによって記載内容を変更し、適切に作成することが重要です。
■私文書が原本であること、真正な複写(コピー)であることを宣言する一般文書認証用の宣言書
■日本国と相手国の両方の言語に精通し、かつ私文書の内容を正確に翻訳したことを宣言する翻訳文認証用の宣言書
■日本国政府が発行したパスポートの写しであることを宣言する、パスポートコピーの認証用の宣言書
■残高証明書用の宣言書
■卒業証明書用の宣言書
外国向け宣言書(Declaration)
宣言書にどのような内容を記載するかどうか、宣言書は日本語と相手国の言語、どちらで作成するかどうかについては、相手国や提出先の機関等によって異なります。提出先国の機関等に事前に確認することをお勧めします。
外国に提出する文書の認証について
公文書の認証は外務省によるアポスティーユ・公印確認、私文書の認証は公証人による認証(ノータリゼーション)と一括りにできない点にご注意ください。以下で詳しく解説していきます。
どのような場合に必要か
外国に提出する私文書の認証を受ける必要があるケースには、下記のようなものがあります。
■私文書(私署証書)や発行後3カ月を経過した公文書(卒業証明書など、複数回発行されない性質の文書を除く。)にアポスティーユ・公印確認を受けたい場合
■専門学校や外国大学等の卒業証明書(私文書)、在学証明書や推薦状を外国の大学に提出する場合
■登記簿謄本や戸籍謄本(公文書)の翻訳書面を外国の行政機関や企業等に対して提出する場合
■在籍証明書、定年退職証明書、委任状、契約書等(私文書)を外国の行政機関や企業等に対して提出する場合
■パスポート等に直接アポスティーユを受けることを望まない場合で、複写(コピー)したものにアポスティーユを受けたい場合
私文書にアポスティーユ・公印確認を受けたい場合には、アポスティーユ・公印確認は公文書以外の文書に直接受けることが原則できないため、一度公証役場において、公証人による認証(ノータリゼーション)を受けることにより、その私文書は公文書となりますので、アポスティーユ・公印確認を受けることが可能になります。
外国での提出先が企業の場合には、公証人による認証(ノータリゼーション)で事足りるケースもありますが、基本的には外務省による認証(アポスティーユ・公印確認)を求められます。前述しましたが、私文書は直接外務省の認証を受けられないため、公証人の認証により当該私文書を公文書とすることにより、間接的に外務省の認証を受けることになります。
出典:「申請手続きガイド 1証明できる書類」(外務省)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000549.html)をもとに作成
どのような種類があるか
公証人の認証を受ける外国向け私文書には、以下のようなものがあります。
■公文書(登記簿謄本・戸籍謄本等)を翻訳したもの
■公文書を複写(コピー)したもの
■専門学校の卒業証明書・外国大学の卒業証明書
■委任状
■契約書
■退職証明書
■在職証明書
■離婚協議書
■遺言書
認証手続の流れ
外国向け私文書の認証手続きの流れは、以下の通りです。外国向け文書の認証については、実務上、公証人による認証(ノータリゼーション)のあとに外務省による認証(アポスティーユ・公印確認)を受けることが一般的ですが、外国向け文書の認証を受けた後の手続きについては 5.外国向け文書の認証を受けた後の手続 にて解説します。
① 相手国、提出先に必要に応じて確認を行う(宣言書が必要な場合にはその内容や言語、私文書の翻訳の必要の有無)
② 必要書類の作成・準備
③ 公証役場の予約
④ 公証人の認証を受ける(認証文の付与)
必要書類と申請の方法
外国向け私文書の認証に必要な書類については、下記のようなものがありますが、あくまで一例であり、相手国、提出先、提出する経緯や文書の性質によって追加が発生する可能性もありますので、詳しい内容は弁護士や公証役場といった専門家に確認することをお勧めします。
| 署名した本人が公証役場に行く場合
(面前認証、面前自認、宣誓認証) |
代理人が公証役場に行く場合(代理自認) | |
| 認証を受ける文書に署名したのが個人で肩書き等がない場合 | ■認証を受ける文書1通
■署名者本人の証明書 |
■認証を受ける文書1通
■署名者本人の印鑑証明書 ■署名者本人の実印が押印された委任状 |
| 認証を受ける文書に署名したのが法人の代表者で肩書きを付して署名する場合 | ■認証を受ける文書1通
■署名者本人の肩書を証明する資料 ■署名者本人の証明書 |
■認証を受ける文書1通
■署名者本人の肩書を証明する資料 ■法人代表者の印鑑証明書 ■署名者である法人代表者からの委任状(印鑑証明書と同一の押印がされたもの) |
| 認証を受ける文書の署名者が法人の代表者以外の者で、役職者等の肩書きを付して署名する場合 | ■認証を受ける文書1通
■署名者本人の肩書を証明する資料 ■法人代表者の印鑑証明書 ■法人代表者が作成した役職証明書又は委任状(印鑑証明書と同一の押印がされたもの) |
■認証を受ける文書1通
■署名者本人の肩書を証明する資料 ■署名者(役職者)からの代理人への委任状(署名者の実印又は法人の印鑑証明書と同一の押印がされたもの) ■代理人の身分確認書類 |
外国向け文書の認証を受けた後の手続
外国向け文書の認証については、実務上、公証人による認証(ノータリゼーション)のあとに外務省による認証(アポスティーユ・公印確認)を受けることが一般的です。外国向け文書の認証を受けた後の手続きについては ワンストップサービスを利用できる場合とそうでない場合に分けて解説します。
北海道公証役場(札幌法務局管区内)、宮城県公証役場、東京都公証役場、神奈川県公証役場別、静岡県公証役場、愛知県公証役場、大阪府公証役場、福岡県公証役場ではワンストップサービスの提供を受けて、スピーディーにアポスティーユや公印確認を受けることが可能です。
<通常の流れ>
①公証人による外国向け文書の認証を受ける
②公証人による認証が正しいことの証明(公証人押印証明)を地方法務局長から受ける
③地方法務局長からの証明(公印)が正しいことの証明を外務省から受ける
④外務省からの証明が日本国外務省からの証明であることを、相手国(提出先国)の駐日大使館(領事館)からの証明(領事認証)を受ける
⑤提出する
<アポスティーユを受ける場合>
ハーグ条約(1961年の外国国文書の認証を不要とする条約)加盟国間で文書の提出・受領が行われる場合には、外務省のアポスティーユを受けることにより、相手国の領事認証を得ずに、相手国に文書を提出できます。この場合、④が省略されます。
①公証人による外国向け文書の認証を受ける
②公証人による認証が正しいことの証明(公証人押印証明)を地方法務局長から受ける
③地方法務局長からの証明(公印)が正しいことの証明を外務省から受ける
④外務省からの証明が日本国外務省からの証明であることを、相手国(提出先国)の駐日大使館(領事館)からの証明(領事認証)を受ける
⑤提出する
<ワンストップサービスの提供を受ける場合>
北海道公証役場(札幌法務局管区内)、宮城県公証役場、東京都公証役場、神奈川県公証役場別、静岡県公証役場、愛知県公証役場、大阪府公証役場、福岡県公証役場ではワンストップサービスといって、申請者からの要請により、公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認又はアポスティーユを一度にまとめて取得することが可能です。この場合、②③④が省略されます。
①公証人による外国向け文書の認証を受ける
②公証人による認証が正しいことの証明(公証人押印証明)を地方法務局長から受ける
③地方法務局長からの証明(公印)が正しいことの証明を外務省から受ける
④外務省からの証明が日本国外務省からの証明であることを、相手国(提出先国)の駐日大使館(領事館)からの証明(領事認証)を受ける
⑤提出する
法務局や外務省に出向く必要がなくなり、スムーズな文書の提出ができるようになりますが、外務省からアポスティーユではなく公印確認を受けた場合には、駐日大使館(領事館)の領事認証を必ず取得する必要がある(④が省略できない。)という点にご留意ください。
出典:「申請手続きガイド 2申請の流れ」(外務省)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html)をもとに作成
外国向け文書の認証について、よくある質問
外国向け文書の認証について、よくある質問にお答えしていきます。気になる点や分からない点がある場合には、是非お問い合わせフォームからご連絡ください。適切なサポート内容を提示いたします。
Q1.私文書の内容が正しいことを証明してもらうことはできないのでしょうか?
A .公証人が行いことのできる認証は、“署名や記名押印が署名者本人のものであること”(署名認証) “コピーされた文書(謄本)が原本と同一のものであること”(謄本認証) “文書に記載された内容が真実であるかどうか当事者が宣誓したこと”(宣誓認証)です。内容の真実性を認証することはできません。
Q2.公文書の認証を公証人にしてもらうことはできるのでしょうか?
A .公文書の直接的な認証は外務省が行うため、公証人による認証を受けることはできません。しかし、添付書類(公文書・翻訳文)を付した宣言書(Declaration)(私文書)を公証人が認証することは可能です。
Q3.卒業証明書の認証を受ける際に、学校(文書作成者)からの委任状をもらえるのかどうか心配です。
A.実際には学校からの委任状を得ることは難しかったり、仮にできたとしても、かえって手続きに時間がかかってしまうケースも多いです。こういった場合にも宣言書が有用です。宣言書を作成し、その宣言書に卒業証明書を添付します。このような方法により、卒業証明書ではなく宣言書に公証人による認証を受けることができます。宣言書の作成者は学校ではありませんので、委任状の心配はいりません。
Q4.署名がされていない文書(会計書類や会社の定款)にも認証を受けることが可能ですか?
A.公証人による認証を受けることができるのは私文書であるため、署名や記名押印がない文書については、そのままでは認証を受けることができません。もっとも、この場合にも、会計書類や会社の定款を添付した宣言書を作成することで、宣言書に認証を受けることが可能です。
Q5.相手国の提出先から翻訳した戸籍謄本を提出するように言われたのですが、公証人の認証を受ける前に公証役場で翻訳を依頼できますか?
A.公所役場における公証事務は、公正証書の作成、認証の付与、確定日付の付与です。外国向け文書の認証は、あくまで認証を付与することが業務内容となりますので、翻訳の依頼は専門家にされることをお勧めします。
この記事では、契約書・委任状・翻訳文・卒業証明書といった私文書を外国の行政機関・企業等に提出する際におさえておきたい、私文書の認証(ノータリゼーション)や宣言書とは何か、どのような場合に宣言書が必要とされるのか、対象となる文書やその申請方法について解説しました。
日本の印鑑制度が通用しない外国に私文書を提出する際には、その文書に署名や記名押印があったとしても、それをもってその文書が正式なものであると判断してもらうことは難しい場合があります。そのため、相手国や提出先に慎重に確認を取りながら、提出文書を受け入れてもらえる形に仕上げる(各種認証を受ける)必要があります。
該当文書をどこの国から求められたのか、何の文書をどこの機関に提出するのかによって、準備するものと必要な申請方法が異なります。また、提出までのスケジュールによっても、各種手続きの進め方を工夫することが可能です。
外国向け文書の認証を迅速・確実に取得することを希望される方は、弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所まで、いつでもご相談ください。
日本企業の海外進出をサポートしてきた弊所では、外国向け文書の認証に関する手続について、法人・個人に関わらず、これまで多くのクライアント様からの委任を受け、ご支援してまいりました。適切な書式やサンプル等に基づき、必要とされる書類を取得する業務を行っております。
外国向け文書の認証を必要とする際には、いつでもご相談ください(費用については、必要とされる手続の内容等を確認のうえお見積りさせていただきますので、お問合せフォームからご連絡ください)。
※弊所では英語対応や翻訳も可能です。
If you would like to obtain an Notarization quickly and reliably, please feel free to contact the First & Tandem Sprint Law Offices!
Click here for inquiries about our firm’s full range of legal support and services.
Our lawyer and paralegal teams, who have extensive experience in international work, will support you.
※本稿の内容は、2025年4月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|