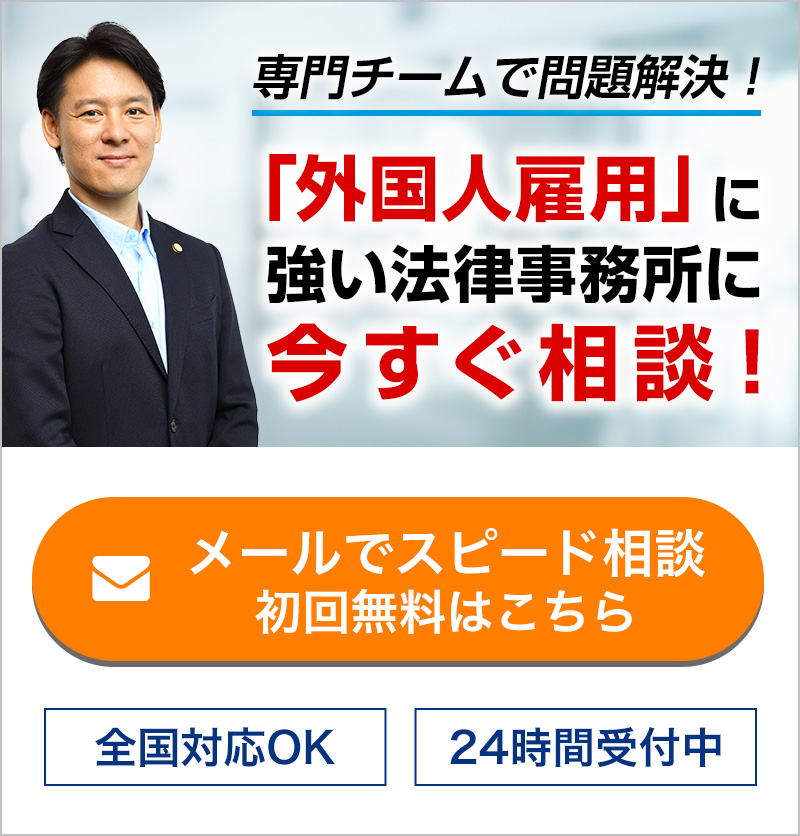目次
少子高齢化や労働力人口の減少に伴い、外国人労働者への関心が年々高まっています。
外国人雇用するにあたり、就労ビザについて企業の人事部・採用担当者の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「外国人雇用って大変そう…」
「就労ビザを申請したいけど適切なビザが分からない…」
「就労ビザの申請の流れとは?」
「就労ビザ申請の際に確認すべきこととは?」
「就労ビザ申請が不許可になったらどうすれば良いの?」
「外国人労働者を雇用する際の注意点は?」
この記事では就労ビザの種類や就労ビザの申請の流れ、就労ビザ申請の際に確認すべきことや不許可になったときの対応を分かりやすく解説します。
就労ビザとは
一般的に「就労ビザ」と言われているものは「在留資格」のことを指すことが多いです。「ビザ」と「在留資格」は全く異なるものです。
◆ビザ(査証)とは
日本に入国する前に海外の日本公館で発行されるものです。日本に入国するために必要なものです。入国が保証されるものではありませんが、入国手続きに必要になります。
◆在留資格とは
日本に入国した後に付与される資格です。日本に滞在し活動するため必要なものです。
在留カードにも記載されます。
分かりやすく例えると、「ビザ(査証)」は日本に来るための許可証、「在留資格」は日本で活動するための許可証です。
厳密には「就労ビザ」というものは存在しませんが、「日本で就労するために必要な在留資格」のことを指しています。この記事では「日本で就労するために必要な在留資格」の意味で「就労ビザ」と記載します。
就労ビザの種類とは
日本には様々な職業があります。就労ビザも職業の性質や職種にあわせ現在16種類あります。
就労ビザは一つしか受けることができません。原則として保有する就労ビザで認められている活動の範囲内でのみ就労が認められます。
なお、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者といった身分系のビザは日本人と同様に違法でない限りは制限なく就労することができます。ただし、日本人の配偶者と離婚するなど身分に変更があった場合は在留資格の変更も必要になりますので、家族情報に変更があった際などは必ず届出をしてもらうようにしましょう。
外交
外国大使館や外国領事館の構成員としての活動。外国大使館や外国領事館の構成員の配偶者や子も該当します。
公用
外国大使館や外国領事館、国際機関の公務活動。外国大使館や外国領事館の職員は「公用ビザ」を取得します。また、海外政府から公務で派遣される者の配偶者や子も該当します。
教授
大学や高等専門学校での研究、指導、教育活動。大学教授や研究者などが該当します。
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。作曲家や美術家などが該当します。
宗教
布教、宗教活動。海外の宗教団体から派遣された神官や牧師などが該当します。
報道
海外の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。報道記者やカメラマン、アナウンサーなどが該当します。
経営・管理
事業の経営、管理活動。企業の経営者や管理者が該当します。
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動。弁護士、公認会計士以外にも司法書士や行政書士などの士業も該当します。
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。看護師や薬剤師なども該当します。
研究
国内の公私機関との契約で行う研究活動。研究者が該当します。
教育
国内の小中高等学校、専門学校などで行う語学その他の教育活動。小中高等学校、専門学校などの教員や補助教員などが該当します。
技術・人文知識・国際業務
国内の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務に従事する活動。マーケティングやエンジニア、広報、通訳など幅広い業務が該当します。
企業内転勤
海外から日本国内の本店、支店に転勤して行う技術・人文知識・国際業務に該当する活動です。
介護
国内の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動。介護福祉士が該当します。
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係る活動やその他の芸能活動。サーカス団員やモデルなどが該当します。
技能
国内の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。外国料理のコックやパイロットなどが該当します。
その他特別な就労ビザ
職業の性質や職種にあわせて取得する就労ビザの他に働き方や就労能力によって取得できる特別な就労ビザもあります。
◆高度専門職
高度で専門的な知識を持っている外国人労働者が対象です。雇用企業や年収などいくつかの項目があり、ポイント制で判断されます。また、雇用企業によってもポイントが変わる可能性があるため、転職をした際は職種に変更がなかったとしても、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
◆技能実習
技能実習生が対象です。
◆特定技能
介護・建設などの特定産業分野で所定の業務に従事する外国人労働者が対象です。
◆特定活動の一部
ワーキングホリデーやインターンシップ生が対象です。
資格外活動許可
資格外活動許可とは、日本に在留している外国人が、本来の在留資格で認められていない活動(就労など)を行うために取得する許可です。
例えば、留学や家族滞在ビザを持っている人は、通常、日本で働くことは認められていません。しかし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内という制限はありつつもアルバイトなどの就労が可能になります。
就労ビザ申請の流れ
就労ビザ申請の流れは、海外にいる外国人を採用する場合と、日本にいる外国人を採用する場合で異なります。
海外にいる外国人の就労ビザ取得手順
1.日本の企業が外国人を採用し、雇用契約を締結する
まず外国人を採用し雇用契約を締結します。
就労ビザの審査の際には、日本で行う予定の活動(業務内容)が申請された就労ビザの活動内容に該当するかを確認しますので、先に雇用契約を締結し、業務内容を確定させておく必要があります。
「まだ就労ビザが取得できると分からない状態で雇用契約を締結するのは怖い」という声も聞きますが、雇用契約書内に「適切な在留資格の取得が許可されなかった場合、本契約は無効とする。」という一文を入れておくと、就労ビザが取得できなった際には入社させる必要はありません。
2.企業が代理で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
基本的には企業が代理で申請しますが、弁護士や行政書士に任せることもできます。
弁護士や行政書士に任せることで正確な書類が早くでき、申請までの期間も短くすることができます。
3.在留資格認定証明書が交付される
在留資格認定証明書交付申請をしてから約1~3ヶ月ほどで在留資格認定証明書が交付されます。申請する就労ビザや場所、時期にも影響されますが、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」で東京出入国在留管理局に申請した場合は2か月強かかることが多いです。
採用が決まったらすぐに申請の手続きを行えるよう準備しましょう。
4.在留資格認定証明書を外国人本人に送付する
在留資格認定証明書が交付されたら、すぐに外国人労働者本人に送付します。
5.外国人が在留資格認定証明書を持って日本公館でビザ申請を行う
外国人労働者本人が在留資格認定証明書を受け取ったら、すぐに日本公館へ行き、ビザ申請を行います。
6.ビザが発給される
申請内容に特に問題がなければ5営業日ほどでビザが発給されます。
7.日本に入国して就労開始
パスポートとビザ、在留資格認定証明書を持って日本に入国します。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。
在留資格認定証明書が交付されてから3ヶ月以内に日本に入国しなければなりません。
そのため、在留資格認定証明書が交付されたらすぐに外国人労働者本人に送付するように徹底しましょう。
日本にいる外国人の就労ビザ取得(変更)手順
1.日本の企業が外国人を採用し、雇用契約を締結する
まず外国人を採用し雇用契約を締結します。
採用については、自社サイトでの募集や人材紹介会社を利用するなどの方法があります。
就労ビザの審査の際には、日本で行う予定の活動(業務内容)が申請された就労ビザの活動内容に該当するかを確認しますので、先に雇用契約を締結し、業務内容を確定させておく必要があります。
「まだ就労ビザが取得できると分からない状態で雇用契約を締結するのは怖い」という声も聞きますが、雇用契約書内に「適切な在留資格の取得が許可されなかった場合、本契約は無効とする。」という一文を入れておくと、就労ビザが取得できなった際には入社させる必要はありません。
また、「本契約の開始日において、在留資格変更許可申請の結果が未だ出ていない場合、許可が下りるまでの間、就労させないものとする。」という一文を入れておくと、審査が長引いて審査結果が出ていない場合も就労させない根拠になります。
ただし、外国人労働者は契約始期がきたら無条件で働けると思っている可能性もあります。雇用契約を締結する際にはきちんと説明をしましょう。
2.「在留資格変更許可申請」を行う
外国人労働者本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
基本的には外国人労働者本人が行いますが、申請書の作成や出入国在留管理局への提出は弁護士や行政書士に任せることもできます。
3.在留資格変更許可申請が許可される
在留資格変更許可申請をしてから約1~3ヶ月ほどで在留資格変更許可申請が許可されます。申請する就労ビザや場所、時期にも影響されますが、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」で東京出入国在留管理局に申請した場合は1か月強かかることが多いです。
採用が決まったらすぐに申請の手続きを行えるよう準備しましょう。
4.就労開始
在留資格変更が許可されてから就労開始します。
資格外活動許可の取得の流れ
1.日本の企業が外国人を採用し、雇用契約を締結する
まず外国人を採用し雇用契約を締結します。
資格外活動許可の審査の際には、実際に就労予定であるかの確認をしますので、先に雇用契約を締結しておく必要があります。
「まだ資格外活動許可が下りるか分からない状態で雇用契約を締結するのは怖い」という声も聞きますが、雇用契約書内に「資格外活動許可申請が許可されなかった場合、本契約は無効とする。」という一文を入れておくと、資格外活動許可申請が不許可だった際には入社させる必要はありません。
また、「本契約の開始日において、資格外活動許可申請の結果が未だ出ていない場合、許可が下りるまでの間、就労させないものとする。」という一文を入れておくと、審査が長引いて審査結果が出ていない場合も就労させない根拠になります。
ただし、外国人労働者は契約始期がきたら無条件で働けると思っている可能性もあります。雇用契約を締結する際にはきちんと説明をしましょう。
2.「資格外活動許可申請」を行う
外国人労働者本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に「資格外活動許可申請」を行います。
基本的には外国人労働者本人が行いますが、申請書の作成や出入国在留管理局への提出は弁護士や行政書士に任せることもできます。
3.資格外活動許可申請が許可される
資格外活動許可申請をしてから早くて2週間ほどで資格外活動許可申請が許可されます。
4.就労開始
資格外活動が許可されてから就労開始します。
・外国人の就労ビザを取得する方法|ビザ申請に強い法律事務所が解説
就労ビザ申請の際に確認すべきこと
就労ビザを取得するためには一定の基準を満たす必要があります。
不許可のリスクを減らすためにも以下のポイントを確認しましょう。
在留資格の該当性があるか
日本で行う予定の活動(業務内容)が申請する就労ビザの活動内容に適しているかを確認します。
≪例≫
・ITエンジニアとして働く予定⇒「技術・人文知識・国際業務」ビザ
・介護士として働く予定⇒「介護」ビザ
上陸許可基準との適合性があるか
上陸許可基準とは、外国人が日本に入国し、特定のビザを取得するために満たすべき条件のことです。この基準をクリアしないとビザが取得できません。
≪例≫
・「技術・人文知識・国際業務」ビザ
⇒業務内容に関連する大卒or日本国内の専門学校卒or実務経験10年以上
相当性があるか(法違反をしていないかなど)
申請者が過去に日本の法律違反(オーバーステイ、不法就労、犯罪など)をしていないかが確認されます。
違反歴があると、不許可や在留期間の短縮の可能性があります。
なお、相当性を確認されるのは、既に日本で生活をしている外国人労働者です。
海外から呼び寄せる場合には過去に日本に滞在していたことがあったとしても考慮されません。
適切な労働条件であるか
外国人労働者の労働条件が、日本の労働基準法に適合しているか確認されます。
・ 給与が日本人と同等以上であること(合理的な理由がある場合を除く)
・適切な社会保険(健康保険・年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入
・労働契約が明確に記載されており労基法違反がないこと(勤務時間・休日・業務内容など)
主に上記の点が確認されます。
雇用企業が法違反をしていないか
企業が過去に外国人の不法就労を助長したり、労働基準法違反をしていないかが確認されます。
法令違反がある企業は、外国人のビザ申請が不許可になる可能性があります。
特に過去に不法就労助長罪に問われていると不許可のリスクは高まります。
雇用企業に安定性があるか
会社の経営が安定していなければ、雇用継続が難しくなるため、就労ビザの審査においても安定性は確認されます。
主に直近の決算書で確認されますが、赤字だからといって必ずしも不利になるとは限りません。
適切な資金調達ができているか、設立してからの年月なども含め総合的に判断されます。
雇用企業に継続性があるか
企業が長期的に存続できるかも審査対象になります。
こちらも決算書の数字のみで判断されるわけではありません。
事業内容なども含め総合的に判断されます。
就労ビザの更新について
原則として就労ビザには1年or3年or5年の期限が定められています。
期限の3か月前から在留期間更新許可申請ができます。
外国人労働者本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」を行います。
基本的には外国人労働者本人が行いますが、弁護士や行政書士に任せることもできます。
在留期間更新許可申請をしてから約1~3ヶ月ほどで在留資格変更許可申請が許可されます。申請する就労ビザや場所、時期にも影響されますが、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」で東京出入国在留管理局に申請した場合は1か月程かかることが多いです。
・外国人の就労ビザの更新手続|ビザ申請に強い法律事務所が解説
不許可になったらどうする?
外国人労働者の増加に伴い、不法就労問題も増えてきました。
そのため、就労ビザの審査は年々厳しくなっており、不許可になる可能性もあります。
不許可になる事例と不許可になった際の対応についてみていきましょう。
不許可になる事例
1.学歴や職歴が要件を満たしていない
就労ビザごとに定められている学歴や職歴要件を満たしていないと思われる場合、不許可になる可能性が高いです。
≪例≫
・技術・人文知識・国際業務ビザ
⇒業務内容に関連する大学卒業or国内の専門学校卒業or10年以上の実務経験
・介護ビザ⇒日本の介護福祉士資格が必要
・技能ビザ(料理人など)⇒5年以上の実務経験が必要
2.業務内容がビザの種類にあっていない
申請するビザの種類と実際の仕事内容が一致していないと思われる場合、不許可になる可能性が高いです。
≪例≫
・「技術・人文知識・国際業務」ビザで申請
⇒実際は単純労働(工場作業員など)だった
・「技能ビザ(フレンチシェフ)」で申請
⇒実際はファストフードの調理業務だった
3.会社の経営状態が不安定or信用がない
外国人を雇用する企業の経営状態や信用も審査対象になります。
以下のような会社は不許可の可能性が高いです。
・資本金や売上が少なく、経営が不安定と思われる会社
・過去に不法就労を助長したり、労働基準法違反をしていると思われる会社
・設立したばかりで実績がないと思われる会社
ただし、経営状況については単に赤字か否かではなく、適切な資金調達ができているか、業務内容なども考慮し、総合的に判断されます。
もし、審査にあたり不安なことがあれば、今後売上が増加する見込みを根拠を持って説明する文書を添付したり、その売上増加のために外国人労働者の力が必要であることを伝えられれば許可される可能性はあります。
4.日本人労働者と比較して給与が極端に低い
外国人労働者の給与が、日本人と比べて極端に低い場合、不許可になる可能性があります。
≪例≫
・フルタイム勤務なのに給与が月15万円
⇒生活するには不安定な金額である、場所によっては最低賃金未満の可能性がある
・日本人労働者は月給30万~で募集しているのに、外国人労働者は月給20万円~で募集している
⇒日本人労働者との差が顕著である
ただし、合理的な理由があって給与額に差があるのは問題ありません。
例えば、日本人労働者はリーダー候補募集であり、外国人労働者は役職なしの募集である場合は金額によっては合理的な理由があると思われます。
出入国在留管理局では審査の際に、ハローワークや求人サイトなどの募集要項を確認していることがあります。
外国人労働者と日本人労働者の募集金額が異なる場合は、合理的な理由を説明する文書を添付して申請することで誤解を回避することができます。
5.過去に不法滞在・不法就労・犯罪歴がある
過去に日本で以下のような違反をしている場合、不許可の可能性が高くなります。
・オーバーステイ(不法滞在)
・資格外活動許可なしでアルバイトをした(不法就労)
・日本や他国で犯罪歴がある(詐欺、暴力、薬物犯罪など)
不安材料がある場合は、弁護士や行政書士に相談の上申請した方が不許可を回避できる可能性が高まります。
6.提出書類に不備や偽りがあると思われる
申請書類に不備や偽りがあると思われると、不許可になる可能性があります。
「不備があれば連絡が来るのではないか」と思われるかもしれませんが、繁忙期などは連絡なしに不許可になることもあります。
申請の際は入念にチェックしましょう。
≪例≫
・学歴や職歴を偽る(卒業していないのに卒業証明書を偽造)
・会社が存在しない、または事業内容を偽る
・提出すべき書類が不足している
7.現在の在留状況が適切でない
既に日本に滞在している外国人がビザの変更や更新をする場合、現在の在留状況が適切でないと不許可になる可能性があります。
≪例≫
・「家族滞在」ビザの人がフルタイムで働いていた
・留学生なのに学校に通っていない
不許可になっても再申請できる
不許可になった理由が、書類の不備や申請内容に誤解が生じてしまったなどすぐに解消できる場合であればすぐに再申請を行います。
場合によっては理由書や上申書などを付けた方が良いケースもありますので、弁護士や行政書士に相談の上再申請すると安心です。
一度母国に帰国する方がスムーズなケースもある
就労ビザの申請が不許可になっても、在留期間内であれば何度でも再申請することができます。
しかし、一回不許可になっている以上、その理由が解消されない限り許可されることはありません。
また、何度も再申請を行うことで申請手数料がかさんでしまいます。
不許可になった理由が、在留態度が悪いと思われたなどすぐに解消することが難しい場合は、一度帰国した上で在留資格認定証明書交付申請を行う方が良いこともあります。
在留資格認定証明書交付申請の際には相当性(過去の在留態度など)は審査対象になりません。
不許可になった場合は弁護士や行政書士に今後の流れを相談することをおすすめします。
外国人労働者を雇用する際の注意点
外国人労働者を雇用する際は、日本人を雇う場合とは異なる点に注意が必要です。
適切な契約・文化的配慮・在留資格の管理などを徹底することで、トラブルを防ぎ、良好な労働環境を築くことができます。
雇用契約を明確化すること
外国人労働者とのトラブルを防ぐためには、雇用契約を明確にし、きちんと説明することが大切です。
可能であれば母国語に翻訳したものも渡すことが望ましいです。
日本で初めて働く外国人労働者の中には、給与額について総支給額をそのままもらえると思っていることも少なくありません。
社会保険料や源泉徴収税の説明も行い、手取り額もあわせて伝えておくと安心です。
また、報酬については日本人労働者と同等以上であることも求められます。
価値観や文化の違いを理解すること
外国人労働者は、日本の労働文化に慣れていない場合があります。
価値観の違いを理解し、適切に対応することが重要です。
≪例≫
・日本には「暗黙の了解」という概念があるが、海外にはない場合もある。
・日本は「チームワーク」を重要視するが、海外は個人の成果を重視することがある。
文化的な配慮と職場の多様性
外国人労働者の宗教や食文化を尊重したり、多言語マニュアルや翻訳ツールなどを利用し、言語の壁を減らす工夫が必要です。
異文化理解の研修を実施することも効果的です。
在留資格の管理を徹底すること
就労ビザの有効期限や就労ビザで働ける業務内容を把握することが重要です。
特に業務内容については人事部などの管理部門だけが把握しているだけでは足りません。
一覧で確認できる表を作成するなど、外国人労働者がいる部署全体にも周知を行っておきましょう。
外国人採用・雇用の手続きについてのお悩み・課題は解決できます
この記事では、就労ビザの申請手順や外国人雇用の際の注意点について、企業の皆さまが直面すると思われるお悩みや課題について、解決の手助けになる基本的な知識の概要をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社の外国人の就労ビザ取得や採用・雇用について、必要な手続きを適切に行われ、トラブルなく、貴社の皆さまが、日本人も、外国人も、笑顔で、働いていける未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、外国人の採用・雇用についての専門的な法律の実務を得意にしています。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当法律事務所にご依頼いただくことで、
「適切な就労ビザが分かる」
「就労ビザ申請の流れが分かる」
「就労ビザ申請の際に確認すべきことが分かる」
「就労ビザ申請が不許可になった際の対応について分かる」
「外国人労働者を雇用する際の注意点が分かる」
さらに、
「外国人との雇用契約書の注意点が分かり、法律的に問題なく作れるようになる。」
「学生ビザ(アルバイト)から就労ビザ(正社員)への変更手続きを正確に進められて、不安なく雇用できるようになる。」
しかも、
「日本に来た後のフォローアップやサポート体制について、適切なアドバイスを受けられるようになる。」
このようなメリットがあります。全力でご支援させていただきます。
当事務所では、すべての皆さまにスピード感をもって対応させていただくために、まずはメールで相談をお受けしています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00