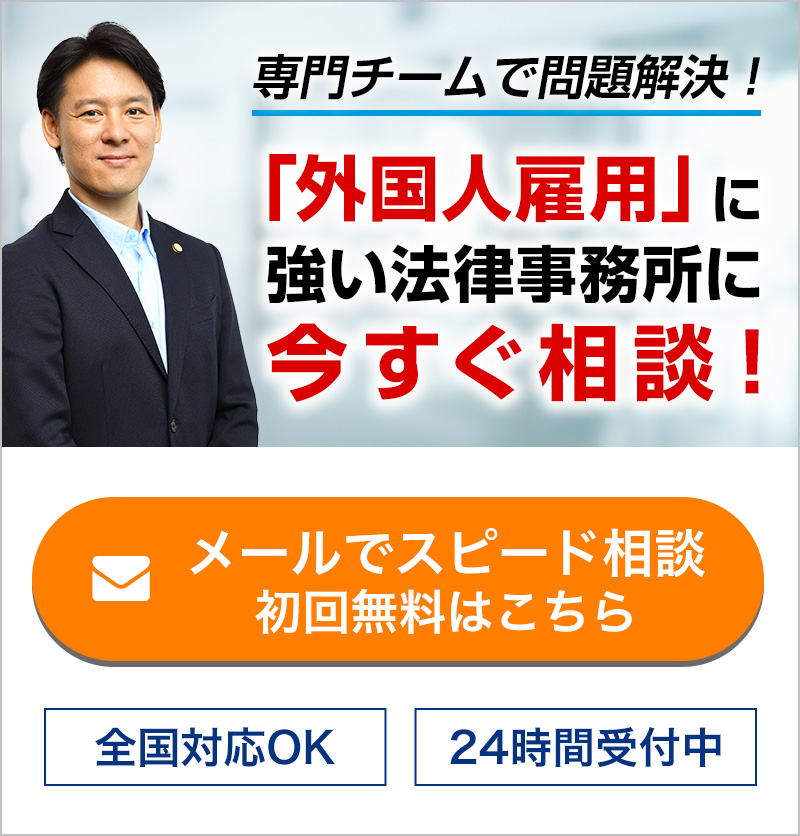目次
少子高齢化や労働力人口の減少に伴い、外国人労働者への関心が年々高まっています。
外国人採用の手続きについて企業の人事部・採用担当者の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「外国人雇用をするメリットは?」
「外国人雇用って大変そう…」
「外国人を採用する際に注意すべきことは?」
「外国人従業員の入社時・入社後に、どのような注意をすれば良いのか?」
この記事では外国人労働者を雇用する際の注意点を選考時、入社時、入社後の流れに沿って分かりやすく解説します。
外国人雇用状況について
厚生労働省の発表によると、令和5年10月末時点で外国人労働者数は2,048,675人、前年比で225,950人増加しており、届出が義務化された平成19年以降過去最高を記録しました。外国人労働者の雇用状況の概要は以下の通りです。
国籍別ではベトナムが最も多く518,364人、中国の397,918人、フィリピンの226,846人と続きます。
在留資格別では身分に基づく在留資格が最も多く615,934人、専門的・技術的分野の在留資格の595,904人、技能実習の412,501人と続きます。
在留資格別では現時点では身分に基づく在留資格が一番多いものの、対前年増加比は専門的・技術的分野の在留資格、技能実習、資格外活動の順で伸びており、就労のためにビザを取得して働いている外国人が急増していることが分かります。
また、外国人労働者数が多い産業は製造業が最も多く552,399人、サービス業の320,755人、卸売業・小売業の263,555人と続きます。
一方で外国人雇用が多い産業では卸売業・小売業が最も多く59,497か所、製造業の54,495か所、宿泊業・飲食サービス業の45,495か所と続きます。
製造業は1つの企業で多くの外国人が働き、卸売業・小売業は様々な企業で多くの外国人が働いてることが分かります。
日本国内の人手不足も相まって、外国人の専門的な能力を活かせる機会が今後さらに広がると予想されています。
外国人労働者を雇用するメリットとデメリット
外国人雇用は今後も増え続けると予想されていますが、当然にメリットとデメリットの両方があります。
特にデメリットは先におさえておくことで、リスク発生への対策になります。外国人雇用に関連するさまざまな要因を理解することは、雇用の質を高めるためにも重要です。
外国人労働者を雇用するメリット
外国人労働者を雇用するメリットは主に以下があげられます。
- 人手不足の解消になる
第一に建設業や介護分野などの人手不足の産業にとって外国人労働者の雇用は、ギャップを埋める手段となります。特に、建設業界では、インフラ整備や都市開発の需要が増加している一方で、日本国内の労働人口は減少しています。「特定技能」制度を活用すれば、業務経験のある即戦力を確保しやすくなります。その結果、プロジェクトもスムーズに進行でき、顧客満足度の向上にもつながります。 - インバウンド対策になる
外国人雇用のメリットは単純な人手不足の解消にとどまりません。
特に、人手不足が叫ばれている観光業などのサービス業では外国の文化を知り、外国語を話せる従業員は貴重な存在です。観光業や飲食業では、訪日外国人観光客の増加に伴い、外国人労働者の雇用が顧客対応力を強化するカギとなります。英語や中国語を話せるスタッフがいることで、外国人観光客の満足度が向上し、リピーターの増加が期待されます。その結果、訪日外国人向けのサービスの充実や質を上げることで今後の収益アップが見込めると考えられます。 - 海外進出の足掛かりになる
外国人労働者の母国やネットワークを活用することで、海外市場への進出や取引の拡大をすることができます。また、外国人労働者が持つ言語スキルや文化的知識、商慣習の知識は、国際取引や海外顧客とのコミュニケーションで役立ち、取引先との交渉がスムーズに進むと考えられます。 - 社内への良い刺激が生じる
社内での文化交流は、従業員の国際感覚を育て、よりオープンな職場環境を築くことができます。多文化環境での働き方は、日本人従業員にとっても学びの場となります。外国人労働者とのコミュニケーションを通じて新しい視点や柔軟な発想が生まれ、従業員同士の交流が活発になります。その結果、外国人労働者と働く上で、日本人従業員が新しい文化や価値観を学ぶ機会が得られます。 - 新しい視点やアイデアの導入ができる
異なる文化や背景を持つ人々が集まることで、多様な視点や斬新なアイデアが生まれます。特に商品開発やマーケティングにおいては、海外市場や異文化を意識したアプローチが可能になります。 - 新しいスキルや技術の導入ができる
特にITやエンジニアリング分野では、高度な技術や専門的な知識を持つ外国人労働者が企業の競争力を高めます。外国人労働者が新しい技術や専門的な知識を持ち込み、企業の技術力を育てる可能性があります。 - 既存従業員の成長が期待できる
異なる文化背景を持つ労働者と働くことは、職場に新しい刺激を与え、既存従業員の視野を広げます。また、母国ではない国で働くために来日した外国人労働者は意欲の高い存在です。外国人労働者の働く姿勢や意欲は、他の従業員に良い影響を与え、既存従業員の士気を高める効果も期待されます。過去には外国人労働者と協働する日本人スタッフが自主的に外国語を学び始めるなど、学習意欲が高まった事例もあります。 - 企業イメージの向上につながる
外国人労働者を積極的に受け入れることで、社会的責任を果たす会社としての評価が高まり、会社のブランドイメージが向上する可能性もあります。特にグローバル市場での認知度向上や多様性を重視する若い世代へのアピールにつながります。
外国人労働者を雇用するデメリット
外国人労働者を雇用するデメリットは主に以下があげられます。
- コミュニケーションが難しいことがある
日本語が十分に話せない労働者の場合、作業手順の誤解やミス、顧客対応のトラブルなど業務指示やコミュニケーションに支障が出ることがあります。多言語対応のマニュアルを用意する、日本語教育を行う、管理者やチームメンバー向けに異文化コミュニケーションの研修を実施することで対策できます。また、現場でのトラブルを減らすために、翻訳アプリやAI通訳機器を活用する企業も増えています。 - 文化や習慣の違いがある
文化や習慣は国による特色が出やすいところです。日本では当たり前のことでも、海外では当たり前でないこともあります。礼儀や働き方に対する価値観の違いから、日本特有の「暗黙の了解」が伝わらないなどの誤解や摩擦が生じる場合があります。こちらも管理者やチームメンバー向けに異文化コミュニケーションの研修を実施することで対策できます。 - 雇用管理において会社側にも負担がある
外国人労働者を雇用するには、在留資格や資格外活動の有無を正確に確認し、在留期間も管理する必要があります。このような情報は、従業員の在留資格や更新状況を登録するシステムを導入し、適切に管理することが有効です。管理や手続きに不備があると、不法就労に繋がるリスクがあるので注意が必要です。弁護士や行政書士のサポートを受けたり、在留資格や労働条件を管理するシステムを導入することで対策できます。 - 初期コストや教育コストがかかることがある
日本語研修や業務に必要なスキル研修を受けさせるなど、外国人労働者を即戦力化するためにはコストがかかります。また、外国人労働者が短期間で母国に帰国したり転職したりする場合は投資した教育コストが無駄になる可能性があります。研修費用を助成する公的支援制度を活用したり、長期雇用を前提としたキャリアプランを提示することで対策できます。 - 離職リスクが高い場合がある
人手不足の中、労働市場の競争は激化しています。高いスキルを持つ外国人労働者は、待遇の良い他の企業へ転職する可能性があります。また、会社や日本の労働文化、生活環境に適応できず、自ら帰国や離職を選ぶケースもあります。労働条件や待遇を適正に設定し、魅力的な職場環境作りをしたり、外国人労働者の生活面をサポートすることで対策できます。また、既存社員からの紹介による採用(リファラル採用)の場合はミスマッチ率が低い傾向にあります。
日本人雇用と外国人雇用の違いについて
外国人は日本人のように無条件で雇用できるわけではありません。
日本人雇用との違いのポイントについてみていきましょう。
就労可能な在留資格がないと採用できない
日本に滞在している外国人は、原則として「在留資格」を持っています。
在留資格は身分や滞在する目的に応じて与えられます。
そして、在留資格の中でも働くことができるものとできないものがあります。
外国人が日本で働くためには、就労することが許可されている在留資格を持っている必要があります。
代表的な就労可能な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。
また、「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系の在留資格を持っている場合も働くことができます。
「留学生」や「家族滞在」など原則として就労が認められていない在留資格であっても別途「資格外活動許可」を得ていれば働くことができます。
もし、採用した外国人労働者が適切な在留資格を持っていなかった場合は、「在留資格変更許可申請」か「資格外活動許可申請」を行い、許可されてから就労開始する必要があります。
・外国人の就労ビザを取得する方法|ビザ申請に強い法律事務所が解説
在留資格で認められた業務しか行えない
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格がないといけませんが、就労系の在留資格は業務内容ごとに分けられています。
例えば、代表的な「技術・人文知識・国際業務」は専門性が必要な業務が対象となっているため、単純労働をさせることはできません。
就労可能な在留資格を持っていたとしても、業務内容が在留資格の要件に適していなかったら不法就労罪(出入国管理及び難民認定法第73条)に問われる可能性があります。
外国人雇用の選考時に注意点について
外国人労働者の採用ミスマッチを防ぐため、適切な外国人雇用を行うためには、選考時から気を付けるべきことがあります。
選考の段階では在留カードの提示は求めないこと
適切な在留資格を持っていないと就労ができないため、
「可能であれば選考の段階から在留カードを確認しておきたい」
と考える方もいらっしゃると思います。
しかし、選考の段階から在留カードの提示を求めることは国籍などによる差別防止の観点から適切ではないとされています。
会社側に差別の意図がなかったとしても、外国人労働者側に不信感を与えてしまう可能性や、お見送りになったときに「国籍差別された」などの誤解が生じるリスクもあります。
必ず選考が終わり、内定承諾を得たタイミングで提示を求めるようにしましょう。
外国人雇用の目的を決めておくこと
優秀な外国人労働者を採用するためには「インバウンド対策」や「アウトバンド対策」、「職場の活性化」など外国人雇用の目的をきめておくことが重要です。
外国人労働者は「この企業で自分は価値を提供できるのか」「そして何を(サポートなど)得られるのか」を見ています。
しかし、採用担当者が外国人雇用の目的を理解できていない、社内で目的が共有されていないがために魅力的な自社アピールや採用目的を伝えられずに、採用したい外国人候補者を採れなかったという例があります。
これから1から育成していくことを念頭に採用するのと、ある程度の経験者で即戦力を期待して採用するのかでもアプローチは違ってきます。
また、採用目的はできるだけ長期的な目線の方が賢明です。
例えば、「離職が相次いでしまったから、とりあえず外国人を雇用しよう」としても、そもそもなぜ離職が相次いだのかの問題が解決しない限り、同じことが続く可能性があります。
「外国人労働者に入社してもらって新しい風を吹かせたい」「多様性を推進し、風通しの良い職場にしたい」など今ある課題の長期的な解決策として外国人雇用を行うことが大切です。
そして、外国人雇用の目的は採用担当者全員に共有し、候補者に自社の魅力をアピールできるようにしておきましょう。
また、実際に外国人労働者が配属される予定の部署にも外国人雇用の目的を共有し、理解してもらい適切なサポートができるようにしておくことも重要です。
内定を出す際は「就労可能な在留資格が確認できないときは内定取り消しになる」旨もあわせて伝えること
内定を出すときは「適切な在留をしていると確認できない場合および適切な在留資格に変更を希望しない場合は内定取り消しになる」旨を伝えます。
内定を出したタイミングではまだ在留カードの確認はしていません。
万が一在留期間が過ぎていた、本物かどうか疑わしい在留カードを提示された場合、就労するにあたり在留資格変更を拒否された場合、就労可能な在留資格への変更が許可されなかった場合に内定取り消しができるようきちんと伝えておくことが大切です。
時には抵抗されることもあるかもしれませんが、本来は就労できない外国人を雇っていた、本来は行ってはいけない業務を行わせていたとなれば、会社も不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2)に問われてしまう可能性があります。「内定取消」というとグレーなイメージがあるかもしれませんが、この場合は、法律上働かせてはいけない人を働かせるリスクを減らすための定めなので、正当な運用といえます。
外国人雇用の入社時の注意点について
外国人労働者と会社双方が安心して雇用をスタートするためには、入社時にも気を付けるべきことがあります。
在留カードを確認すること
内定承諾後に在留カードの提示を求め、在留期間内であるか、適切な在留資格を持っているかの確認をします。就労可能な在留資格を持っていたとしても、その在留資格で認められていない活動はできません。適切な在留資格を持っていなかった場合は在留資格変更の手続きが必要なことを伝えたり、期限を過ぎていた場合はすぐに弁護士や行政書士に相談する必要があります。
雇用契約書には「本契約は、雇用者が就労可能な在留資格を取得した場合に限り、有効となる。」のように記載し、適切な在留資格を得ないと有効にならないようにします。
また、在留カードはコピーや写真ではなく必ず原本で確認するようにしましょう。
在留カードが本物かどうか確認できるアプリも利用すると安心です。
労働条件や就業規則についてはきちんと説明すること
労働条件は誤解が生じないように、丁寧に契約内容を説明することが重要です。
特に労働時間においてはトラブルが多いです。
「1日8時間の契約だが、業務状況によっては延長をお願いする場合がある」など残業が発生する可能性がある場合はあらかじめ伝えます。
また、可能な限り母国語へ翻訳した雇用契約書(雇用条件通知書)や就業規則も用意し、書類外国人労働者にしっかりと確認いただくようにしましょう。
給与について、外国人労働者は提示された金額がそのまま振り込まれると思っていた事例があります。給与計算方法や控除するもの(社会保険や所得税、その他労使協定で定められた積立金など)とおおよその手取り額も資料を用いて伝えておくと安心です。
また、外国人雇用を行うのは社内制度を整備する良いきっかけにもなります。
自社の就業規則が外国人雇用に適しているかの確認を行うことも大切です。
原則として日本人と同待遇にすること
在留資格の変更や更新時においても日本人と同待遇かは確認されます。
労働基準法をはじめ、労働法規を遵守していても、日本人と差があれば問題とされます。
同待遇とは、給与額だけでなく福利厚生なども含まれます。
しかし、正当な理由がある場合は差があっても問題ありません。
例えば、「外国人労働者は未経験募集だが、日本人労働者は経験者募集である」場合は、賃金に差があっても正当な理由があるといえます。
入国管理局は在留資格変更や期間更新の審査の際には求人サイトやハローワーク、会社のホームページの求人募集を見ていることがあります。
もし、募集している条件よりも外国人労働者の条件が劣る場合は正当な理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。
グローバルな人材競争が激化している中、優秀な外国人労働者を確保するためにも、公正で魅力的な労働条件にしていくことが求められます。
外国人雇用の入社後の注意点について
外国人労働者と会社双方にリスクなく雇用を継続させるためには、入社後にも気を付けるべきことがあります。
不法就労にならないように管理すること
・就労可能な在留資格を持たずに働いた場合
・在留期間を超えて働いた場合
・在留資格にあった業務内容でなかった場合
・資格外活動許可を得て働く際に週28時間を超えてしまった場合
に該当する場合は入管法違反になります。
また、派遣社員としては働けない在留資格もありますので、雇用形態が適切か否かの確認も必要です。
入管法違反にならないように会社側でも管理する必要があります。
・内定後に在留カードの提示を求めて適切な在留資格があるか確認する
・在留期間を控えておいて更新3か月前に会社からも更新のアナウンスをする
・在留資格外の業務をさせてはならないと現場の従業員に徹底して伝える
・資格外活動許可を得て働く場合は週の労働時間集計を必ず行う
ことを社内ルールとして徹底することが重要です。
対応すべきことの一覧を作成し誰でも一定のレベルで抜け漏れなく対応できるようにすることも有効です。
もし、入管法に違反してしまった場合は、外国人労働者本人は不法就労罪(出入国管理及び難民認定法第73条)に問われる可能性があります。しかし、罪に問われるのは外国人労働者本人だけではありません。企業や場合によっては人事担当者など個人としても不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2)に問われてしまう可能性があります。管理すべきことの一覧表を用意しておくと安心です。
不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2)は5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い罰則があります。外国人労働者は日本の制度に不慣れな場合もあり、在留資格の制度についても完全に理解していない可能性もあります。企業側も入管法の知識を持ち、外国人労働者本人と一緒に在留資格や期間の管理を行うことが大切です。
価値観や文化の違いを理解すること
外国人労働者を迎え入れる会社では、価値観や文化の違いを理解して受け入れる姿勢が求められます。異なる価値観や文化は、新しいアイデアや創造的な解決策を生み出す源泉となり、異文化の視点を取り入れることで、企業の競争力が向上します。
また、外国人労働者が自分の文化や価値観を尊重されていると感じると、仕事に対する満足度が高まり、生産性も向上することが期待されます。
◆価値観や文化の違いを理解するための方法
1.日本人特有の価値観や文化を認識すること
相手の価値観に違和感や嫌悪感を抱いてしまうのは、自身の価値観や文化と異なるからです。例えば、日本には言いたいことをハッキリとは言わずに空気を読むという価値観・文化があります。しかし、海外の中には「言いたいことははっきり伝える」という価値観・文化のところもあります。
真逆の価値観・文化なので、違和感を覚えることもあるかもしれませんが、「日本には言いたいことをハッキリとは言わずに空気を読むという価値観・文化がある」と認識できていれば、「価値観・文化が合わないから違和感を覚えるのね」と冷静に受け止めることができます。
もし、日本の文化・価値観を認識できていない状態だったら「あの人は空気が読めない人だ」と矛先が人に向いてしまい、外国人労働者と働くことにストレスを感じてしまう可能性があります。
価値観や文化には「正しい」や「間違い」という考えは存在しません。
そのため、日本も含め、一つの文化・価値観を冷静に受け止める必要があるといえます。
2.教育とトレーニングを行う
管理職や従業員に異文化理解や多様性をテーマにした研修を行うことが効果的です。
研修では、外国人労働者の母国文化や宗教について、基本的な知識を共有します。
3.オープンなコミュニケーションを行う
定期的に面談を実施し、外国人労働者の意見や悩みを聞く機会を設けます。最初はなかなか本音を話してくれないかもしれませんが、きちんと聴いてもらえることが分かったら回数を重ねるにつれて話してくれるようになるでしょう。
また、外国人労働者の価値観や文化を理解し配慮することも必要ですが、日本の価値観や文化を理解していただくことも必要です。信頼関係が強くなってきたら日本の価値観や文化についても伝え、相互理解を深めることが大切です。
4.配慮ある職場環境作りをする
可能な限り英語を優先的に多言語対応のマニュアルやツールを導入します。多言語対応のマニュアルなどの作成は会社にとっては大きな負担になってしまう可能性があります。その場合は、絵やスクリーンショット、写真を用いるなど可視化できるマニュアルを作成することが効果的です。
5.専門家を活用する
必要に応じて、社会保険労務士や産業カウンセラー、異文化コンサルタントやコミュニケーションコンサルタント、通訳のサポートなどを受けることも検討しましょう。
異動の際は在留資格の内容にあっているか確認すること
会社の一員として働いている以上、外国人労働者も異動する可能性も考えられます。
日本人であれば違法でない限りどんな業務でも従事することができますが、外国人労働者の場合は、在留資格の範囲内の業務しか行えません。
外国人労働者を異動させる際には、異動後の業務が現在の在留資格に合うかきちんと確認することが必要です。
もし、今後、外国人労働者に行ってほしい業務が現在の在留資格に合わない場合は、在留資格変更許可申請をして、許可後に新しい業務を行ってもらう必要があります。
就労可能な在留資格であることのみならず、業務内容によっても必要な在留資格が異なる点は常に留意しておきましょう。
外国人採用・雇用の手続きについてのお悩み・課題は解決できます
この記事では、外国人雇用の注意点について、企業の皆さまが直面すると思われるお悩みや課題について、解決の手助けになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社の外国人の就労ビザ取得や採用・雇用について、必要な手続きを適切に行われ、トラブルなく、貴社の皆さまが、日本人も、外国人も、笑顔で、働いていける未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、外国人の採用・雇用についての専門的な法律の実務を得意にしています。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当法律事務所にご依頼いただくことで、
「外国人を採用する際に注意すべきことが分かるようになる。」
「外国人従業員の入社時・入社後に、法律的に注意すべきことが分かるようになる。」
さらに、
「外国人との雇用契約書の注意点が分かり、法律的に問題なく作れるようになる。」
「学生ビザ(アルバイト)から就労ビザ(正社員)への変更手続きを正確に進められて、不安なく雇用できるようになる。」
しかも、
「日本に来た後のフォローアップやサポート体制について、適切なアドバイスを受けられるようになる。」
このようなメリットがあります。全力でご支援させていただきます。
当事務所では、すべての皆さまにスピード感をもって対応させていただくために、まずはメールで相談をお受けしています。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※本稿の内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|