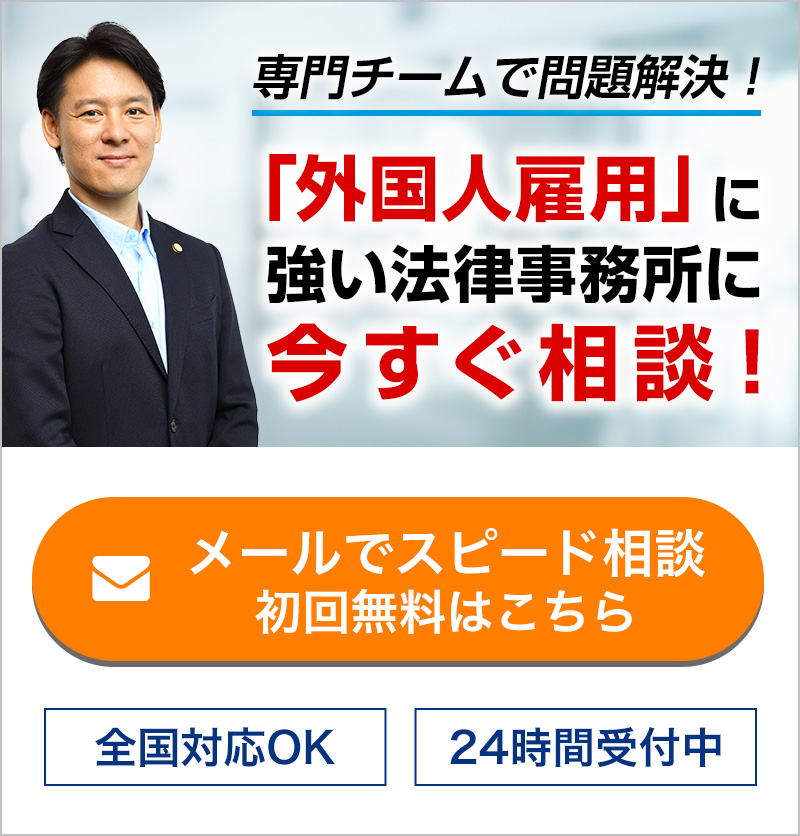外国人材の活用を考えている企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
■外国人雇用に伴う法的リスクをどう回避できますか?
「ビザや労務管理の法律が複雑で、ミスがないか常に不安。手続きの不備で、会社全体が罰則を受けたり、外国人材を受け入れられなくなったりするリスクを避けたい。」
■採用後の煩雑なマネジメント業務負担をどう軽減できますか?
「採用後のビザ更新や生活サポート、文化の違いによるトラブル対応に時間と手間がかかりすぎている。人事や管理職が本来の業務に集中できず、疲弊してしまう状況を何とかしたい。」
■外国人材を定着させ、モチベーションを維持するには何が必要ですか?
「せっかく採用してもすぐに辞めてしまうことが多く、投資に見合う効果が得られない。外国人材が長く意欲的に働き続けられるような、具体的な信頼関係構築や環境整備の方法が知りたい。」
この記事では、外国人雇用の複雑なプロセスを一元管理できる外国人雇用マネジメントサービスの具体的な活用法を解説。さらに、実際にサービスを導入し、外国人材の定着と戦力化に成功した成功事例をご紹介します。
目次
外国人活用が「待ったなし」の時代へ
わが社は関東地方で倉庫業を営んでいます。業務の都合上、シフト勤務、土日祝勤務があり、年々人材の確保が難しくなっていました。また、転職市場が活発化したことにより、せっかく育成した人材の退職にも悩まされていました。
採用活動も思わしくなく、昨年度から外国人労働者の雇い入れを始めたのですが、現場や管理職とのコミュニケーションがうまくいっておらず、外国人材のやる気低下、職場の士気低下、現場でのトラブル、管理職の負担増加といった問題が生じています。
外国人労働者の雇い入れについて、事前知識がないまま急ぎ足で進めてしまいました。外国人労働者のマネジメントサービスが気になっているのですが、わが社はまず、何から始めたらいいのでしょうか。
なるほど。今日は外国人労働者のマネジメントについての相談ですね。まずはビジネスにおける外国人活用の必要性について解説します。
「令和6年版 労働経済の分析」(厚生労働省)によると、直近10年間で、ほぼすべての産業において欠員率の上昇がみられます。また、欠員率が大きく上昇する要因として、企業規模が小さいこと、建設業、飲食サービス業であること、パートタイム労働者であることなどが挙げられます。つまり、人手不足の痛手が大きい企業や業種であるほど人手不足の影響を受けている現状があるといえます。
一方で、転職市場の活発化やインフレによる賃金上昇の影響もあり、大企業間での転職や、中小企業から大企業への転職率は上昇傾向です。当面は少子化の影響も続くことが予想できるため、中小企業の人手不足対策は待ったなしであります。とはいえ、日本人労働者を獲得するためには、大企業と同等程度の給与水準や福利厚生が必要となるケースもあり、中小企業にとっては負担が大きくなります。
そこで、外国人労働者の活用が求められます。日本人の職場選びの評価軸は賃金や通いやすさ、福利厚生が大きなポイントであると考えられます。一方で、外国人労働者はこれらの要素のほかにも職場の人間関係や、私生活への手助けの有無、同じ外国人労働者がいるかどうか、そういった点も評価軸になり得ます。つまり、外国人労働者の求人採用において、中小企業は取り組み方次第で、大企業に競り勝てる可能性があるということです。
外国人労働を雇用することにより、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給を受けながら、外国人労働者の労働環境の整備を行うことができる可能性もあります。
外国人雇用マネジメントサービスとは?導入のメリット
外国人材の獲得に舵を切ることによって、人材獲得競争で大企業にも競り勝てるという点に希望が持てました。一方で、雇い入れ後のマネジメントや環境整備を見据えて採用しないと、人材を獲得して終わりになってしまいますよね。
そうですね。コストをかけて雇用した人材を有効に活用するというビジネス的観点はもちろん、異国の地で働こうとする外国人を雇い入れたからには適切にマネジメントすべきという法的・社会的責任の観点からも、外国人雇用マネジメントサービスのニーズは高まっていきます。
外国人雇用マネジメントサービスの定義と機能
外国人雇用マネジメントサービスという呼称は聞きなれないと思いますが、要は外国人材の採用と雇用について、法律面で必要なことをアウトソーシングするサービスです。具体的なサービスの選び方については後述しますが、一般的には下記のような機能が提供されます。
■求人表・求人内容チェック
■ビザ申請・ビザ管理・在留資格チェック
■面接・労働条件の説明・雇用契約書作成
■労働環境(研修・コミュニケーションなど)の整備
■安全衛生に関するチェックリスト作成
■管理職への労務管理・文化やコミュニケーション尊重のためのアドバイス
■外国人材定着のためのロードマップ作成
■外国人材のトラブル対応
■日本語に不慣れな外国人材の行政手続きサポート
なぜ「今」、外国人雇用マネジメントサービスが必要なのか?
外国人材の雇用において、文化や言葉の違いは業務効率、人材の定着やモチベーションの向上にとって、大きな障壁であるといえます。これらの違いによって、下記のようなトラブルが起こり得ます。
■休暇に関する考え方の違いにより、帰国のための長期休暇、突発的な休暇など、事業に支障が出る休暇を要求される
■業務上の指導や注意が気に入らず、突然職場に来なくなってしまったり、指示に従わなくなる
■コミュニケーションのすれ違いによって弁護士を通してパワハラを主張される
■寮費の負担、一時帰国費用の負担について説明が足りずに不信感を持たれてしまう
■社会保険制度や福利厚生について外国人材が理解ができておらず、説明責任を追及されてしまう
■作業内容や労働環境についての不満が噴出し、外国人労働者同士でストライキを起こされてしまう
これらは一例ですが、コミュニケーション不足、双方の文化の理解不足、ルールの整備が追い付いていないことが原因です。一方で、こういったトラブルを防止するためには、各種法令の理解や多方面への指導や配慮が必要になるなど、マネジメント層の負担が過大になるリスクがあります。
外国人雇用マネジメントサービスを活用すれば、こういった煩雑な業務を外注しながら、社内にもノウハウが蓄積されていきます。また、法律の専門家が支援することで、ルールや制度の整備・周知によって外国人労働者と信頼関係を構築できるといったメリットがあります。
企業がサービスを最大限に活用する「4つのステップ」
外国人雇用マネジメントサービスによって、外国人労働者を活用するための社内の仕組づくりもできるんですね。ゼロからルールや仕組みを整備することは、人手や作業時間を要するので後回しになりがちですから、専門家に依頼する方が効率的であると思いました。
おっしゃるとおりです。外国人雇用マネジメントサービスにより、企業と外国人労働者の成長し続ける関係をサポートします。次は、外国人雇用マネジメントサービスを最大限に活用するための4つのステップを解説していきます。
ステップ1:採用計画と受け入れ体制の明確化
第1のステップは、採用計画と受け入れ体制の明確化です。第1のステップでは、下記の点を重視しながら計画を策定していきます。
■採用する人数や人物像を明確にする
■外国人材が行う業務を決定し、マニュアルや教育体制を整備する
■募集方法・選考の流れを決定する
■募集内容・雇用条件を決定しておく
特に重要なのは、募集内容・雇用条件の明確化と、これらを外国人材に伝える手段です。募集内容の明示は、労働契約の基礎となる部分で、求人の際には必ず行わなければなりません(労働基準法第15条参照)。求人票作成の際にはリーガルチェックを行い、渡航費用や帰国費用の負担、寮の有無などトラブルになりがちなポイントを押さえておくようお勧めします。
また、従事する業務内容・契約期間・就業場所・労働時間・休日・賃金・社会保険の適用等に関する事項は、書面で明示し、残る形で保管しておきましょう。日本語や母国語で説明を行い、外国人労働者がきちんと理解できるようにすることがポイントです。
募集の際に書面にて明示した労働条件等を変更する場合には、変更後の内容も書面にて交付するようにしましょう。
ステップ2:入社後の定着とパフォーマンス最大化
外国人労働者に長く、良好なモチベーションで就労してもらうためには、外国人材の働きやすさを追求していくことも必要です。法務の観点からは下記のような取り組みが可能です。
■社内規定の多言語化を行い、外国人材が社内のルールや福利厚生、給与規定などを理解できるようにする。
■役職者へのコンプライアンス研修を行い、役職者を外国人材の相談窓口とする。
■社員寮の準備を行う際には、物件管理者との賃貸借契約、外国人材との賃貸借契約を適切な契約書をもって締結する。
■文化や生活習慣などお互いの違いを認め合いながら働けるよう、日本人労働者へのコンプライアンス研修を行う。
参照:「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)
ステップ3:法令遵守と労務管理の徹底
外国人材を活用するためには、労働基準法をはじめとした法令を遵守し、適切な労務管理を行うことも不可欠です。このステップが欠けると、外国人材の安心安全な就労が妨げられることはもちろん、労働災害の発生により企業の社会的信用リスク・金銭的リスクが高まります。法務の観点からは、下記のような取り組みが可能です。
■現場管理者への労働基準法をはじめとした労働関係法令の研修を行う。
■健康診断、面接指導の制度を外国人材に説明したうえで、必ず参加するように促す。(労働安全衛生法第66条の4参照。)
■機械の使用方法について視認性のあるステッカーを作成し、労働災害を防止する。
■勤怠管理・有給管理のルールを明確化し、形に残るようにしておく。
ステップ4:多様性(D&I)を活かした組織文化の醸成
外国人材はもちろん、既存の日本人労働者が働きがいを見出し、高いモチベーションで業務に向き合うためには、組織文化を醸成し、チームワークを高めていく必要があります。組織文化を醸成する際に、外国人材による多様性を活かすのは効果的です。法務の観点からは、下記のような取り組みが可能です。
■外国人材から意見をヒアリングする機会を設けて、労働環境の改善はもちろん、業務上の革新的な解決策の発見に繋げる。
■必要に応じて労働条件・ポジションの変更を行える体制を構築し、人材の適切配置を通して組織力を強化する。
■労働者からの多様化する要望について、対応の有無・度合いを適切に検討し、組織の秩序と柔軟性を両立させる。
【成功事例紹介】外国人雇用マネジメントサービス活用のリアル
外国人雇用マネジメントサービスの活用について少し理解が深まりました。サービスを利用する際には、サービスの利用計画は自社で策定するのでしょうか?
当事務所では、まず企業様からのヒアリングを大切にしています。ビジネス上、法律上の懸念点を確認し、適切な利用計画を一緒に考えていきます。また、当事務所では、企業様へのサービス導入実績が多数あります。一部ですが、3つの事例を紹介しますのでご参照ください。
事例1:製造業A社(離職率を30%から10%以下に改善)
従業員数300名の中堅精密機器メーカーであるA社は、熟練技術者による高度な技能が求められる製造ラインを抱えていましたが、高齢化と退職による技術伝承の危機に直面していました。この技術者の穴を埋めるため、特定技能外国人を中心とした採用を強化していましたが、入社後のサポート体制が不十分であったため、離職率が30%に達するという深刻な課題を抱えていました。さらに、複雑な労務管理ミスが原因で、外国人材の在留資格に影響が出るのではないかという法的リスクへの懸念も高まっていました。
この状況を打開するため、A社は弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の外国人雇用マネジメントサービスを導入し、ビザ申請の依頼だけではなく、「外国人労務顧問」としてサービスの活用を決めました。
まず、弁護士によるリーガルチェックのもと、労働条件や評価制度を見直し、外国人材に配慮し、法令を遵守した形で雇用契約書や社内規則を整備しました。これにより、労務管理体制の透明性が確保され、不法就労等の法的リスクを事前に排除しました。
次に、定着支援として、定期的な生活相談サポートに加え、日本人社員向けの異文化理解研修を実施し、社内全体の受け入れ体制を強化しました。
その結果、法的安定性と手厚い生活・労務サポートが両輪となり、外国人従業員からの企業への信頼感が大幅に向上。課題であった離職率は10%以下にまで大幅に改善しました。さらに、法令遵守の基盤が確立されたことで、技術分野での高度人材(技術者)の採用にも安心して踏み切ることができ、企業の製品開発の多角化も実現しました。この成功は、外国人雇用において「法的安心感の提供」が「人材の定着」に直結することを証明しています。
事例2:IT企業B社(採用から入社までのリードタイムを平均1.5ヶ月短縮)
Webサービス開発を行うベンチャー企業のB社は、グローバル市場への事業拡大を目指し、高度なスキルを持つ外国人エンジニアの採用を積極的に行っていました。しかし、優秀な人材は世界中で争奪戦となっており、複雑な在留資格(ビザ)申請手続きに時間がかかり、内定から入社までの採用リードタイムが長期化してしまうことが大きなネックでした。また、採用後も、日本の商習慣や社内ルールに関するミスマッチから、外国人エンジニアが早期に戦力化しないという課題を抱えていました。
B社は、このスピード感と確実性を担保するため、「在留資格・ビザ申請サービス」と「応募者リーガルチェック」に強みを持つ、弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の外国人雇用マネジメントサービスを導入しました。
まず、弁護士・行政書士によるチームが、内定を出した優秀なエンジニアのビザ申請手続きを迅速かつ確実に代行。さらに、採用計画の初期段階で応募者の資格要件に対するリーガルチェックを行うことで、採用後の手続き遅延や不許可リスクを最小限に抑えました。この法務サービスの徹底により、採用から入社までのリードタイムを平均1.5ヶ月短縮することに成功し、競合他社よりも早く優秀な人材を確保できるようになりました。
入社後も、外国人雇用マネジメントサービスによる、業務開始時の文化的な橋渡しサポートを活用。法的・行政的な不安がなく業務に集中できる環境が整っていたことも相まって、外国人エンジニアのオンボーディング期間は従来の半分に短縮されました。結果として、B社は高度人材を早期にプロジェクトの主力メンバーとして活用することができ、グローバル市場での開発スピードと競争力を高めることに成功しました。この事例は、法務手続きのスピードと正確性が、高度人材の確保と早期戦力化に極めて重要であることを示しています。
事例3:飲食・宿泊C社(緊急募集やシフト穴埋め対応が年間80件減少)
ホテル・レストランチェーンのC社は、現場スタッフの慢性的な人手不足と労務管理が不十分であることによる意図せぬ法令違反リスクに悩んでいました。このリスクへの不安が、外国人材の定着を妨げ、結果として現場の欠員が常態化していました。
C社は、この現場の労務リスクの解決こそが安定化の鍵と捉え、「外国人雇用のトラブル対応」を含む、弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の外国人雇用マネジメントサービスを導入しました。
まず、弁護士による社内体制コンサルティングを実施し、日本人社員と外国人社員双方の雇用に関する労務管理ルールを法的な観点から明確に整備。これにより、現場のマネージャーは労務・法務の観点から自信を持って指導・管理できるようになり、現場レベルでの法令違反リスクを実質ゼロにしました。
さらに、マネージャー層への研修を通じて適切なコミュニケーションと指導法を習得した結果、外国人材は安心して長く働く環境だと認識するようになりました。
その結果、C社は劇的な成果を達成しました。以前は常に欠員があり、その緊急募集やシフト穴埋め対応が年間で約100回発生していましたが、サービス導入と体制整備後の1年間では、これが約20回に減少しました。これは、現場の欠員リスクが年間で80%減少したことを意味します。この安定化により、日本人スタッフの業務負荷も大幅に軽減され、C社はサービスの質向上に注力できるようになりました。この事例は、法的安心感とマネジメント体制の強化が、組織の安定化と持続的な成長を可能にする効果的な手段であることを示しています。
サービス選びのチェックリスト
外国人雇用マネジメントサービスを活用することで、単純作業に従事する人材だけでなく、高度人材の採用を行えるというメリットもあるんですね。さきほど気になって外国人雇用マネジメントサービスを提供している企業を探してみました。なにか選び方のポイントがあれば教えていただきたいです。
外国人雇用マネジメントサービスを選ぶ際には、自社の外国人雇用を採用から人材活用まで幅広くサポートしてくれ、法律面で必要なことを守りながら、外国人採用のメリットを最大化できるかどうかが重要です。
外国人材を「戦力化」するための要点
外国人材の雇用は、採用、教育、定着、戦力化という段階を踏みながら、計画的・戦略的に行う必要があります。採用はしたものの、教育環境が十分に構築できていなければ、職場内で外国人材が戦力になりません。
また、せっかくの教育環境を整備しても、慣れない土地で暮らし、働く外国人材の生活面のサポートができなければ、職場に定着してもらうことは難しく、かけたコストが回収しきれなくなってしまします。
外国人材を戦力化するためには、前述した段階を踏まえて以下の点を大切にしましょう。
■自社の求める人物像を整理し、採用活動を行う
■採用条件に相互の認識違いが生じないよう、書面・対面での説明を行う
■職場の教育制度・安全管理を構築する
■外国人材に必要なビザや労務に関する法律手続のサポートを確実に行い、仕事に集中できる環境を整備する
■外国人材を幅広くサポートし、自社に定着するメリットを感じてもらう
■外国人材の成長度合いや実力に見合った責任や業務を割り当てる
失敗しない!サービス選びのチェックリスト
外国人雇用マネジメントサービスを選ぶ際には、採用、教育、定着、戦力化という段階に幅広く対応してくれるサービスを選びましょう。そのうえで、チェック項目と評価ポイントを一覧にしましたのでご参照ください。
| チェック項目 | 評価ポイント |
| 実績・専門性 | 自社の業界・職種における支援実績があるか? |
| サポート範囲 | 法務手続きだけでなく、労務管理のマネジメントまでカバーしているか? |
| 柔軟性・連携 | 自社の文化や制度に合わせたカスタマイズが可能か? |
| コスト構造 | 月額費用が明確で、費用対効果はどうか? |
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の外国人雇用マネジメントサービスについて
当事務所では、外国人雇用マネジメントサービスの提供も行っております。チェック項目と評価ポイントの表を基に、当事務所のサービスについてご紹介します。企業様へのサポートのほかにも、監理団体向けのサポートや、外国人雇用サービスセンターを活用した留学生のインターンシッププログラムの実施、高度人材の採用といった専門的なサポートも行っております。
ぜひ、初回のメール無料相談をご活用ください。
| チェック項目 | 評価ポイント | 当事務所のサービス |
| 実績・専門性 | 自社の業界・職種における支援実績があるか? | 企業法務の専門家として数々の業界・業種の企業様へのサポート実績あり。 |
| サポート範囲 | 法務手続きだけでなく、労務管理のマネジメントまでカバーしているか? | 弁護士・社会保険労務士・行政書士をはじめとした専門家が、企業様に必要なサポートを幅広くカバー。 |
| 柔軟性・連携 | 自社の文化や制度に合わせたカスタマイズが可能か? | 初回の無料相談・契約締結後のこまめなヒアリングを通じて、企業様のご要望をできる限り反映。 |
| コスト構造 | 月額費用が明確で、費用対効果はどうか? | 報告・連絡・相談・質問が気軽にできるチャットサービスもあり、費用や費用対効果についても正直に対応。 |
外国人材のマネジメントに関するお悩み、リスク、課題は解決できます
外国人材のビザや労務管理、もしもの際のトラブル対応には不安があったので、弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談できる点が心強いと思いました。ぜひお願いしたいです。
はい。企業法務の専門家としてビジネス上のアドバイスも可能なため、貴社にあったサポートプランを一緒に構築していきます。外国人材を活用し、人材不足を乗り越えましょう!
この記事では、外国人材を活用しようとする企業の皆さまが、外国人のマネジメントに関して、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、外国人の雇用・マネジメントについての専門的な法律の実務を得意にしています。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当事務所にご依頼いただくことで、
「外国人労働者を雇用する際に守るべき法律や、外国人材特有のトラブルについて理解し、適切な対策をすることができる。」
「外国人労働者を雇用した後のマネジメントやトラブル、疑問点について包括的に随時相談することができる。」
「ビザ管理や行政手続きといった日常生活に関するサポート、労働環境の整備や不法就労の防止といった透明感のある経営を通して、外国人材の定着とモチベーションアップを目指せる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「外国人労働者の採用を検討した時点から、採用、雇用、労働環境の整備、マネジメント、トラブルへの対応などを包括的に依頼することができ、現場や管理職の負担が軽減された。」
「外国人材特有のコミュニケーションや文化の違いに苦労していたところ、信頼関係構築のための取り組みや、管理職によるマネジメントのポイントについてアドバイスをしてもらい、法的にもビジネス的にも安心して相談することができた。」
「外国人労働者への制度の説明、苦情への対応、ルールの設定周知、現場を考慮したアドバイス、従業員への研修の支援などもしていただいた。従業員、外国人労働者ともにいきいきと働くことができている。また、管理者が本来業務に集中することができている。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年11月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00