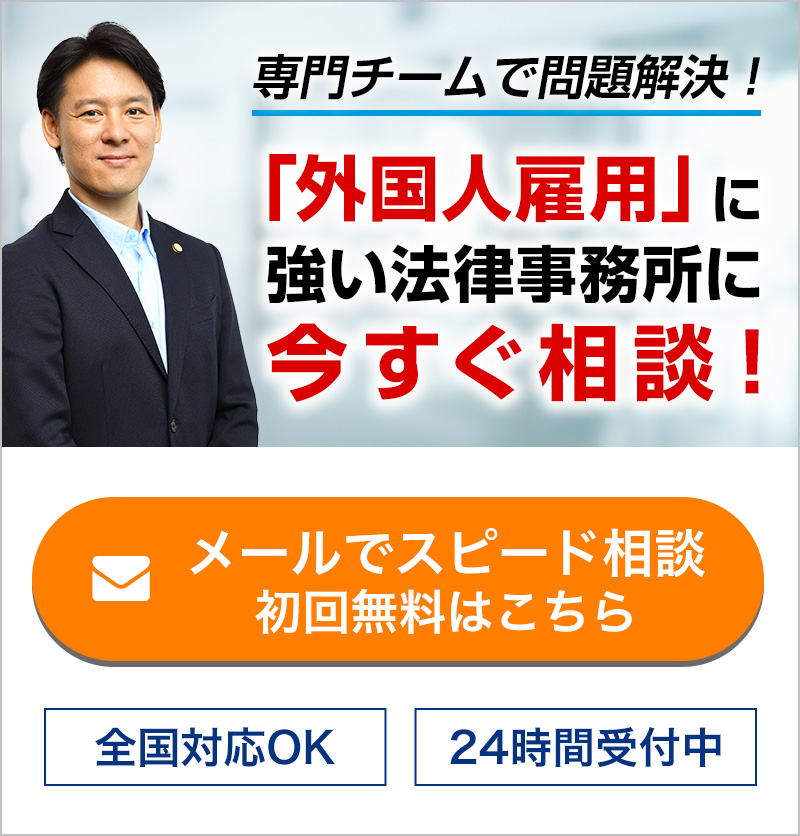外国人を雇用しようとする企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「人手不足が深刻で外国人労働者の採用を検討しているが、前例がないため環境の整備が難しい。」
「外国人労働者を活用する際の注意点や法的な要点を知りたい。」
「外国人労働者には日本人と同じように労働基準法などの法律が適用されるのか?」
この記事では、外国人を雇用しようとする企業に向けて、外国人労働者と労働基準法のポイントについて弁護士が詳しく解説します。
目次
外国人労働者を雇用する際の基本知識
当社は関東に工場を複数有し、車のシートやバネなどの部品を製造しているメーカーです。当社の製造する部品の需要は堅調なものの、昨今の人手不足により、工場作業員の人材確保が難しくなっています。
そこで、社内で外国人労働者の採用を進める計画が上がりました。一部の役職者からは「外国人労働者を採用すれば人件費が抑えられるのではないか?」という声もありますが、外国人労働者には労働基準法が適用されないのでしょうか?また、外国人労働者の採用にあたって守るべきルールがあれば教えてほしいです。
なるほど。今日は外国人労働者と労働基準法についての相談ですね。まずは外国人労働者を採用する前にチェックしたい基本知識について解説します。
外国人労働者とは?
外国人労働者とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)で定められている在留資格の範囲内で就労活動が認められ、実際に日本で就労をしている外国人を指します。2025年10月現在、在留資格は27種類あります。在留資格によって、就労が認められるかどうか、どの程度の就労が認められるか異なります。
在留資格に定められた範囲で就労が認められる18種類の在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動、以上18種類の在留資格では、在留資格に定められた範囲内での就労が認められています。在留期間は各区分により異なりますので、雇い入れの際には慎重に確認しましょう。
一般的には、下記の4種類の雇用が多く見られます。
■技術:(例)コンピューター技師、自動車設計技師
■人文知識・国際業務:(例)通訳、語学指導、デザイナー
■企業内転勤:(例)企業が期間付きで海外の本支店から受け入れる従業員
■技能:(例)中華料理のコック
原則として就労が認められない5種類の在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、以上5種類の在留資格では、原則として就労することはできません。留学と家族滞在の在留資格を持つ外国人には、資格外活動の許可を受ければ就労が可能となりますが、1週間の労働時間は28時間が上限となります。また、留学では在籍する教育機関があり、家族滞在の場合には家族の都合があるため、採用・教育・中期的な就労は難しい場合があります。
就労活動に制限がない4種類の在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、以上4種類の在留資格には、就労活動に制限がありません。
在留資格による外国人労働者と混同されやすい制度に、技能実習制度があります。技能実習生も在留資格によって事業に従事しますが、技能実習制度はあくまでも技能実習生の技能等の習得等のためのものであり、労働力の需給の調整の手段にすることはできません。技能実習生を受け入れる際には、法律の趣旨に反しないように注意が必要です。(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第3条参照)。このような技能実習生も、労働者として日本人労働者と同様に労働関係法令の適用を受けます。
「外国人雇用状況の届出について」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)をもとに作成
・製造業における外国人雇用|就労可能なビザ・雇用時の注意点を解説 | 国際ビジネス法務サービス
外国人労働者の活用における課題
外国人労働者の活用は、人手不足・労働力不足の解消の助けになりますが、いくつかの課題もあります。外国人労働者とのトラブル、外国人労働者によるトラブル、職場環境の悪化を防止するためにも、適切な雇用を行うようにしましょう。
危険な環境での労働
厚労省の調査によると、外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等で一番多かった違反事項は「使用する機械等の安全基準」で25%でした。
実際のケースでは、工場にて技能実習生が機械に指を挟まれて負傷、機械の停止をせずに機械つまりを直そうとしたことが原因であったため、母国語による手順書の作成・通訳を介した教育・注意喚起のステッカーの貼付といった指導・安全対策が行われました。意思疎通の難しさから機械の使用や作業についての注意喚起が不十分なまま、危険な環境での作業をしている外国人労働者もいます。
不適切な賃金支払い
違反事項として次に多いのは、「割増賃金の支払い」で15.6%です。賃金・割増賃金の不払いについては、技能実習生から労働基準監督署への令和6年の申告内容のうち、約8割を占めています。
労働基準法についての知識が乏しく、事業者の不適切な賃金に気づかないケースや、休憩時間中に労働していたことが後から発覚するようなケースもあります。
不十分な健康管理
違反事項として3番目に多かったのは「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」で14.9%です。そのほかにも、事業者と外国人労働者の労働関係法の知識不足により、労働時間が守られていなかったり、年次有給休暇を取得できていなかったり、健康に就労できるような人事管理がきちんと行われていないケースがあります。
「技能実習生を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63807.html)をもとに作成
外国人労働者の不適切な管理によるリスク
外国人労働者に対する重大・悪質な労働基準 関係法令違反が認められた場合には、労働基準監督官によって送検される可能性があります。送検された事案は検察庁に引継ぎされ、検察官によって起訴され、有罪となった場合には拘禁刑や罰金刑が課される可能性もあります。
また、外国人労働者がケガをしたり、心身に不調をきたした場合には、会社に対して損害賠償請求をされる可能性があります。そのほかにも、労働環境が悪いことによって作業の質が低下したり、一斉にボイコットが行われたり、事業自体にも支障が生じるリスクがあります。さらに、外国人労働者を不当に扱っていることが発覚した場合には、取引先や消費者からの信頼は地に落ちるでしょう。外国人労働者に限ったことではありませんが、労働関係法令を遵守し、健康や安全、適切な賃金の支払いを実現することは会社側の責務です。
外国人労働者を雇用する際の法的なポイント
外国人労働者について少し理解が深まりました。外国人労働者を雇用する際には、具体的にどのようなことに気をつければいいでしょうか。
外国人労働者を雇用する際に注意すべき法的なポイントについて、採用から雇い入れの場面ごとに解説します。繰り返しになりますが、外国人労働者にも日本人と同様に労働基準法をはじめとした労働関係法令が適用されるため、各法律の要点を把握し、実務に落とし込んでいくことが重要です。
募集と採用の適正化
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して 事業主が適切に対処するための指針」には、外国人労働者が安心して働くことによって、きちんと能力を発揮できるように、会社側が講ずるべき措置について定められています。
募集の注意点
募集時に気を付けるべきポイントは、一例ですが下記のとおりです。特に、募集内容の明示については、労働契約の基礎となる部分ですので、双方の認識違いが生じないよう、求人票作成の際にはリーガルチェックを行うことをお勧めします。
■従事する業務内容・契約期間・就業場所・労働時間・休日・賃金・社会保険の適用等に関する事項を、募集時に書面等の残る形で明示しましょう。簡単な日本語や母国語で説明して、外国人労働者がきちんと理解できるようにすることがポイントです。
■国外から外国人を受け入れる場合には、渡航費用や帰国に要する費用の負担、寮などを用意するかしないかについても明確にしましょう。
■外国人労働者の派遣や、人材紹介を利用する際には、職業安定法や労働者派遣法を遵守している企業からあっせんを受けましょう。
■人材紹介会社に求人を掲載する際には、外国人労働者の国籍を指定したり、差別的な取扱いをしないようにしましょう。
■募集の際に書面にて明示した労働条件等を変更する場合には、変更後の内容も書面にて交付するようにしましょう。
採用の注意点
採用を行う際には、面接に来た外国人がきちんとルールを守って働けるかどうかを確認することはもちろんですが、在留資格についても注意して確認しましょう。就労の許されない在留資格を持つ外国人を採用しないようにしましょう。
適切な労働条件の確保
採用後には、外国人労働者の働く環境をきちんと整備する必要があります。具体的には、外国人労働者にも労働基準法をはじめとした労働関係法令が日本人と同様に適用されます。外国人労働者だからといって、労働関係法令が定める基準を下回った環境で就労させることはできません。
均等待遇・労働条件の明示
賃金・そのほかの労働条件の内容は、国籍を理由として差別的な取扱いにならないように注意しましょう。また、賃金や労働時間といった労働に関する重要な条件は書面で交付しましょう。
適正な賃金・労働時間
給与を決定する際には最低賃金を下回らないようにし、基本給や割増賃金は全額支給しましょう。食費や寮費を控除する場合には、労使協定や労働契約に基づいて行うようにし、不当に高額の控除にならないようにします。
また、適切な労働時間の管理にも努めましょう。時間外労働や休日出勤の発生を抑止し、タイムカードで客観的に勤務時間を記録することが重要です。また、年次有給休暇については一方的に取得の時期を決定せず、外国人労働者の意見を聞き、反映できるようにしましょう。
労働基準法等の周知
日本語の理解力が不足している外国人労働者も想定されます。自分の労働条件について十分に理解できていなかったり、理解不足からトラブルが生じる可能性がありますので、就業規則や労使協定については、外国人労働者が理解できるよう周知を行うようにしましょう。
雇用形態・就業形態と待遇
外国人労働者が短時間勤務、有期雇用労働者、派遣労働者であっても、一般的な労働者と比べて著しく待遇が低くならないよう、公平な待遇を確保するようにしましょう。また、これらの外国人労働者から質問されたり、説明を求められた場合には、一般的な労働者との待遇の違いについて、その内容と理由を明示するようにします。
労働者名簿・金品返還・寄宿舎
労働基準法等の規定に従って、労働者名簿、賃金台帳、有給休暇管理に関する帳簿を設けましょう。また、在留カードやパスポートは預からないようにし、寮などに外国人労働者を住まわせる場合には、健康や風紀の維持管理に努めましょう。
安全衛生の確保
外国人労働者が危険な環境で就労し、ケガを負ったりすることのないよう、安全衛生の確保にも努めましょう。安全衛生については、分かりやすい運用を目指し、機械器具の使用方法や健康診断の活用などを外国人労働者が理解できるようになることが重要です。
安全衛生教育の実施
安全衛生教育とは、労働災害を防止するために機械等の使用方法、使用材料の注意点について労働者に対して教育を行うことを指します。安全衛生教育は外国人労働者の母国語を用いたり、マニュアルやステッカーなどで視覚的に訴えかけて理解を深めることが重要です。
労働災害防止のための取り組み
安全衛生教育のほかにも、労働災害を防止するためには、日本語教育を行うことも方法も1つです。監督責任者の指示や合図を理解し、外国人労働者自身も正しい合図を身に着けられるようにしましょう。現場内でのコミュニケーションがスムーズになれば、突発的な危険やイレギュラーな状況から外国人労働者を守ることができます。
健康診断・健康指導・健康相談
健康診断、面接指導の実施をきちんと行うようにしましょう。健康診断を行うだけでなく、健康診断の結果に異常があった場合には当該外国人労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。(労働安全衛生法第66条の4参照。)
また、産業医や衛生管理者等の協力を得ながら、健康指導や健康相談を行い、外国人労働者の心身の健康増進に努めましょう。
母子保護等に関する措置
外国人労働者が女性である場合には、産前産後休業、要求に応じた妊娠中の軽い不可の業務への転換、時間外労働等の制限、妊娠中・出産後の健康管理のための措置を取るようにしましょう。
労働安全衛生法等の周知
労働安全衛生法の内容の周知を行い、外国人労働者が自身の権利を理解し、活用できるようにしましょう。具体的には外国人労働者に向けたガイドブックの作成、入社時の説明会、社内での相談窓口の設置なども方法の1つです。周知を怠った結果、外国人労働者を雇い入れる事業者としての義務を怠ったとみなされないようにしましょう。
社会保険の適用
社会保険の適用についても外国人労働者が理解できるように周知をし、保険給付の補助をするようにしましょう。社会保険制度になじみのない国籍の外国人労働者もいるため、給与から不当に控除されているという勘違いを防止し、不信感や不安感が芽生えないようにすることが重要です。
制度の内容・手続きの周知
社会保険の制度の内容と手続の周知についてのポイントは下記の通りです。
■労働・社会保険に係る法令の内容と保険給付の手続きを、外国人労働者が理解できる方法によって周知する。
■労働・社会保険に係る法令の規定に従い、外国人労働者(被保険者)に適用される手続きをとる。
■外国人労働者が退職したときは、資格確認書を速やかに回収し、国民健康保険または国民年金の適用の手続きが必要になることを伝える。
■外国人労働者が国民健康・国民年金に入る必要があるときは、役所での手続きに協力するように努める。
■労働保険(労災保険・雇用保険)の適用が任意の事務所でも、外国人労働者が求めた場合には労働保険の加入を行う。
保険給付の請求援助
■外国人労働者の退職時、雇用保険被保険者離職票の交付などの手続きを行う。
■失業等給付の受給に必要なハローワークの窓口を案内するなど、外国人労働者に必要な手助けを行う。
■労働災害等発生時、労災保険の給付請求手続きに関して。外国人労働者や家族からの相談に応える。
■外国人労働者が病気、負傷をして就業できない場合、傷病手当金が健康保険から支給され可能性があることを説明する。
■障害の状態になった場合は、障害年金が支給される可能性があることを説明する。
■外国人労働者が帰国するとき、公的年金の被保険者期間が一定期間以上の場合、帰国後に脱退一時金が支給される可能性があることを説明する。
人事管理・教育訓練・福利厚生
最後に、外国人労働者が長く、良好なモチベーションで就労するために必要な、人事管理や教育訓練について解説します。安全衛生や労働環境といった土台を整えたうえで、更なる環境整備を行いましょう。
人事管理
外国人労働者の職場への適応を促進するためには、社内規定や業務に関する文書の多言語化を目指し、スムーズなコミュニケーションを図りましょう。また、外国人労働者が業務に従事するにあたって、どのようなスキルが必要なのか、好ましい社員像を明確にし、評価基準、賃金や昇給の決定、異動配属については透明化を確保することが重要です。これらが不明確・不透明な場合には、職場内での不公平感ややる気の低下にも関わりますので要注意です。
生活支援
慣れない日本での生活・就労で、外国人労働者は心理的に大きな不安を抱えているケースがあります。また、文化の違いにより、住居や生活態度について近隣住民とトラブルに発展する可能性もあります。日本語や日本の生活習慣、文化、風習などを外国人労働者が理解できるよう指導しましょう。また、地域貢献や地域活動に参加し、外国人労働者が地域とのつながりや交流を深められるように協力することも大切です。
外国人労働者が日常生活に困らないよう、役所、病院、銀行などの生活に欠かせない場所について説明するとともに、必要に応じて同行し、安心して日常生活が送れるようにしましょう。
相談体制の構築
労働環境に関する苦情や相談に対応するための体制を構築することも必要です。具体的には社内に相談窓口を設置したり、労働環境や労働条件に不安があるときには特定の矢う蝕者に相談するように周知する方法があります。
教育訓練の実施
教育訓練を実施し、外国人労働者の母国語で採用後研修を行ったり、定期的な研修を行い、教育の機会を提供できるようにしましょう。外国人労働者の技能の向上、職場への定着のためにも、外国人労働者の自主訓練に頼るのではなく、教育環境を整備することが好ましいです。
その他の援助・配慮
その他にも、下記のような援助や配慮をするように努めましょう。
■寮の用意をする場合には、適切な施設の確保に努めましょう。
■在留期間の更新がない場合、雇用契約の解約を行い、帰国のための手続きについての相談に応じるようにしましょう。
■外国人労働者がやむを得ない事情(病気・事故等)によって帰国費用を工面できない場合には、一時貸付けを行うなど旅費の負担を行うように努めましょう。
■一時帰国をする場合、有給休暇をまとめて取得できるようにするなど、人員の調整に努めましょう。
■日本人労働者と外国人労働者が文化や生活習慣など、お互いの違いを認め合いながら働けるように配慮しましょう。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf)
- 外国人労働者は解雇できる?注意点を解説
-
せっかく採用した外国人労働者の勤務態度が思わしくない場合や、業務の習得が著しく遅いこと、また業務外(私生活)での素行が悪く会社に迷惑をかけてしまうことも、残念ながら可能性としては考えられます。会社としては速やかに解雇したいケースもありますが、前述した通り、外国人労働者にも労働関係法令が適用されるため、外国人の解雇を行う際には労働契約法に従って解雇を行う必要があります。
労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。安易な解雇や雇止めは、労働契約法違反となります。外国人労働者から地位確認の訴えが提起され、解雇が無効とされた場合には解雇日からの賃金支払いの必要が生じるリスクもあります。採用した外国人に対する解雇・雇止めを行うときはドラブル防止のためにも、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、解雇後の外国人労働者への援助として、関係企業への就職や職業訓練のあっせん、ハローワークとの提携ができるように努めましょう。
外国人雇用に関するQ&A
外国人労働者を雇用するときには、基本的には日本人労働者と同じように扱うことが大切なんですね。
そうですね。労働関係法令の適用については日本人労働者と同様に扱い、国籍における差別がないようにしなければなりません。外国人労働者は慣れない土地での就労というハンデを抱えていますので、スムーズな業務を実現する観点から、私生活での困りごとも会社としてフォローできるように体制を構築しましょう。最後に、企業様から問い合わせが多い質問について解説していきます。
外国人労働者にも労働基準法は適用されますか?
労働基準法は外国人労働者にも適用されます。労働基準法第9条には「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。また、第3条では「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定されています。
つまり、事業で使用されている(指揮監督下にある)者はすべて労働者であり、外国人労働者も該当し、外国人であることをもって日本人と異なる労働条件の取扱いはできないということです。一方で、国籍による差別は禁止されていますが、労働者としての能力を理由とした区別をすることが可能です。
技能実習生にも労働基準法は適用されますか?
まず、労働基準法は不法入国者・不法滞在者などの在留資格のない者(不法就労者)についても、事業で雇用されているときには適用されるという点に留意が必要です。雇用されているという点がポイントなので、実習実施機関と雇用契約を締結する技能実習生についても当然に適用されます。
一方で、団体監理型の技能実習生が入国時に受ける座学については雇用状態とはいえず、労働基準法は適用されません。また、農業に従事する労働者には特定の事項に関する労働基準法の適用はされないといった例外がある点には注意です。
外国人雇用の届出をしないとどうなりますか?
雇用対策法第28条では「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(以下略)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定されています。
外国人雇用の届出を怠った場合には指導・勧告の対象となるほか、30万円以下の罰金が違反した行為者だけでなく法人にも同様の刑が科される両罰規定が設けられているため、適切な届出を心がけましょう。
外国人雇用について分からないことがあるときはどうすればいいですか?
外国人労働者に雇用や管理で分からないことがある場合には、事業所を管轄するハローワークに問い合わせることにより、外国人雇用管理アドバイザーへ相談することができます。相談内容は下記の通りです。
■労務管理や労働条件が日本人と同様かどうか
■外国人労働者の日本語力に応じた職場環境かどうか
■職場環境や生活環境への配慮について
そのほかにも、相談内容に応じて各機関への相談が可能です。個別の事案に応じた具体的なアドバイスや、外国人労働者に関する幅広い包括的なアドバイスをお求めの場合には、弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談することをお勧めします。
外国人労働者の雇用に関するお悩み、リスク、課題は解決できます
今日はありがとうございました。外国人労働者には労働基準法などが適用されるが、日本人よりも特に配慮することが多い点に驚きました。外国人労働者の採用については、法律的な知識はもちろん、ビジネス的なノウハウを持つ先生にアドバイスをいただきたいと考えていますが可能でしょうか。
もちろん可能です。外国人労働者の雇用は難しさもありますが、昨今の人手不足の危機を脱するために有効な手段でもあります。法律を活用し、適切に外国人労働者を導入していきましょう。
この記事では、外国人を雇用しようとする企業の皆さまが、外国人を雇用する場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、外国人の採用・雇用についての専門的な法律の実務を得意にしています。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当事務所にご依頼いただくことで、
「外国人労働者を雇用する際に守るべき、労働基準法などの法令が理解でき、適切な運用をすることができる。」
「外国人労働者を雇用した後の疑問点を随時相談することができる。」
「外国人労働者の募集~離職・解雇まで、包括的な法律サポートを得ることができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「外国人労働者の採用を検討した時点から、労働基準法の適用など不明な点や疑問点を細かく相談できたので、スムーズに外国人労働者の雇用をすることができた。」
「雇い入れ後、運用面で分からないところや、判断が難しい問題が出たときにアドバイスをいただき安心感を持ってビジネスを進めることができた。」
「外国人労働者への制度の説明、苦情への対応、ルールの設定周知、現場を考慮したアドバイス、従業員への研修などもしていただいた。従業員、外国人労働者ともにいきいきと働くことができている。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年10月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00