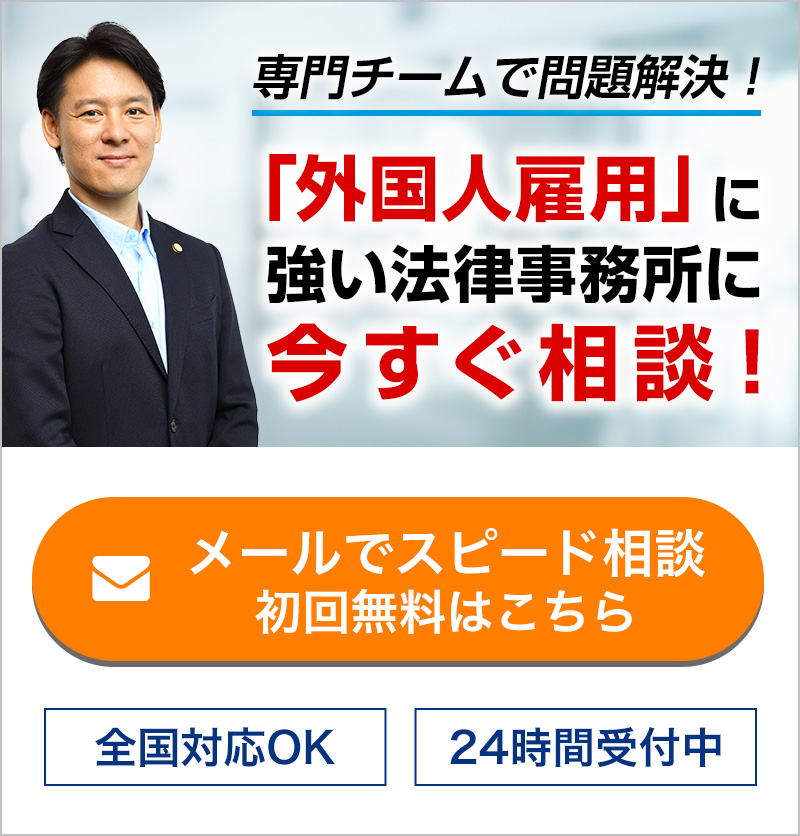目次
少子高齢化や労働力人口の減少に伴い、外国人労働者への関心が年々高まっています。しかし、誤った認識に基づき安易に採用をすると、後々問題に発展する可能性もあります。外国人雇用について企業の人事部・採用担当の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「外国人労働者を採用するメリットは何?」
「外国人労働者を採用するデメリットがあるの?」
「外国人労働者を雇用する際に注意点はある?」
「外国人労働者を採用したい場合の手順は?」
この記事では外国人労働者を雇用するメリット・デメリットをはじめ、注意点や採用手順についてまとめて解説します。
外国人雇用状況について
厚生労働省の発表によると、令和5年10月末時点で外国人労働者数は2,048,675人、前年比で225,950人増加しており、届出が義務化された平成19年以降過去最高を記録しました。国籍別ではベトナムが最も多く、518,364人、在留資格別では身分に基づく在留資格が最も多く、615,934人です。在留資格別では現時点では身分に基づく在留資格が一番多いものの、対前年増加比は専門的・技術的分野の在留資格、技能実習、資格外活動の順で伸びており、就労のためにビザを取得して働いている外国人が急増していることが分かります。
◆国籍別の状況
労働者数が多い上位3か国
ベトナム 518,364人
中国 397,918人
フィリピン 226,846人
対前年増加率が大きい主な3か国
インドネシア 56.0%増
ミャンマー 49.9%増
ネパール 23.2%増
◆在留資格別の状況
労働者数が多い上位3資格
身分に基づく在留資格 615,934人
専門的・技術的分野の在留資格 595,904人
技能実習 412,501人
対前年増加率が大きい上位3資格
専門的・技術的分野の在留資格 24.2%増
技能実習 20.2%増
資格外活動 6.5%増
◆産業別
外国人労働者数が多い上位3産業
製造業 552,399人
サービス業 320,755人
卸売業・小売業 263,555人
外国人雇用が多い上位3産業
卸売業・小売業 59,497か所
製造業 54,495か所
宿泊業・飲食サービス業 45,495か所
◆都道府県別の状況
外国人労働者数が多い上位3都府県
東京都 542,992人
愛知県 210,159人
大阪府 146,384人
外国人雇用をしている事業所数が多い上位3都府県
東京都 79,707か所
大阪府 25,450か所
愛知県 25,225か所
外国人労働者を雇用するメリット
外国人労働者を雇用することは企業にとっても大きなメリットがあります。事業拡大にあたり外国人雇用の活用も選択肢に入れてみましょう。
人材不足の解消
少子高齢化に伴う人材は特に中小企業にとっては大きな問題です。人材不足の状態が続くと、労働環境の悪化や従業員のモチベーション低下に繋がり、更なる離職や事業の縮小にまで発展してしまう恐れもあります。しかし、採用の対象を外国人にも広げることで優秀な人材を確保できる可能性が生まれます。
海外進出がしやすくなる
企業として多言語対応ができるようになると海外進出もしやすくなります。現地の言語や文化、慣習に精通した従業員がいることで商談でのコミュニケーションも取りやすくなります。また、現地の法律を知っていることで、安全にビジネスを発展させることが可能になります。外国人労働者は日本の文化や法律を学び、日本人労働者は外国人労働者から外国の文化や法律を学ぶことでお互いのビジネススキルを向上させることができます。
訪日外国人への対応が可能
企業として多言語対応ができることで、海外からのお客様対応の質を上げることができます。2023年の訪日外国人客数は2,507万人であり、コロナ前の水準に回復しつつあります。また、2023年の訪日外国人客の消費額は52,923万円であり、初めて5億円を超えました。訪日外国人向けのサービスを充実や、質を上げることで今後の収益アップが見込めます。特に観光業界と外国人雇用の相性は良いと言えます。
社内への良い刺激が生じる
自ら望んで母国ではない日本で働く選択をしている外国人労働者はとてもモチベーションが高い存在と言えます。また、日本人とは育ってきた環境も価値観が異なるので、新しいアイディアやサービスを生み出すきっかけになる可能性があります。
外国人労働者を雇用するデメリット
外国人労働者を雇用することはメリットだけでなくデメリットもあります。デメリットへの対処方法も検討した上で外国人労働者を受け入れることが大切です。
コミュニケーションが難しいことがある
日本への留学経験や就労経験の有無などにより、外国人労働者の日本語能力には個人差があります。特に日本語は「移動」と「異動」など同音異義語が多く、更に、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字の4種類の文字が入り混じり非常に複雑です。外国人労働者が日本語に慣れるまでは、細かい指示や複雑な話がうまく伝わらないことも考えられます。
外国人労働者が日本語に慣れるまではマメにフォローアップする、一緒にやってみる、可能な限りマニュアルは多言語化する、メンター制度を取り入れるなどの対策も検討しましょう。
文化や習慣の違いがある
海外には様々な文化や習慣があります。日本人が当たり前と思っている文化や習慣は海外では当たり前ではないこともあります。例えば日本の「おもてなし」文化は海外から高い評価を受けていますが、それは海外では珍しいからこその現象と言えます。日本は「空気を読む」など言葉以外の文脈や状況を重視するハイコンテクスト文化です。一方でアメリカなどの欧米はきちんと言葉で伝えるローコンテクスト文化です。お互いの文化を尊重せず自身の価値観だけで相手の言動を受け止めてしまうと誤解が生じ双方が傷付いてしまう可能性もあります。自国の文化や習慣をしっかりと認識し、相手の国の文化や習慣を理解し、尊重することでより良い関係性が築けます。
雇用管理において会社側にも多少の負担がある
外国人労働者が日本で働くためには就労ビザが必要です。そして就労ビザには1年・3年・5年の在留期間(有効期間)があり、在留カードに記載されています。この在留期間(有効期間)を超えて働いてしまうと外国人労働者は不法就労罪に、企業や人事担当者は不法就労助長罪に問われる可能性があります。基本的に在留期間(有効期間)の管理は外国人労働者本人が管理するものですが、雇っている以上企業側でも管理して、期間更新の確認や案内などを行うことが望ましいです。
また、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は、「外国人労働者の雇用労務責任者」の選任が必要になります。外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項についての管理や、関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当し、原則として人事課長や労務課長などの管理職の中から選任します。
外国人雇用に対する誤解について
外国人雇用が急増しているとは言え、まだ外国人雇用したことがないという企業も多いと思います。外国人雇用については誤った情報が出回っていることもありますので、正しい知識を身に着けていくことが大切です。
【誤解1】低賃金で雇える
外国人労働者にも最低賃金法は適用されますので、最低賃金未満で働かせることは違法です。最低賃金未満の労働契約に外国人労働者が納得したとしても、最低賃金が優先されます。また、就労ビザ取得の際には適正な賃金であるかの審査もあります。就労ビザ取得の際の適正な賃金とは「日本人と同等の賃金」であることを指します。例え最低賃金以上であっても、同じ仕事内容の日本人労働者と比べて正当な理由がなく低い賃金だと審査に影響があります。例えば、求人には月額30万円~と記載があるのに外国人労働者の月額賃金が20万円だと問題があります。ただし、「求人に出していたのは経験者採用だけれども、外国人労働者は未経験採用である」など説明できる正当な理由があれば問題ありません。求人の賃金額と外国人労働者の賃金額に差がある場合はきちんとその理由を説明できるようにしましょう。
【誤解2】すぐに働ける
人手不足問題が深刻な中、「就労ビザを取得して来月から働いてほしい」などすぐにでも活躍してもらいたい場面もあると思います。しかし一般的には、海外から呼び寄せる場合は3ヶ月~4か月、既に日本にいて就労ビザへの変更手続きを行う場合でも3ヶ月は見積もる必要があります。就労ビザへの変更申請を出したとしても、実際に許可が下りる前に働かせてしまうと不法就労になってしまうので、注意が必要です。
【誤解3】外国人労働者を雇いさえすれば助成金が受給できる
助成金は多種多様あり、中には外国人労働者も対象になっているもの、外国人雇用に特化したものもあります。しかし、残念ながらただ外国人労働者を雇うだけで利用できる助成金はありません。助成金は雇用保険が財源なので、原則として労働法を守っていることが大前提であり、法律以上の取り組みを行っている企業を対象としているものがほとんどです。外国人雇用に特化した「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は社内規程の多言語化や一時帰国のための休暇制度の整備などの取り組みをする企業が対象になります。また、助成額も必要経費の一部であり、全額支給されるものではないことにも注意が必要です。
外国人雇用の注意点について
外国人雇用はひとたび誤った手順踏んでしまうと定着率が低くなってしまったり、確認すべきことが抜けてしまうと不法就労罪に該当してしまう可能性もあります。注意すべきことをきちんと確認しましょう。
外国人雇用の目的を決めておくこと
優秀な外国人労働者を採用するためには「インバウンド対策」や「アウトバンド対策」、「職場の活性化」など外国人雇用の目的をきめておくことが重要です。外国人労働者は「この企業で自分は価値を提供できるのか」「そして何を(サポートなど)得られるのか」を見ています。しかし、採用担当者が外国人雇用の目的を理解できていないがために魅力的な自社アピールや採用目的を伝えられずに、採用したい外国人候補者を採れなかったという例があります。これから1から育成していくことを念頭に採用するのと、ある程度の経験者で即戦力を期待して採用するのかでも違ってきます。また、採用目的はできるだけ長期的な目線の方が賢明です。例えば、「離職が相次いでしまったから、とりあえず外国人を雇用しよう」としても、そもそもなぜ離職が相次いだのかの問題が解決しない限り、同じことが続く可能性があります。「外国人労働者に入社してもらって新しい風を吹かせたい」「多様性を推進し、風通しの良い職場にしたい」など今ある課題の解決策として外国人雇用を行うことが大切です。
就労可能なビザを保有していること
外国人が日本で働くためには就労可能なビザを保有している必要があります。ビザには様々な種類があり、中には「留学」「家族滞在」のように就労不可とされているものもあります。就労不可のビザにも関わらず、働いてしまうと不法就労と判断される可能性があるので注意が必要です。しかし、就労不可のビザであっても「資格外活動許可」を得れば原則として週28時間以内という条件付ではありますが働くことができます。資格外活動許可の有無は在留カードの裏面に記載がありますので、必ず確認するようにしましょう。
在留資格にあった業務内容であること
就労ビザは16種類あり、働く業務に合ったビザであることが求められます。就労ビザは保有していても、業務内容に合わないビザだった場合は不法就労と判断される可能性があります。外国人労働者を雇用する際には、必ず在留カードで業務内容に合った在留資格であるか確認しましょう。もし、業務内容に合っていない在留資格だった場合は、要件を満たしているか確認した上で業務内容の変更か在留資格変更許可申請を行うかの検討をします。短時間労働者であれば、資格外活動許可申請も選択肢に入れます。
不法就労助長罪に問われないよう管理すること
就労ビザを持たずに働いた場合、在留期間を超えて働いた場合、在留資格にあった業務内容でなかった場合など入管法に違反してしまった場合は、外国人労働者本人は不法就労助長罪に問われる可能性があります。しかし、罪に問われるのは外国人労働者本人だけではありません。企業や場合によっては人事担当者など個人としても不法就労助長罪に問われてしまう可能性があります。
不法就労助長罪は5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い罰則があります。外国人労働者は日本の制度に不慣れな場合もあり、ビザの制度についても完全に理解していない可能性もあります。企業側も入管法の知識を持ち、外国人労働者本人と一緒に在留期間などの就労ビザの管理を行うことが大切です。
無意識にパワハラの対象になってしまうことがあること
外国人労働者は日本人とは異なる文化や価値観を持っています。日本は、思ったことをハッキリとは伝えない傾向にありますが、海外には思ったことをしっかりと伝えるという文化の国もあり権利意識も強い傾向にあります。日本人であれば受け入れてしまうような言動であっても、外国人労働者にとっては苦痛に感じてしまう可能性もあります。
例えば、以下のような言動は外国人労働者にとってはパワーハラスメントだと感じてしまう可能性が高いです。
・締め切りを守ることを強く指導される
・期待の意味も込めて過度の業務を依頼される
・本来は他の人がすべき仕事を依頼される(欠勤の穴埋めなど)
・指導なしで働くよう強いられる
・嫌みや小言を言われる
・間違った際に怒鳴られる
パワーハラスメントは
・職場において行われる
・優越的な関係を背景とした言動であって
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
・労働者の就業環境が害されるもの
を指します。優越的な関係とは、必ずしも上司→部下とは限りません。先輩後輩や業務の経験年数などによっては同僚→同僚や部下→上司も当てはまります。業務上に必要な指導はあくまで業務に関することであり、○○をしてはいけないなど注意の矢印は「業務(行ったこと)」に向いている必要があります。「○○をするあなたはダメな人間だ」など矢印が人に向いてしまうとパワーハラスメントと認定される可能性が高くなってしまいます。また、「○○人はお金に汚い」など特定の国の人を悪く言う行為や「日本に来て何年だっけ?日本語分かる?」など外国人であることを強調した発言はパワーハラスメントに認定される可能性があります。業務上間違ってしまった場合や人に迷惑をかけてしまった場合は注意・指導が必要ですが、ただ怒って終わりではなく、「なぜその行為が誤っているのか」「改善するにはどうしたらいいのか」「今後の期待」も冷静に伝えることが大切です。ハラスメント問題は周りの従業員の士気にも関わってきますので、徹底して起こらないようにしましょう。
外国人労働者の採用手順について
募集
必要な人材をペルソナ化することがスムーズな外国人採用のポイントです。そして、ペルソナ像にあった募集方法を考えます。募集方法はリファーラル採用、人材紹介会社の利用、大学など教育機関への求人募集、自社のホームページ、ハローワークの利用、SNSの利用など多くあります。
◆リファーラル採用
知り合いや従業員から紹介してもらう制度です。似た方法に縁故採用がありますが、縁故採用は能力に関係なくほぼ100%採用するのに対し、リファーラル採用は紹介をしてもらうだけで必ずしも採用に至らない可能性がある点で違います。リファーラル採用はコストが低く、ある程度人となりや適性を知った上で採用できるので、マッチング率は高い傾向にあります。
◆人材紹介会社の利用
人材紹介会社によってはIT業界の人材紹介が得意など扱う業種や職種が異なります。ある程度欲しい人材の特徴を絞ることで即戦力の人材を紹介してもらえる可能性があります。また、希望にあった人材を選定して紹介してくれる点においても即戦力採用には向いています。しかし、紹介料は理論年収の30%が相場であり決して安くはありません。
◆大学など教育機関への求人募集
主に留学生の新卒採用やインターシップ採用が対象になります。一から育成することが前提になりますが、日本語や日本での生活に慣れている分コミュニケーションは問題なくとれる可能性が高いです。
◆自社のホームページ
代表者や従業員の声を顔写真付きで紹介することで企業に対しての親近感や実際に働くことへのイメージが持ちやすくなります。既に外国人採用をしている場合は、外国人労働者の声も載せることで安心感も与えることができるでしょう。また、自社のホームページであればタイムリーな更新が可能です。募集内容の変更や追加情報などにもすぐに対応することができます。さらに、自社のホームページを見て応募してくるのは、企業について興味を持ちきちんと調べ、企業の文化に共感している可能性が高いです。そのため、企業文化にマッチした人材が集まる可能性が高いです。家族や友人にも見てもらえるのも安心できるポイントです。一方で自社のホームページでしか採用していないと認知度の限界というデメリットはあります。
◆ハローワークの利用
ハローワークは登録料もかからず、幅広い求職者層にアピールできる強みがあります。一方でハローワークによっては十分な外国語対応できる職員不足により求職者のニーズに十分に応えきれない可能性もあります。
◆SNSの利用
最近では外国人採用に関わらず、SNSを採用活動のツールにする企業が増えてきました。SNSは無料で気軽に全世界にアクセスできるため幅広い求職者層にアピールできる強みがあります。また、リアルタイムでの更新できるので採用活動のスピードを上げることも可能です。また、採用情報だけでなく企業文化や社内の雰囲気も発信することでお客様サイドへのアピールも同時に行えます。しかし、幅広い求職者層にアピールできるがゆえに求めるスキルを持っている人材からの応募ばかりが集まるわけではない可能性はあります。
選考
採用ステップを簡略化することも優秀な外国人労働者の雇用対策になります。海外では日本に比べて採用ステップが短い傾向にあります。可能な限り「書類選考―一次面接―最終面接―内定」などスピード感を持った採用スケジュールにしましょう。また、入社後のミスマッチ率を低くするためにも、自社の理念や人事評価制度、労働環境は正直に伝えましょう。企業には良い面と反対の面があって当然です。一見マイナスに思えることでもきちんと伝えることでミスマッチ率が低くなるだけでなく、正直な姿勢が高印象になる可能性もあります。そして、選考の段階で在留カードの提示を求めることは国籍などによる差別防止の観点から適切ではないとされていますので注意が必要です。
内定
内定を出すときは、「適切な在留をしていると確認できない場合および適切な在留資格に変更を希望しない場合は内定取り消しになる」旨も伝えます。内定の段階ではまだ在留カードの確認をしていません。万が一在留期間が過ぎていた、本物かどうか疑わしい在留カードを提示された場合、就労するにあたり就労ビザ(在留資格)への変更を拒否された場合、就労ビザへの変更が許可されなかった場合に内定取り消しができるようきちんと伝えておくことが大切です。また、内定承諾書は書面でもらうようにしましょう。
在留カードの確認
内定承諾後に在留カードの提示を求め、在留期間内であるか、適切なビザ(在留資格)を持っているかの確認をします。適切なビザ(在留資格)を持っていなかった場合はビザ変更の手続きが必要なことを伝えます。また、在留カードはコピーや写真ではなく必ず原本で確認するようにしましょう。本物かどうか確認できるアプリも利用すると安心です。
労働契約の締結
労働契約の締結の際は誤解が生じないように、きちんと契約内容を説明することが重要です。例えば、残業の有無、固定残業代の範囲、社会保険料や雇用保険料、源泉所得税の控除は疑問を抱かれやすくトラブルに発展しやすいポイントです。特に控除されるものは納得してもらえない可能性もありますので、どういう制度なのかもあわせて伝えるようにしましょう。また、可能な限り母国語へ翻訳した雇用契約書(雇用条件通知書)も用意しましょう。
就労ビザの取得・変更
海外から呼び寄せて採用する場合には就労ビザ取得申請(在留資格認定証明書交付申請)、日本国内で採用して在留カードを確認した際に適切なビザ(在留資格)を持っていなかった場合は、就労ビザへの変更申請(在留資格変更許可申請)を行います。
・外国人の就労ビザを取得する方法|ビザ申請に強い法律事務所が解説
入社準備
入社書類の準備をすることはもちろんのこと、初めての外国人採用であれば既存の従業員に対しての研修を行い外国人雇用の理解を深めることも検討しましょう。研修の内容は主に外国人採用の主旨を伝える、価値観や文化の違いについての理解を深める、言ってはいけない言葉の例(特定の国への中傷と捉えられる可能性のある言葉など)、困ったことが起こった際の相談先(上司や人事部など)などがあげられます。
入社
オリエンテーションを実施し、企業の方針、労働条件、職場のルールなどについて伝えます。特に、労働時間(残業含む)や休憩、休日、評価制度については揉めやすいポイントなので具体的に伝えることが重要です。流れ作業にならないようより丁寧な対応を心がけます。外国人労働者に用意してもらうものについては一覧表にまとめて渡すと分かりやすいです。また、可能な限り資料を翻訳することも検討します。そして、質問の機会を与えできるだけ疑問はその場で解消できるようにしましょう。
外国人労働者の入社手続きについて
入社後に発生する手続きも漏れがないように注意しましょう。
労災保険
労災保険は企業に雇用される労働者全員が対象になります。副業であってもそれぞれの企業で加入しますが、特に加入にあたり手続きは必要ありません。毎年6~7月に行われる年度更新の際に外国人労働者への賃金も含め確定保険料と概算保険料を計算して納付します。
雇用保険
雇用保険は週20時間以上働く労働者が対象になります。副業の場合は主たる勤務先で加入します。「雇用保険被保険者資格取得届」を資格取得日の翌月10日までにハローワークに提出します。また、週20時間未満の労働契約などで雇用保険取得対象者ではない外国人労働者は「外国人雇用状況の届出」が必要です。
社会保険
社会保険は企業で社会保険に加入している人が51人以上いる場合は以下の条件を満たす場合に加入が必要です。
・週20時間以上勤務
・月額報酬が88,000円以上(通勤手当は除く)
・学生でない
・2か月を超える雇用の見込みがある
企業で社会保険に加入している人が50人未満の場合は正社員の4分の3以上の所定労働時間の場合は加入義務があります。
また、社会保険の加入手続きの際にはマイナンバーの届出も必要ですが、マイナンバーと基礎年金番号の情報が紐づいていない場合はあわせて「ローマ字氏名届」の提出も必要です。
就労資格を有する中長期在留者等に関する届出手続
「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ中長期在留者(日本に3ヶ月以上滞在する在留資格を有し、かつ「短期滞在」や「外交」「公用」の在留資格を有しない外国人)を雇用する企業(外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除く)は出入国在留管理庁長官に対し、「中長期在留者の受入れに関する届出」を行います。
外国人の採用・雇用の手続についてのお悩み・課題は、解決できます
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、外国人雇用のメリット・デメリットについての相談や、雇用に関する手続のご支援など、外国人雇用に関する法務サービスを総合的にご提供する、外国人雇用マネジメントサービスを行っております。外国人雇用は人材不足を解消し、企業の成長の可能性を高める手段として有効です。一方で入管法関連の制度が複雑であること、言葉の壁や文化・価値観の違い、手続きの煩雑さなどから決して気軽にできるものではありません。また常に最新の法改正を追うのも労力がかかります。しかし、適切な手順をふまないと自社にあった優秀な外国人の採用ができなかったり、採用できても長続きしなかったり、就労ビザが取得できなかったという事態に陥ってしまう可能性があります。当法律事務所では、外国人雇用以外にも、就労ビザの代表格である技術・人文知識・国際業務ビザや高度専門職ビザ、特定技能ビザについての相談サービスも行っております。スタッフ全員が行政書士の資格を持ち、弁護士の指導のもと、外国人雇用・ビザ申請・労務・契約書など、法務の専門知識を持ったプロフェッショナルがそろっています。ご安心してご相談ください。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、外国人の採用・雇用についての専門的な法律の実務を得意としています。
また、オンラインを活用したスピード感のある業務に定評があります。
当法律事務所にご依頼いただくことで、
「候補者のビザが現在の業務に適しているか確認でき、安心して採用できるようになる。」
「必要な場合はビザの変更手続きを代行してもらえて、手続きに時間を取られずに済むようになる。」
「就労ビザの申請に必要な手順が明確になって、スムーズに手続きできるようになる。」
「ビザの審査にかかる期間の見通しが立ち、採用計画が立てやすくなる。」
さらに、
「外国人との雇用契約書の注意点が分かり、法律的に問題なく作れるようになる。」
「学生ビザ(アルバイト)から就労ビザ(正社員)への変更手続きを正確に進められて、不安なく雇用できるようになる。」
しかも、
「日本に来た後のフォローアップやサポート体制について、適切なアドバイスを受けられるようになる。」
このようなメリットがあります。全力でご支援させていただきます。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視するクライアントの皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
こちらから「メールでスピード相談」ができます。
※本稿の内容は、2024年11月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。
執筆者:弁護士小野智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
当事務所のご支援事例
| 業種で探す | ウェブ通販・越境EC | IT・AI | メーカー・商社 | 小売業 |
|---|
| サービスで探す | 販路開拓 | 不動産 | 契約支援 | 現地法人運営 | 海外コンプライアンス |
|---|
ご相談のご予約はこちら

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所
(代表弁護士 小野智博 東京弁護士会所属)
03-4405-4611
*受付時間 9:00~18:00